「釣り堀でシマアジを狙ったけど全然釣れなかった…」そんな経験はありませんか?シマアジは視力が良く警戒心も非常に強い魚で、エサを**「吸って吐いて」**と何度も吐き出すためアタリも取りづらく、釣るのが難しいとよく言われます 。しかしコツさえ掴めば、マダイほど簡単とはいかないまでも初心者でも確実にシマアジを釣り上げることは可能です 。本記事では、海上釣り堀でシマアジを確実に釣るための仕掛けやエサ選び、誘い方のテクニックを初心者向けに分かりやすく解説します。難攻不落のシマアジ攻略法をマスターして、釣果アップと美味しいシマアジの味わいを両方手に入れましょう!
シマアジの特徴と釣り堀での動き方
シマアジは回遊性が高く、釣り堀のイケス内を数匹の群れで泳ぎ回る習性があります 。放流直後や魚の活性が高いときは水槽の中層〜上層まで活発に動き回り、エサを探して回遊します。一方、時間が経ってプレッシャーが掛かったり活性が落ちてくると、シマアジはより深場の中層~底付近へ移動しがちです。実際、海上釣り堀ではマダイより浅い層(中層付近)にシマアジがいることが多いですが、寒い冬場など水温が低い時期には底付近に溜まって動きが鈍くなる傾向があります。季節や時間帯、水温によって群れの泳ぐレンジ(層)が変化するので、シマアジの群れの動きを見極めることが釣果アップの鍵となります。
釣り堀内でのシマアジは警戒心も非常に強く、エサや仕掛けに少しでも違和感があると口を使いません 。特に漂っているエサには反応せず、目の前に落ちてくるエサだけを見つけて食べる習性があります 。そのため、狙ったシマアジの目の前にエサを届けることが重要です。群れが回遊しているコースや層を予測し、そこにタイミング良くエサを投入することでヒット率が大きく上がります。
釣れる時間帯やシーズン
釣れる時間帯
釣り堀でシマアジを狙うなら、時間帯とシーズンも見逃せません。まず狙い目の時間帯は朝イチと放流直後、そして夕方です。朝一番のモーニングタイムは、前日から釣れ残った魚たちがお腹を空かせているため食い付きが非常に良好で、手早く仕掛けを投入すれば次々とヒットが期待できます 。釣り開始から1~2時間後に行われる放流直後も絶好のチャンスタイムです。魚が放たれてわずか5分ほどで活性が一気に上がり、次々とエサに食いついてくるので、放流のタイミングには万全の準備を整えて臨みましょう 。また、日没前後の夕方も魚の活性が上がりやすく、良い釣果が期待できる時間帯です 。朝方や夕方は光量が落ち着き魚の警戒心も和らぐため、比較的シマアジも口を使いやすくなります。
釣れるシーズン
シーズンでは、一般的に夏から秋がシマアジ釣りのベストシーズンとされています 。水温が18~24℃程度の暖かい時期はシマアジの活性も高く、エサへの反応も良好です。特に夏~秋にかけては産卵前で体に脂が乗り始めるため、釣ったシマアジの食味も最高の時期です 。一方、冬場は水温低下でシマアジの動きも鈍くなりがちで、活性が下がる「渋い」状態になることがあります。そのような活性が低い時は、シマアジがいるレンジも深め(底近く)になりやすいので、思い切ってウキ下を底付近まで下げてみるのも手です。エサへの反応が鈍い場合は、できるだけ違和感の少ない小さめのエサや動きの少ないエサでじっくり誘うなど、アプローチを変えてみましょう。季節や時間に応じて適切な戦略を取ることで、難しいシマアジ釣りでもチャンスを確実につかむことができます。
仕掛けの選び方(ウキ釣り・ミャク釣り)
シマアジを釣るにはウキ釣りとミャク釣り(探り釣り)という2つの代表的な釣法があります。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けることで釣果アップが期待できます。
ウキ釣り
ウキ釣りの場合、タナ(棚)を正確に合わせることが何より重要です。シマアジは警戒心が強いため、エサが泳いでいる層(レンジ)がズレていると決して食いつきません 。まずは釣堀スタッフなどからシマアジのいる深さの情報を得てウキ下(ハリスの長さ)を設定し、魚の反応を見ながら細かく調整しましょう 。一般的にマダイ狙いよりやや深めの中層~底近くを狙うと良いですが、その日の状況で変わるので臨機応変に探ってください。また、仕掛け自体もできるだけシンプルかつ繊細にするのがポイントです。シマアジは太い仕掛けや大きな針だとすぐに見切ってしまうため 、ハリス(リーダー)はフロロカーボンの約3号前後と比較的細めにし、針もグレ(メジナ)やチヌ用の小針サイズ3号~8号程度を選ぶと良いでしょう 。違和感の少ない細仕掛けにすることで、シマアジの繊細なアタリも逃さず捉えやすくなります。ウキ釣りは仕掛けを遠くに投入でき、決めたレンジにエサを安定して留められる利点があるので、魚がイケスの中央付近に固まっている場合や広範囲を探りたい場合に適しています。
ミャク釣り
ミャク釣り(脈釣り)はウキを使用しない釣法で、道糸にオモリと針だけという非常にシンプルな仕掛けです 。ウキがない分、仕掛けの投入から回収までの手返しが早く、何よりも感度が抜群なのが特徴です。道糸と竿先が一直線に繋がるため、エサにつつくわずかな変化も手元にダイレクトに伝わります 。シマアジのようにアタリが小さい魚でも、ミャク釣りならではの微細なアタリを捉えて掛けることが可能です。またミャク釣り最大のメリットは、素早く自由にレンジ(タナ)を上下調整できる点にあります 。リールのカウンターを見ながら狙いたい水深まで一気に仕掛けを沈めたり、逆に巻き上げて別の層を探ったりと、短時間で色々なレンジを探ることができます。この機動力の高さは、回遊しているシマアジの群れを探り当てるのに非常に有効です。
一方でミャク釣りのデメリットとしては、基本的に竿の真下近くしか狙えないため攻略範囲が限られることが挙げられます 。自分の足元から竿の長さ程度の半径(数メートル圏内)が射程範囲となるため、イケスが大きく魚が中央に固まっている場合には仕掛けが届かず攻略しづらいです。そのような状況ではウキ釣りで遠投して狙う方が効果的でしょう。逆に、自分の足元付近までシマアジの群れが回ってきている場合や、活性が高く上層まで浮いてきている場合には、ミャク釣りで手敏くアタリを取りながら狙うのが有利です。状況に応じてウキ釣りとミャク釣りを使い分けることで、シマアジの攻略率が格段にアップします。
おすすめのエサとその使い方
シマアジは雑食性で食欲旺盛な魚のため、好むエサの種類も幅広いです。海上釣り堀で実績のある定番エサだけでも、配合餌のダンゴ(練り餌)、オキアミ(エビの一種)、甘エビ・シラサエビなどのエビ類、イワシやキビナゴなどの小魚の切り身、さらには虫エサ(ゴカイ類)まで、多岐にわたります 。基本的にはマダイや青物狙いに用いるエサで代用できますが、その日のシマアジの嗜好や活性によって当たり餌が変わるため、複数種類のエサを用意してローテーションすることが大切です 。
おすすめのエサ
初心者にも扱いやすくシマアジに効果的なエサとしてまず挙げられるのが、冷凍オキアミ(エビ)です。オキアミは多くの海水魚に好まれる定番餌で、シマアジも例外ではありません。また、生のエビ(シラサエビやブツエビなど)が手に入る季節であればぜひ持参しましょう。シラサエビはシマアジの大好物で、「シラサエビしか食わない」ような渋い日でも効果を発揮する切り札です 。ただし春~夏以外の時期は釣具店で入手しにくいこともあるため注意が必要です 。ほかにもイワシの切り身やキビナゴといった小魚の切り身餌、アオイソメなどの虫餌が有効な場合もあります。釣堀専用の練り餌(配合餌)では、黄色く着色された視認性の高いダンゴ餌がシマアジ攻略に人気です。たとえば市販の「マダイイエロー」や「シマアジ用配合餌」などは、海中で目立ち扱いやすいため初心者にもおすすめです 。日によってシマアジの好む餌は変わるため、活性が高い時はアピールの強い餌(派手な色・匂いの餌)で積極的に狙い、食い渋っている時は餌のサイズを小さくしたり匂い控えめのものに変えるなど工夫してみましょう 。
エサの付け方
エサを用意するだけでなく、付け方にもひと工夫が必要です。シマアジはエサの不自然な動きを極端に嫌うため、できるだけ自然に漂わせることが重要になります 。例えばオキアミやエビ類をつける場合は、針が目立たないようエサの頭部や尾の付け根から刺し、エサがまっすぐ水中に沈むように付けます 。針先がエサから飛び出していたり、エサの重心が偏ってクルクル回転して沈むような状態だとシマアジは違和感を抱いて見切ってしまいます。同様に練り餌(ダンゴ餌)を使う場合も、針全体をしっかり餌で包み込みつつ、なるべく小さく丸めてください 。シマアジは口が小さめで吸い込みも弱いため、大きすぎる餌玉だと吸い込み切れずに吐き出されてしまうことがあります。エサ付けは「針を隠しつつ小さく」が基本です。細かいポイントですが、この付け方次第でシマアジの食い込みが大きく変わるので、面倒がらずに毎投丁寧にエサを付け直しましょう。
エサのローテーション
さらに、釣り堀ではエサのローテーションも効果的なテクニックです。シマアジは群れで行動していても個体によって食いつきやすいエサが異なることがあります。あるエサで反応がなければ別の種類に替えてみる、といった風にいくつかのエサを順番に試すことで、その時その場所での当たり餌を見つけられる可能性が高まります 。活性が高い時ほど欲張って何でも食べてきますが、活性が低い時ほどエサの好みが偏る傾向があるため、 「エサを変える」という選択肢 を常に頭に入れておくとよいでしょう。
誘い方とアワセのコツ
肝心なシマアジの誘い方
シマアジを釣る上で、誘い方とアワセ(合わせ)のタイミングも極めて重要です。シマアジはじっと漂っているエサより、ゆっくり動いて沈んでいくエサに強く反応する習性があります 。そのため、ウキ釣りでもただ待つだけでなく、ときどき竿を軽く上下させてエサに変化を与える「誘い」を入れると効果的です。ポイントは小さな動きでエサをふわふわと漂わせるように見せること。例えばウキ下を少し短めにしておき、ゆっくり竿先を上げ下げしてエサを上下に揺らすことで、エサがヒラヒラとスローフォール(ゆっくり沈下)する状態を演出できます。実際、練り餌を平たくつぶしてヒラヒラと落とすスローフォールでシマアジをヒットさせた例も報告されています 。急激に動かしたり大きく煽ったりするとシマアジが警戒して散ってしまうので、ゆっくり柔らかい誘いを心がけましょう。「動かしすぎない」ことがシマアジの誘いでは肝心です。
誘いを入れてエサを目の前に送り込んでも、シマアジはすぐには食いつかないことも多いです。エサを見つけてもすぐには飲み込まず、前述のように一度口に含んでは吐き出すような慎重な食べ方を繰り返します 。ウキ釣りの場合、ウキがスッと沈んでもそれはシマアジがエサを吸い込んだ瞬間で、まだ針まで食い込んでいない可能性があります。焦ってすぐに合わせると、エサだけ吐き出されて針掛かりしないことが多いです。アワセのタイミングは他の魚以上に慎重に見極めましょう。ウキが明確に消し込んだ後も少しだけ我慢し、竿先や道糸から手元にグッと魚の重みが乗った瞬間まで待つのがコツです(※ただし待ちすぎると吐き出されるので注意)。ミャク釣りの場合も、竿先にコツコツと小さいアタリが出た時点では合わせず、竿先がゆっくりと絞り込まれる(もたれる)感触が伝わった時に素早く合わせると成功率が高いです。
合わせのコツ
シマアジに掛け合わせる際は、力加減にも気を付けましょう。シマアジは引きが強烈で重量感のあるファイトを見せますが、その反面口が非常に柔らかいという弱点があります 。青物(ブリやカンパチ)のように勢いよく大アワセをすると針が口穴を広げてしまい、走られた拍子に穴が裂けてバレてしまう(口切れ)ことが少なくありません 。合わせは「素早く、しかし強すぎない」力加減で、竿をスッと立てる程度にとどめるのが理想です 。フッキングが決まった後も油断は禁物で、掛かったシマアジは縦横無尽にイケス内を走り回ります。他の人の仕掛けとオマツリ(絡まること)しやすいので、掛かったらすぐに**「シマアジ掛かりました!」**と周囲に声をかけて知らせるようにしましょう 。周囲の協力も得つつ、シマアジの走りをいなして弱らせ、浮いてきた隙に素早くタモですくって取り込みます。暴れるシマアジを強引に巻こうとすると前述の通り口切れでバラしやすいので、ドラグを適度に緩めに設定し、走られたら無理をせず糸を出して耐えることも大切です。慎重かつ的確なやり取りで、貴重なシマアジを確実にキャッチしましょう。
最後に、シマアジは群れで行動する魚ですから、一匹掛かった後も同じ群れが近くにいる可能性が高いです。ヒットがあったタナやエサをしっかり覚えておき、そのパターンを次に活かすことで効率よく連続ヒットを狙えます。同時に、群れは常に移動していますので、しばらくアタリが遠のいたら群れが離れたサインと考えましょう。タナを再度変えて探ったり、思い切って隣の釣り座との間のポイントを狙ってみるなど、群れの居場所を探す工夫を続けることが肝心です。
釣れない時の対処法
どれだけ工夫してもシマアジが釣れない…そんなときは以下のポイントを再チェックしましょう。
■タナの微調整
シマアジは群れで移動するため、一箇所で釣れてもすぐに群れが散ってしまうことがあります。逆に言えば、タナさえ合っていないと群れがいても全く釣れません。釣れないと感じたらまず疑うべきはタナ設定です。仮に周囲でシマアジが釣れているなら、その人と同じウキ下に合わせてみます。一方、自分以外誰もシマアジが上がっていない場合は群れのレンジを探る必要があります。開始直後に釣れたタナで反応が途絶えたら、同じ深さに固執せず再度上から下まで探り直しましょう 。例えば水面下3mから始め、5m、7mと順にレンジを変えて落としてみる、といった具合です。通常、同じタナで釣れてもせいぜい2~3匹程度で群れのレンジが変わることが多いので、アタリが止まったら粘りすぎず群れの高さを探し直すのが得策です 。また、群れが自分の正面から移動してしまった可能性もあります。他の釣り人がシマアジを掛けたら、その方角やタナを参考にして狙いを修正しましょう。
■エサのサイズ・種類の変更
シマアジが全く口を使わないときは、思い切ってエサを変えてみるのも有効です。同じエサばかり使っていると魚に見切られている可能性があります。例えば、ずっとオキアミを付けて反応がないなら、シラサエビや練り餌、小さめのキビナゴなどエサの種類や大きさを変えてみると突然ヒットすることがあります 。活性が低い時ほど「食わせエサ」を見極める必要があるため、エサのローテーションで反応を探りましょう 。実際、釣り堀では放流直後の活性が高い魚が一巡すると残りの魚はスレて食い渋ることが多いですが、ここからが腕の見せ所です 。魚の目先を変えるように、エサを小さくしたり活きエサに替えるなどアプローチを変えてみてください 。それでもダメなら、配合餌に集魚剤を混ぜてみるなど少し強めのアピールに振ってみる手もあります (※市販の魚寄せパウダー等を活用)。要するに、**「同じことを繰り返さない」**のが釣れない状況を打破するコツです。
■周囲の釣れている人を参考にする
自分だけ釣れずに周りが釣れている場合は、素直に上手な人のやり方を真似するのが近道です。遠慮は無用ですので、その釣り人に「何mくらいのタナで釣れましたか?」「エサは何を使っていますか?」と聞いてみましょう。釣り好きの方は親切に教えてくれることが多いですし、話しかけにくければそっと観察するだけでも得られる情報はあります。釣れている人の仕掛けの投入場所やタイミング、ウキの動き方などを注意深く観察し、自分の釣り方と違う点があれば積極的に取り入れてみましょう。また、釣堀のスタッフに状況を尋ねるのも有効です。「今シマアジはどのあたりにいますか?」「オススメのエサはありますか?」と聞けば、リアルタイムな攻略ヒントをもらえるでしょう 。プロの意見や他の釣り人の技術を取り入れることで、自分では気付けなかった改善点が見えてくるはずです 。
以上のように、シマアジが釣れないときはタナ・エサ・釣り方の再チェックと情報収集が肝心です。一手間加えることで状況が一変することも珍しくありません。「釣れない…」と諦める前にできることを実践し、貴重な一匹に繋げましょう。
釣ったシマアジの持ち帰り・食べ方
念願のシマアジを釣り上げたら、最後に大事なのが持ち帰りまでの処理です。シマアジは高級魚だけあって鮮度によって味が大きく変わります。せっかく釣れたシマアジを最高の状態で持ち帰り、美味しく味わうために、以下の処理を徹底しましょう 。
■締め方(鮮度保持の基本処理)
魚を美味しく持ち帰るための三原則は、①即殺(暴れさせない)、②血抜き(腐敗防止)、③保冷(温度管理)です 。シマアジが釣れたら、まずは活き締めを行います。具体的には、エラ蓋を開いてエラの付け根をナイフやハサミで切り、心臓が動いているうちに血を抜きます。海水を入れたバケツの中で魚を泳がせるように動かし、しっかりと血を吐かせましょう 。可能であれば神経締め(脊髄にワイヤーを通して脳死させる処理)も行うと完璧ですが、難しければ血抜きまでで構いません。血抜きが終わったら、素早く氷締め(冷却)に移ります 。海水と氷を入れたクーラーボックス(潮氷)を用意し、その中にシマアジを浸けて急速に冷やします。氷水に浸けることで魚体を静かに確実に絶命させると同時に、鮮度の劣化を防ぎます 。ポイントは常に魚を暴れさせないことです。暴れさせてしまうと身に乳酸が溜まり、せっかくの旨味成分が消費されて味が落ちてしまいます 。釣れた喜びで写真を撮ったり計量したりしたくなりますが、締め処理は一刻を争います。記念撮影は締め処理後にゆっくり行うくらいの気持ちで、まずは締めと血抜き・冷却を最優先してください。
■持ち帰り後の下処理
自宅に持ち帰ったら、できればその日のうちに内臓とエラを取り除きましょう(内臓は傷みやすく腐敗しやすいため)。捌く時間がない場合も、エラブタからハサミを入れてエラと内臓だけでも抜き取っておくと鮮度が保てます。下処理したシマアジはキッチンペーパーで表面の水気を拭き、ラップに包んで冷蔵庫で保管します。シマアジは釣ってすぐよりも一日程度寝かせ(熟成させ)た方が身に旨味が回って美味しくなる魚です。釣り当日の夜に食べたい気持ちをぐっと堪えて、翌日以降まで冷蔵熟成させるのもおすすめです(※鮮度管理がしっかりできていれば2~3日程度熟成可能です)。
■美味しい食べ方
締めたシマアジは鮮度抜群。ぜひお刺身でその脂の乗った身を堪能しましょう。シマアジの刺身は透明感のある上品な身質で、噛むごとに甘みと旨味が広がります。ほんのり桜色がかった身は見た目にも美しく、高級魚ならではの味わいです。シマアジは皮下に脂があるので、皮付きのまま湯引きして薄造りにする「松皮造り」や、軽く酢締めにするのも絶品です。刺身以外では、シンプルに塩焼きもおすすめです。適度に脂の乗った身は焼くとふっくらジューシーで、旨味が凝縮された白身の美味しさを堪能できます。塩焼きにする場合は、釣った当日などなるべく新鮮なうちに調理すると臭みもなく絶品です。また、アジ科の魚の料理として有名ななめろう(身を叩いて味噌や薬味と和えた郷土料理)もシマアジで作ると格別です。シマアジの甘みの強い身となめろうの風味がよく合い、ご飯のお供やお酒の肴に最高でしょう。ほかにも漬け丼、カルパッチョ、フライやムニエルなど、シマアジは和洋問わず様々な料理で楽しめます。釣り人ならではの贅沢な食卓をぜひ満喫してください。
まとめ
海上釣り堀でのシマアジ釣りは難易度が高い分、上手くハマったときの喜びもひとしおです。本記事で解説したように、
•シマアジ攻略の鍵は群れの動きを見極めてタナを合わせること! 警戒心の強いシマアジ相手にはレンジコントロールが命です。
•仕掛けやエサ、誘い方を工夫すれば初心者でも釣果UPは可能! 細仕掛け・エサローテーション・スローフォールの誘いなど、小さな工夫の積み重ねがシマアジとの距離を縮めます。
•釣れたシマアジは丁寧に締めて鮮度を保持し、美味しく味わおう! 釣り人の特権である新鮮シマアジを存分に堪能してください。
最初は難しく感じるかもしれませんが、経験を積むほどシマアジ釣りのコツが掴めてくるはずです。ぜひ諦めずにチャレンジし、釣り堀シマアジならではの爽快な引きと、美味しい食体験を味わってください。あなたの釣果アップを応援しています!


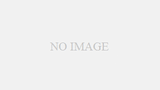
コメント