秋にアオリイカを釣ってみたいけど、「エギングって難しそう…」と思っていませんか?実は、秋の堤防エギングは初心者にも最適な釣りなんです!秋はアオリイカの数釣りシーズンで、専用タックルさえ揃えればシンプルな仕掛けで楽しめます。この記事では、初心者が揃えるべき道具・基本の釣り方・釣れる時間帯・コツ・関西のおすすめ堤防スポットまで完全網羅!これを読めば、週末には堤防でアオリイカデビューできますよ。
アオリイカってどんな魚?秋が狙い目の理由とは?
アオリイカの特徴と魅力
アオリイカは「イカの王様」とも呼ばれるほど人気の高いターゲットです。その最大の魅力は、釣って楽しく食べて美味しいことにあります。まず食材としての価値は折り紙付きで、刺身や天ぷら、唐揚げ、バター焼きなど様々な料理で絶品の味わいを楽しめる高級食材です 。釣り上げてすぐに捌いて食べる刺身の甘さは格別で、自分で釣ったイカならではの特権と言えるでしょう。
さらに、釣りの対象としてもファンが多い理由の一つがその**強い引き(ファイト)**です。アオリイカは軟体動物とは思えないほど力強く抵抗し、ジェット噴射でグイグイとドラグを鳴らします。「こんなにイカの引きって強いの!?」と驚くほどで、その思いがけないパワフルさに魅了されエギングの虜になる人も多いです 。実際にアオリイカを掛けると、根掛かりと間違えるようなズシッとした重みの後、一気にラインを引き出されるスリルを味わえます。釣って楽しく、食べて美味しい――この二重の魅力がアオリイカ釣り人気の秘訣なのです。
なぜ秋がエギングのベストシーズンなのか
アオリイカ釣りは春と秋が二大シーズンと言われますが、中でも秋は初心者にとってベストシーズンです。その理由は、秋が「新子(しんこ)」と呼ばれる生まれた年の子イカが成長する時期だからです。春に孵化したアオリイカは夏を経て秋に100g前後に育ち、堤防から狙えるサイズになります 。小型ながら数が非常に多いため、この時期は数釣りが楽しめるのが特徴です。実際9~10月頃はイカが広範囲に散らばっており、シャロー(浅場)からディープまで色々な場所にいるので、初心者でも出会える確率が高くなります 。
さらに秋は水温やエサ(ベイト)、潮の状況などもイカ釣りに好条件が揃います。水温は22℃前後とアオリイカの適水温域に近く、活発にエサを追い回すため活性が高いです 。夏に生まれた小魚(イワシやアジなど)も秋には岸近くに多く、アオリイカにとって豊富なベイトが接岸するので絶好の捕食シーズンとなります。潮通しの良いポイントではエサとなる魚が集まりやすく、それを狙ってイカも集まる好循環が生まれます。また秋は台風明けで海に栄養が行き渡り、水温も徐々に下がってイカに適した環境が整います。
同じ秋でも9月上旬はイカがまだ小さくリリースしても弱ってしまう個体が多いですが、水温が少し下がる10月頃になるとサイズが手頃になり活発にエサを追い始めます 。この頃は「子イカシーズン」と呼ばれ、引きの強さと数釣り両方を楽しめる絶好の時期です 。つまり、大型を狙うなら春ですが、数を釣りたいなら秋。特に初心者にとっては秋に数釣りを経験して成功体験を積むことで、自信を持ってエギングにハマるきっかけになるでしょう。
初心者でも釣れる!秋の堤防エギングの魅力
堤防エギングが初心者に向いている理由
アオリイカ釣りは磯やサーフ(砂浜)など色々な場所で楽しめますが、初心者には堤防からのエギングが断然おすすめです 。その最大の理由は、堤防は足場が平らで安定しており安全だからです。高低差のある磯場やグラグラするテトラポッドの上では、キャストやシャクリ動作に集中しづらく、バランスを崩して危険な場合もあります。堤防なら地面がコンクリートでしっかりしているので、初心者でも安心して釣りに集中できます。また服装も磯のように本格的なブーツやライフロープを必要とせず、軽装で気軽に楽しめるのもメリットです。
さらに、人気の堤防では周囲に他のエギング愛好者が多く情報交換がしやすいという利点もあります。ときにはベテランの釣り人が近くにいて様子を見られるので、「どんなシャクリをしているのか」「どのエギを使っているのか」など自然と学べますし、声を掛ければアドバイスをもらえることもあります。人通りがある堤防は防犯上も安心です。まず堤防から始めれば、1杯目のアオリイカに出会える確率は高く、成功体験を得やすいでしょう。「堤防を制する者はエギングを制す!」と言っても過言ではありません。実際、足場の悪い地磯ではシャクリやフォール姿勢の安定が難しいですが、堤防ならその点心配無用で十分な釣果が期待できます 。初めての方は、ぜひ安全な堤防からエギングデビューしてみてください。
狙いやすい時間帯・潮・天気のポイント
堤防エギングでアオリイカを効率良く釣るには、時間帯や潮回り、天気の条件も抑えておきましょう。狙い目の時間帯はズバリ朝マズメと夕マズメです。早朝や夕方の薄明るい時間帯には小魚などエサとなる魚が活発になり、それを追ってアオリイカも活性が上がります 。日の出・日の入りの前後1時間程度は絶好のチャンスタイムで、エギへの反応も良く「入れ掛かり」状態になることもあります 。特に夕まずめは日中に比べ人も減り、これから動き出すイカを狙えるのでおすすめです。もちろん夜間にも釣れますが、初心者はまず明るい時間帯~薄暗くなる頃までに挑戦すると良いでしょう。
潮回りでは、満潮前後のタイミングが狙い目です。満ち潮で海水が岸に寄せられると小魚も接岸し、それを追ってイカも岸寄りに来やすい傾向があります。満潮の少し前から満潮直後くらいにかけてがひとつの山場です。また潮通しが良い場所(潮が適度に流れる場所)で、なおかつ潮位が高いときは絶好のポイントになります。ただし潮位が下がり始めて流れが速すぎるとエギが安定せず釣りにくいので、大潮よりも中潮・小潮くらいの緩やかな潮回りの日が初心者には扱いやすいでしょう。
天気や海の状況も大切です。風が弱く波が穏やかな日の方がライン操作がしやすく、エギの動きも安定します。強風の日はラインが風で煽られてアタリが取りづらく、糸絡みなどのトラブルも増えるため、できれば避けたいところです。また水の濁りが少ない日がベターです。アオリイカは視覚でエサを探すので、水が澄んでいる方がエギを見つけてもらいやすくなります。雨の後で濁りが入っている場合や、台風直後で海が荒れている場合は無理をせず、海況が落ち着くのを待ちましょう。
まとめると、「朝夕のマズメ時×満潮前後×風弱く穏やかな日」が初心者にとってヒット率アップの条件です。このタイミングを狙って釣行計画を立てれば、きっと秋の堤防でアオリイカを手にできるはずです。
エギングに必要な道具一式とおすすめアイテム
秋の堤防エギングを始めるにあたって、まずは道具(タックル)一式を揃えましょう。基本はロッド・リール・ライン・リーダー・エギの5点セットです 。ここでは各道具の選び方と、初心者におすすめのアイテムを紹介します(※各カテゴリごとに価格帯別などでおすすめを3つずつ挙げています)。予算やスタイルに合わせて選んでみてください。
ロッド(エギングロッド)の選び方とおすすめ
エギング用のロッドは各メーカーから専用モデルが出ていますが、初心者には長さ8フィート前後(だいたい2.5~2.6m)が扱いやすいです 。具体的には8フィート3インチ(約2.52m)~8フィート6インチ(約2.59m)くらいが標準で、遠投性能と操作性のバランスが良い長さです 。硬さ(パワー)は、秋の小型狙いなら柔らかめのL(ライト)クラスでも良いですが、汎用性を考えるとML(ミディアムライト)~M(ミディアム)クラスが一本目には無難でしょう 。MLは小型エギも扱いやすく、Mは多少重めのエギや春の大型にも対応できます。ロッドは軽いほど一日シャクリ続けても疲れにくいので、可能な範囲で軽量なものを選ぶと◎です。穂先(ティップ)が繊細でアタリを捉えやすい設計や、シャクリ続けても手首が痛くなりにくいバランス設計など、専用ロッドにはメリットが多いので可能であれば専用を手に入れましょう 。
★おすすめロッド3選
ダイワ エメラルダス X 86ML
大手DAIWAのエギング入門用定番ロッドです。全長8.6ft・MLパワーで、秋のエギングに必要十分な汎用性があります。ロッド下部にX巻き補強が施されネジレに強く、キャストのしやすさと操作性を両立。価格も1万円前後と手に入れやすく初心者に人気です 。
シマノ セフィア BB S86ML
シマノから発売されているエギングロッドのエントリーモデル。8.6ftのMLで一年中オールラウンドに使える仕様です 。シマノ独自のハイパワーX構造でブレを抑え、シャクリ時のパワーロスを減らしています 。2万円弱と性能の割に手頃で、初心者が長く使える一本です。
メジャークラフト エギゾースト 1G 862M
コスパに定評のあるメジャークラフト社の入門モデル。8.6ft・Mパワーで、やや硬めながら軽量設計のため大遠投やキビキビしたアクションが可能なのが特徴です 。上位機種のテクノロジーが取り入れられており、1.5万円前後という価格ながらしっかりエギングを楽しめる高コスパロッドです。
※他にも、もっと安価な入門ロッドを求めるならダイワ「ルアーニスト 86ML」やシマノ「ルアーマチック 86ML」など汎用ルアーロッドも選択肢です 。これらは5~6千円程度と安く、エギング以外の釣りにも転用できるので、まずはお試しで始めたい方には良いでしょう。ただし専用ロッドに比べると感度やシャクリやすさで劣る面もあるため、予算に余裕があれば最初からエギング専用モデルをおすすめします。
リール(スピニングリール)の選び方とおすすめ
リールはスピニングリールの2500~3000番台がエギングロッドにマッチします (シマノ表記ならC3000番程度、ダイワならLT2500~LT3000)。重要なのは、PEライン0.6~0.8号が150~200m程度巻けるスプール容量があること 。これくらい巻ければ遠投しても十分な糸巻き量が確保できます。秋の小型狙いではドラグ力はそれほど必要ありませんが、シャクリの負荷に耐える剛性とドラグの滑らかさは大事なポイントです。特にアオリイカは走り出すと一気にドラグが出るので、滑らかで強いドラグ性能を持つリールを選びましょう。
また、リールの自重はできるだけ軽い方がロッドとのバランスも良く、一日扱っても疲れにくいです。200~250g台くらいまでの軽量モデルがおすすめ。ギア比については、扱いやすいノーマルギア(5.x:1程度)を基準にすると良いですが、秋の手返し良い釣りにはハイギア(6.x:1以上)モデルも便利です 。ハイギアなら素早く糸フケを回収でき、手早く次のシャクリに移れるので、活性の高い秋イカをテンポ良く探るのに向いています。
★おすすめリール3選
シマノ 22 セフィアBB C3000SDH
エギング専用リールの定番エントリーモデル。手頃な価格ながら剛性・耐久性が高く、ドラグやギアの性能もエギング用として申し分ありません 。特徴は**ダブルハンドル(DH)**仕様で、シャクリ後の素早い糸フケ回収がしやすい点です。自重も軽めで、防水性能(コアプロテクト)も備え長く使えます 。PE0.6号を下糸なしで200m巻けるスプール設計で、初心者の最初の一台に最適です。
ダイワ 24 レブロス LT2500S-DH
ダイワの高コスパリール「レブロス」の最新モデルで、こちらもダブルハンドル仕様。1万円を切る価格帯ながらATDドラグで滑らかな効き、軽量ローターによる巻き心地の良さなど性能が充実しています。LT2500SサイズはPE0.8号が200m近く巻け、秋イカ狙いには十分。耐久性では上位機種に劣るものの、入門用として人気のモデルです。
アブガルシア カーディナルIII S 2500SD
予算を抑えたい方には、アブガルシアのカーディナルも選択肢になります。5000円前後という安価ながら、必要な基本性能は備えた初心者向けリールです。ギア比5.2:1で扱いやすく、ドラグも実用上問題ありません。ただし上記2機種に比べると巻き心地の滑らかさや剛性感はやや落ちるので、「とりあえず安く始めたい」という方向きです。
※エギング中はシャクリ動作でリールにも負荷がかかりますので、できれば耐久性評判の良いモデルを選びましょう。将来的に春の大型イカにも挑戦するなら、上位シリーズ(例えばシマノならヴァンフォードやツインパワー、ダイワならフリームスやカルディア以上)を検討しても良いですが、まずは上記クラスで十分楽しめます。
PEライン&リーダーの基本とおすすめ
ラインは必ずPEラインを使います。エギングではPEの細く伸びにくい特性が、シャクリの操作性とアタリ感知に絶対不可欠だからです 。太さはPE0.6~0.8号が基準となります 。秋の小型狙いであれば0.6号(強度で言うと約12lb前後)で十分ですが、初心者が扱ううちは0.8号(約16lb)でもOKです。細いほど飛距離が出てアタリも取りやすい反面、風の影響は受けやすくなるため、まずは無難に0.8号あたりから始め、慣れたら0.6号に落とすのも良いでしょう。
長さは150m以上は巻いておきます。エギングでは遠投して広範囲を探る場面も多く、根掛かりなどでラインを切る可能性もあるため、余裕を持って巻いておけば安心です 。最近は8本撚り・12本撚りなど編み数によってしなやかさや感度が異なるPEもありますが、初心者は手頃な価格帯のもので構いません。「しなやかでトラブルが少ないか」「色付きで見やすいか」などに注目すると良いでしょう。
PEラインの先端にはショックリーダー(リーダー)を結束します 。これは根ズレ対策と急な負荷からラインを守るためで必須の仕掛けです。素材は伸びが少なく摩擦に強いフロロカーボン製を使うのが一般的。太さはフロロ1.75号~2号(約7~8lb)程度が秋イカ狙いには適しています。目安として、PE号数の3倍前後の太さを取ると良いです。2号(8lb)あれば小型~中型のイカには充分で、万一障害物に擦れても耐えてくれます。長さはリールから竿先までの長さ+α、だいたい1~2ヒロ(1ヒロ=約1.5m)で、約1.5~3mほどあればOKです 。長すぎるとキャスト時にガイドに結び目が干渉するので注意しましょう。
リーダーとPEラインの結束にはFGノットがおすすめです 。FGノットは強度が高く結び目が細いのでガイド抜けもスムーズだからです。ただし慣れるまでは難しい結び方でもあるので、最初は簡易的な**電車結び(ユニノット同士の結束)**やダブルユニノットで代用しても構いません。いずれにせよ結束強度がしっかり出ないと大物ヒット時や根掛かり対処時にラインブレイクしてしまうので、練習して確実に結べるノットを身につけましょう。最近はSNSノットやSFノットなどFGノットを簡略化した方法も紹介されていますので、動画などを参考に挑戦してみてください。
★おすすめライン&リーダー
バリバス アバニ エギングPE 0.8号 150m
エギング専用設計のPEライン。コーティングにより滑りが良くキャスト飛距離が出しやすいです。8本撚りでしなやかさも十分。色分けマーキング入りで残り深度を把握しやすく、初心者にも扱いやすい定番ラインです。
よつあみ G-soul X8 0.6号 200m
高強力で評価の高いよつあみ(YGK)のPE。0.6号ながら直強力20lb近くあり、秋イカ狙いでは安心の強度。色落ちしにくく視認性も良好です。200m巻きなのでトラブルで多少カットしても当面使えます。価格も比較的リーズナブル。
シーガー フロロショックリーダー 2号 30m
信頼のKUREHA製シーガーブランドのフロロリーダー。根ズレ・摩耗に強く、適度なしなやかさで結束しやすいです。2号は汎用サイズで、イカだけでなく他のルアー釣りにも使い回せます。コスパも良いので1巻持っておくと安心です。
(リーダーは他に、ヤマトヨテグスやデュエルなど各社から専用エギングリーダーが出ています。長さ50m~100m巻きを買っておけば当分もちますので、ケチらず交換するようにしましょう。)
エギ(餌木)の選び方とおすすめ3選
最後に主役のエギ(餌木)です。エギのサイズは番号で表記され、「○号」は約○寸(3.75cm×号数)の大きさに相当します。秋の新子狙いには2.5号~3.0号程度の小さめエギが扱いやすくおすすめです 。一般的な標準サイズは3.5号(全長約105mm)ですが、秋のうちは3号(約90mm)前後にしておくと、小型イカでも抱きつきやすく釣果が伸びます 。逆に11~12月以降でサイズが上がってきたら3.5号にステップアップすると良いでしょう。カラー(色)は非常に種類が多いですが、まず定番はオレンジ系とピンク系です。晴天の日中はナチュラルなオレンジやゴールドベース、朝夕マズメの薄暗い時間帯や濁り気味のときはアピールの強いピンクやパープル系が効果的と言われます 。実績の高いオレンジとピンクのエギは視認性が良く初心者にも見やすいので、まずこの2色を揃えておくと安心でしょう 。さらに夜釣りも視野に入れるなら夜光(グロー)ボディのエギもあると便利です。エギは消耗品なので、根掛かりでロストする可能性も考えて一晩で5本以上は持参してください。
★おすすめエギ3選
ヤマシタ エギ王 LIVE 3号
エギと言えばヤマシタと称されるほど定番中の定番。エギ王シリーズは初心者から上級者まで幅広く支持されています。「エギ王 LIVE」はベーシックモデルで安定したダートとフォールが持ち味。オレンジやピンクなどカラー展開も豊富で、まず**「釣れるエギ」に迷ったらこれ!**という一本です。初心者でも扱いやすく実績抜群のため、まずはエギ王から始めてみましょう。
ダイワ エメラルダス ダートII 3号
ダイワのエギングブランド「エメラルダス」シリーズの代表的エギです。軽快なダートアクションでイカにアピールしやすく、飛距離も稼げます。カラーは夜光やケイムラ(紫外線発光)を含む多彩なパターンがあり、秋イカシーズン用に作られたカラーもラインナップ 。初心者にもダートさせやすい設計で、ヤマシタと並ぶ人気アイテムです。まずは パープル系やブルー系など他と違う色も混ぜて持っておくと、渋い状況で効く場合があります。
デュエル パタパタQ(ラトル) 3号
デュエル(DUEL)の「パタパタシリーズ」はエギに羽根状のフィンが付いており、水中でパタパタ動いてイカを誘う独自のエギです。ラトル音も内蔵しているため、濁りや夜間でもアピール力◎。一風変わったギミックですが、その分スレたイカにも効きやすく、カラーも夜光ゼブラやクリアなど攻めたラインナップ。定番エギで反応がない時の切り札として持っておくと釣果アップに繋がります。
※他にもハリミツの墨族シリーズやシマノ セフィア クリンチシリーズなど、有名ブランドのエギは性能が高く安心です。初心者はまず動かしやすい3号前後・定番カラーから揃え、徐々にシャロータイプ(沈下速度が遅いタイプ)やディープタイプ(沈下早い)など状況に合わせて使い分けを覚えていきましょう。「これ釣れそう!」と自分が直感で思えるエギを選ぶのもモチベーション維持には大切です 。実績と自信のあるエギで秋のアオリイカに挑んでみてください。
アオリイカの釣り方ステップ|堤防でのエギング入門
基本の道具が揃ったら、いよいよエギングの実釣です。ここでは堤防エギングにおける基本的な釣り方の手順を解説します。初めは難しく感じるかもしれませんが、慣れればシンプルな動作の繰り返しなので安心してください。
基本アクション「シャクリ」と「フォール」を覚えよう
エギングの基本動作は、「エギをシャクって動かす」→「フォール(沈めて抱かせる)」 の繰り返しです 。他のルアー釣りのようにただ巻くだけではイカは釣れません。まずエギをキャスト(遠投)し、狙いたいレンジまで沈めます。着底させるか中層で止めるかは状況によりますが、まずは底付近まで沈めてみましょう。そしてラインのたるみを巻き取り、ロッドを**シャープにあおってエギを跳ね上げる(=シャクる)のです 。エギはロッド操作によってダート(左右への跳ね飛び)や急浮上といったアクションをします。続けてロッドを戻しつつラインを送り、エギをフリーフォール(自然沈下)**させます。この「シャクリ→フォール」によって、エギに気づいたアオリイカがフォール中に「抱きつく(捕食動作をする)」のを狙うわけです 。イカ釣りにおける誘いの基本中の基本が、この一連の動きになります。
動かし方のコツは「動と静のメリハリ」です。シャクリで積極的にアピールし、フォールでじっくり食わせる。この緩急が重要となります。初心者がやりがちなのは、エギを動かし過ぎてしまうことです。アオリイカはエギがピュンピュン動き回ると逆に違和感を覚えて抱きづらい場合があります。特に日中は過度にシャクリ倒すのは逆効果です 。**「シャクり過ぎない、じっくり見せる」**を意識しましょう 。例えばシャクリも1回~2回に留め、その後3~5秒フォールさせてしっかり誘う、といった具合です。イカがエギに追いついて抱く間を与えるイメージですね。
最初のうちは「どれくらい沈めればいいの?」「底に着いたかわからない…」など戸惑うかもしれません。底まで沈める場合、ラインがふけたりテンションが一瞬抜けたりする感覚で着底を判断できます。底付近でシャクると根掛かりリスクがあるため、底に着いたらすぐシャクリ上げてフォールに移ると良いでしょう。底がわからなければカウントダウン(エギの沈下スピードから何秒で何m沈むか計算して数える)する方法もあります。
シャクリ方もロッドを大きく素早くあおる「大きなシャクリ」や、小刻みに震わせる「小さなシャクリ」など様々ありますが、初心者は大きめに1~2回シャクる「二段シャクリ」から始めると簡単です。これで充分イカにアピールできます。エギが跳ね上がり過ぎないよう、一定リズムで柔らかくあおる程度にしましょう。「エギを動かし過ぎない自然な誘い」が大事という点を常に念頭に置いてください 。最初の1杯が釣れればコツが掴めるはずです。落ち着いて基本アクションを繰り返してみましょう。
アタリの見極め方とアワセのタイミング
アオリイカは魚と違って明確な「ゴンッ!」というアタリが手元に伝わりにくいです。ではどうやってアタリを取るかというと、主にラインの変化と違和感で判断します。代表的なのが**「ラインの糸ふけ」です。フォール中にラインがふわっと弛んだり急に止まったりしたら、イカがエギを抱いてラインテンションが変化した証拠です。「ん?今ラインがおかしいぞ?」と感じたらアタリかもしれません 。他にも、フォール中やシャクリ後のステイ中にラインが横にスーッと走る**のも典型的なアタリです。これはイカがエギを咥えて横に泳ぎ出した状態で、早朝や夜間など視認しにくい時は指にラインを触れて感じ取ることもあります。
また、シャクリ始めに竿先に重みを感じるケースも。まるで根掛かりのようなズシッとした重さでロッドが引っ張られたら、それはイカが抱いているサインです。「もしかして今の違和感、イカかも?」と思ったら、**迷わず即アワセ(合わせ)**を入れましょう 。エギングでは違和感を感じたら積極的に空合わせ気味でもフッキングするのがコツです 。アオリイカはエギを触腕で掴んでいるだけの場合も多く、放っておくとすぐ離してしまいます。わずかな兆候も見逃さず、「ピン!」と来たらすぐにロッドをグッと煽ってフックを掛けてください。
合わせ方は、ロッドをやや上向きに鋭く煽るイメージです。上下に大きくシャクる必要はなく、竿先で聞いて「重い!」と感じた瞬間にスナップを効かせてキュッと引く程度で十分。強すぎるアワセはエギがすっぽ抜けたり、イカの腕が切れてしまうこともあるので注意です。フッキングが決まったら、絶対にテンションを緩めないようにしてください 。エギのカンナ(針)はカエシが無い構造なので、ラインを緩めるとイカが外れてしまいます 。ドラグを滑らせつつ一定のテンションを保ちながらリールを巻き取りましょう。
イカとのやり取り中、ドラグが「ジーーッ!」と鳴ってラインが引き出されることがあります。これはイカがジェット噴射で走っている証拠です。無理に止めようとせず、ドラグに任せて走らせてから、落ち着いたらゆっくり巻くを繰り返します。イカは途中で何度か墨を吐いて抵抗するかもしれませんが慌てず対応しましょう。アタリを見極め即アワセ→テンションキープでやり取り、これができればもうあなたは立派なエギンガーです。
取り込みとタモ網の使い方
いよいよイカが寄ってきたら、最後の難関が**取り込み(ランディング)です。実はアオリイカは針にしっかり掛かっているとは限らず、「抱きついているだけ」で上がってくることも多いため、足元でポロッと外れてしまうケースが少なくありません。特に堤防のように足場が高い場所で無理に抜き上げようとすると、イカが自重で落ちて海に戻ってしまうことがあります。そこで活躍するのがタモ網(ランディングネット)**です。
初心者の方はできるだけタモ網を使って取り込むようにしましょう。タモ網は長い柄の先に大きな網が付いた道具で、水面まで届かせてイカをすくい取ります。堤防エギングでは折りたたみ式や伸縮式のランディングネットが市販されていますので、一つ用意しておくと安心です。コツは、イカが水面まで浮いてきたら頭(胴体)から網に入れること。イカは後ろ向きにジェットで逃げるので、胴体を先に網に入れれば後ずさりしても網の中に入ってくれます。無理にイカを持ち上げようとせず、寄せてきたらサッと下から網を入れて掬いましょう。
一方、上級者の中にはタモではなくギャフ(カギ状の針)を使う人もいます。エギング用ギャフは先端にカンナ状のフックが付いたもので、イカの胴に引っ掛けて持ち上げる道具です。ギャフは折りたたむとコンパクトで持ち運びに便利ですが、初心者には少し難易度が高いかもしれません。というのも、ギャフ掛けに失敗するとイカを逃したり傷つけたりする恐れがあるからです。まずは確実にキャッチできるタモ網を使うのがおすすめです 。大型イカ狙いでどうしてもギャフを使いたい場合は、十分練習してから挑戦しましょう。
イカを無事ネットインしたら、あとは抜き上げるだけです。この際、自分や周囲に墨を吐きかけられないよう注意してください。アオリイカは空中に上げられると最後の抵抗で墨を吐くことが多いです。顔を近づけない、周りの人にも声をかけて注意してもらうなどして、安全に回収しましょう。イカは胴体を優しく掴めば大人しくなります。釣れたイカはクーラーボックスに入れるか、締め具(イカ締めピック等)で速やかに〆て鮮度を保つようにしましょう。
初めて自分で釣り上げたアオリイカとの対面は感動ものです。最後まで気を抜かず、確実にキャッチして美味しく持ち帰ってくださいね。
初心者がやりがちな失敗とその対策
エギングにはいくつかハマりがちな落とし穴もあります。ここでは初心者が陥りやすい失敗例と、その防止策・対処法をまとめます。同じミスを繰り返さないようチェックしてみましょう。
エギの操作が速すぎる/沈めすぎる
ありがちなミスの一つが、エギを動かすテンポが速すぎることです。早くアオリイカにアピールしようと焦るあまり、シャクリを連発したり、フォールをほとんど取らずにすぐ回収してしまったりするケースですね。これではイカがエギを追いきれず、なかなか抱いてもらえません。エギングは「待ちの釣り」でもあります。 焦らずじっくり誘うのが基本です。「シャクったら3~5秒はフォールさせる」「数回投げて反応なければカラーやサイズを変えるかポイントを少し移動する」など、一投一投丁寧に探ってみましょう。「動かし過ぎは逆効果」という言葉を思い出して、メリハリのある誘いを心がけると釣果が安定します 。
また、エギを沈めすぎて根掛かり連発という失敗もよくあります。特に底付近までフォールさせると海底の障害物にエギが引っかかるリスクが高まります。対策として、事前に水深を把握しておき、底まで完全に沈め切らないようにするのが効果的です。例えば「15秒でボトムかな?」と予測できれば、着底前にシャクって根掛かりを回避できます。また着底してしまっても慌てずラインを緩めてみると外れることもあります(※無理に煽ると余計に刺さる場合があるため)。秋の堤防は海藻やゴロタ石のポイントも多いので、**シャロータイプのエギ(ゆっくり沈むタイプ)**を使って浅く探るのも一手です。
いずれにせよ、「焦らずゆっくり」が成功の秘訣 。じっくり誘えばイカはちゃんとエギを見つけてくれます。テンポ良く探りつつも、一投ごとにしっかり「見せる時間」を作ってあげてください。
PEラインのトラブル(ライントラブル対策)
PEラインは細くてしなやかな分、扱いを誤るとライントラブルが発生しやすい素材です。エギング初心者に多い悩みが「ラインがグチャグチャに絡まった!」というもの。代表的なのは**「バックラッシュ(糸噛み)」や「風による糸絡み」**です。これらを防ぐには、いくつかコツがあります。
まずキャスト前後にはラインのたるみ(糸ふけ)をチェックしましょう。キャスト前にリールのスプールから垂らしたラインがフケていると、一気に放出された際にガイドやスプールに引っ掛かりバックラッシュの原因になります。軽く引っ張ってまっすぐな状態で投げる癖を付けてください。キャスト直後、着水してエギを沈めている間にも風でラインがフケてガイドに絡むことがあります。これを避けるため、着水したらすぐにベールを起こして糸ふけを巻き取る(テンションフォールで沈める)か、指でラインを軽く張って沈めると良いです 。
また、ベール(スプールのアーム)は手で返すのを徹底しましょう。リールのハンドルを回してベールを戻すと、その反動でスプールに緩んだラインが巻き込まれループ状の絡みを起こすことがあります。手で静かにベールを戻し、余計なたるみが出ないようにするだけでライントラブルは激減します。
風が強い日には、思い切って釣り方を変えるのも手です。追い風ならまだしも、向かい風や横風では無理に遠投せず近場を丁寧に探りましょう。それでもラインが風にあおられる場合は、沈める深度を浅めにして風の影響を受けにくくするのも有効です。
それからリーダー結束部分のチェックもお忘れなく。FGノット等で組んだリーダーが不完全だと、キャスト時の衝撃や大物ヒット時にプッツリ…なんてことも。結び目は釣行前にしっかり締め込み、余計なタグ(端糸)は切っておきましょう。夜間に結束する際は焦らず確実に。どうしても難しい場合、現場では簡易ノットで応急処置して、帰宅後に結び直すのもありです。
最後に、初心者はあまりに安価なノーブランドPEラインは避けるのもポイントです 。品質の低いPEはコシがなくトラブルが頻発しがちなので、多少お金を出しても信頼できるメーカー品を使った方が結果的にストレスなく楽しめます。
釣れない=場所の問題かも?
「道具も揃えた、釣り方もそれなりにできている…でも全然釣れない!」というとき、もしかしたら場所選びに課題があるかもしれません。アオリイカは回遊性もありますが、「ここにはイカがいない」というポイントではいくら頑張っても釣れません。そこでヒントになるのが、他の釣り人の釣果情報や現場の墨跡です。
まず、周囲を見渡してみて地面や防波堤の壁にイカ墨の跡(スミ跡)がたくさん付いている場所は、それだけそこでイカが上がっている証拠です 。反対にどこにも墨の痕跡が無い新規開拓ポイントは、残念ながら“空振り”の可能性も。最初のうちは実績のある堤防を選ぶのが近道です。「あそこの港で釣れたらしい」「この堤防は毎年秋イカが上がる」などの情報は、釣具店の店員さんやネットの釣果ブログなどから仕入れることができます。特に関西エリアはエギング人気が高く、情報も得やすいので活用しましょう。
また、一つのポイントで粘りすぎないことも大事です。30分~1時間やってみて反応がなければ、**思い切って移動(ランガン)**してみましょう。例えば同じ港内でも外向きの波止先端へ行ってみる、駐車場から離れた静かなポイントまで歩いてみるなど、イカの付き場を探す意識が必要です。「ここにはイカがいるはず!」と決めつけすぎず、柔軟にポイントを変えることで出会えるイカもいます。
秋は特にイカが広範囲に散っている季節なので、1カ所に固執せず広く探すのも釣果アップの鍵です。一方で、あまり短時間で移動を繰り返しすぎるのも逆効果。基本は**「実績場で腰を据えてやりつつ、ダメなら次」**くらいのスタンスが良いでしょう。
身近な例で言えば、堤防の中でも常夜灯がある場所や、海藻が生えている角、潮通しの良い先端付近などは狙い目です 。逆に真っ暗な場所や障害物の全くない砂地だけの場所などはイカの影が薄いことも。釣り場に着いたらまず周囲を観察し、イカが潜んでいそうな地形変化やベイト有無をチェックする習慣を付けましょう 。それでも釣れない日は…潔く「今日は場所がハズレだったかな」と割り切って、次回別のポイントで再チャレンジしてみてくださいね。
関西でアオリイカが釣れるおすすめ堤防スポット3選
最後に、関西エリアの初心者におすすめしたいアオリイカ好釣果の堤防スポットを3つ紹介します。いずれも足場が良く安全で、駐車場やトイレなどの設備も整っていたりアクセスが容易だったりする場所です。週末の釣行先選びの参考にしてみてください。
淡路島・福良港(兵庫県)
南あわじ市の福良港は、淡路島を代表するエギングスポットの一つです。雑誌やTVでもしばしば紹介される有名ポイントで、初心者向けのメバル釣り場としても登場するほど足場が良く広大な港です 。港内は湾になっていて波風が比較的穏やかで、多数の波止や護岸があり歩いて回れる釣り場がたくさんあります 。車も漁師さんの邪魔にならない場所であれば停められ(港周辺に駐車スペースあり)、すぐ近くにトイレやコンビニもある充実ぶり 。初心者が一日安心して釣りを楽しめる環境が整っています。
福良港がエギング初心者に嬉しいのは、秋に数釣りが楽しみやすい点です。淡路島各所で秋イカ好調ですが、中でも福良周辺は好ポイントが多く、毎年多くのアオリイカが上がっています 。人気エリアでは地面が墨跡で真っ黒になるほど釣果が出ており、週末ともなると大勢のエギンガーで賑わうほどです 。港内でもポイントによって釣果にムラがありますが、外海に面していて潮通しの良いエリアや、消波ブロック周りなどが狙い目とされています 。実際に筆者も秋に訪れましたが、夕まずめの16~18時半で新子を4杯ゲットできました 。イカがどんどん大きく育っていく季節なので、通えばサイズアップも期待できます 。
福良港ではエギング以外の釣りも盛んで、アジやメバルのポイントとしても有名です。そのため夜になるとエギングしながらアジングをする人もいたりします。初心者はまず明るい時間帯から始め、夕方~日暮れにかけて集中して狙うと良いでしょう。「釣れないな…」と思っても港内を移動して墨跡のある所を探すなど工夫してみてください 。淡路島南端の温泉街も近いので、釣り+観光で訪れるのも楽しいですよ。
泉南・加太漁港(和歌山県)
和歌山市加太(かだ)港は、大阪方面から電車でもアクセスできる数少ない好釣り場です。南海電鉄を利用すれば大阪難波から約1時間半、加太駅から徒歩15分ほどで港に到着します 。車が無くても行ける気軽さから、学生さんや電車釣行派にも人気のポイントです。港の沖に突き出した加太大波止(おおはと)は全長が長く、多くの釣り人が竿を出せるスペースがあります。ここは一年を通して青物や底物など様々な魚種が狙える好釣り場で、週末は釣り人で賑わうこともしばしばです 。アオリイカも例年秋に良型が上がっており、秋イカの数釣りポイントとして知られています。
加太の良いところは環境の良さです。周辺はリゾート地の雰囲気があり、釣り場から眺める景色も綺麗でのんびりした空気があります 。釣り場近くには旅館の温泉(日帰り入浴可「ひいなの湯」)や海鮮料理店もあり、釣り+観光のプランも楽しめます 。また和歌山市観光協会が釣竿レンタル付きの海釣り体験プランを提供していたりと、初心者ウェルカムな土地柄です 。家族連れで訪れても、奥様やお子さんが釣りに飽きたら近くの淡嶋神社や友ヶ島観光なんて選択肢も。
エギングポイントとしては、加太大波止の先端外向きが人気です。先端付近には常夜灯もあり、夜間のエギングもしやすいです。昼間狙うなら潮通しの良い外向きがベターですが、風が強い時は内向きで風裏を探すなどしましょう。実績カラーはオレンジやエビ柄などと言われますが、日によって変わるのでローテーションして探ってください。なお加太では他にもアジや根魚もよく釣れるため、予備竿でサビキをして小アジを釣り、それを泳がせてアオリイカを狙う(ヤエン釣り)スタイルの方もいます。エギングで反応が無いときは試してみても面白いかもしれません。
アクセス抜群で施設も整った加太港は、電車派の方や初心者にとって心強い釣り場でしょう。釣り人が多いのでマナーは守り、譲り合って楽しんでください。朝夕のマズメ時、目の前の海でアオリイカがヒットする瞬間は格別ですよ。
和歌山・雑賀崎漁港(さいかざき)
**雑賀崎漁港(和歌山市)**は、“日本のアマルフィ”とも呼ばれる景勝地・雑賀崎の一角にある有料釣り場です。駐車料金として車1台500円(2021年時点)かかりますが、その分設備が整っており、大規模な駐車場(100台以上)と水洗トイレが完備されています 。大阪方面からも釣り客が訪れる超人気ポイントで、冬でも釣り人が絶えないほどです 。
釣り場は大きく外側の堤防(外向き防波堤)と内側の堤防に分かれます 。外側の堤防は高さがあり、先端部へはハシゴを上って上がります 。先端は足元に消波ブロックが入っておらず足場が平らで、アオリイカの墨跡も多数見られる一級ポイントです 。水深もあり潮通しも抜群で、エギングで大型が狙えることで有名です。人も多い場所なのでエギングの方が手返しよく釣りやすいとの声もあります 。実際、毎年秋になるとキロアップ(1kg超え)のアオリイカが報告されており、腕に自信がついた中級者以上にはたまらないスポットです。
一方、内側の堤防は海面からの高さが低く、車を横付けできるためファミリー向けの穏やかな釣り場になっています 。足元はフラットで消波ブロックもなく、お子さん連れでも安心です 。内側ではサビキ釣りでアジやイワシを狙う人が多く、その小魚を求めて小型のアオリイカ(新子)が寄ってくることもあります。初心者はまずこの内向きでエントリーし、慣れてきたら外向きの大物狙いにチャレンジ…というステップも良いでしょう。
雑賀崎は景色が素晴らしく、釣りをしながら綺麗な海岸線を眺められるのも魅力です。夕暮れ時には絶景が広がり、釣れても釣れなくても訪れる価値を感じるはず。もちろんアオリイカの魚影も濃く、墨跡が各所にベッタリ付いているので実績は折り紙付きです 。駐車料金はかかりますが、その分マナーや管理もしっかりしていて快適に釣りができます。ぜひ一度足を運んで、和歌山屈指のエギングスポットで秋イカをゲットしてください。
まとめ
秋はアオリイカエギング初心者にとって最高のシーズンです!エギングに必要な道具は意外とシンプルで、ロッド・リール・ライン・リーダー・エギさえ揃えればすぐに始められます。この記事で紹介した道具選びのポイントや釣り方の基本、そして実績豊富な堤防スポットの情報を押さえておけば、あなたもきっと秋の堤防でアオリイカを手にすることができるでしょう。
まずは安全第一で足場の良い堤防からスタートし、焦らずゆっくり誘ってみてください。アオリイカのグィーン!という強烈な引きを味わえば、その楽しさに病みつきになること間違いなしです。釣り上げたイカはぜひ新鮮な状態で持ち帰り、自宅でお刺身やバター焼きなどに調理してみましょう。自分で釣ったイカの美味しさは別格で、釣りの喜びが一層深まります 。
この秋、エギングタックルを片手に堤防へ出かけ、エメラルドグリーンに輝くアオリイカとの出会いをぜひ楽しんでください。あなたのエギングデビューを応援しています。さあ、週末は堤防でアオリイカにチャレンジしてみましょう!健闘を祈ります。釣れたイカで秋の味覚を満喫してくださいね。🎣🦑


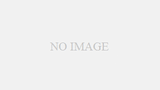
コメント