「秋に青物を釣ってみたい!でも初心者でも釣れるの?」――そんな疑問をお持ちではないでしょうか。実は秋は青物釣りのハイシーズンです。堤防からのショアジギングなら、初心者でも十分チャンスがあります。本記事では、秋に堤防から狙える青物(ハマチ・サゴシなど)の特徴や釣れる時間帯、効果的なアクション、さらに関西でおすすめの堤防スポットまで徹底解説します。釣果アップのコツを押さえて、秋の海で念願の青物を釣り上げましょう!
なぜ秋は青物ショアジギングのベストシーズンなのか
秋は青物釣りが一年で最も盛り上がる季節です。その理由にはベイトフィッシュ(小魚)の接岸や水温の安定など様々な要因があります。なぜ秋がショアジギングのベストシーズンと言われるのか、そのポイントを見ていきましょう。
ベイトの接岸で青物が岸近くまで回遊する
秋になるとイワシやアジなど小魚の群れが岸沿いに寄ってきます。それを追ってブリやカンパチなど青物の群れも沖から堤防付近まで接岸するため、岸からでも大型魚が狙える絶好のタイミングとなるのです 。実際、秋はナブラ(ベイトを捕食して海面が騒ぐ現象)が発生することも多く、そんな場面に遭遇すれば堤防からでも大物ヒットが期待できます。
水温・気温が安定し魚の活性が高い
夏の盛りを過ぎた初秋以降、水温はゆっくり低下しますが適度に安定して魚にとって快適な範囲が続きます 。気温も穏やかで朝夕は涼しくなるため魚の活性が一段と高くなり、冬に備えてエサを激しく追い回す「荒食いモード」に入る個体も多くなります 。このように食欲旺盛な時期なので、初心者でも青物を釣りやすい季節と言えるでしょう。
堤防から狙いやすく初心者向きのシーズン
ベイトが岸近くまで来る秋は、遠投しなくても足元や浅場でヒットする場合もあります 。そのためキャスティング距離や高度なテクニックに自信がない初心者でも魚を掛けるチャンスが増えます。天候も安定して釣り日和の日が多いので、堤防でじっくりと青物を狙うには秋はまさに絶好のシーズンです 。
秋に堤防から狙える青物の種類と特徴
秋の堤防ではどんな青物(回遊魚)が釣れるのでしょうか。ここでは代表的なターゲットとなる魚の種類と、それぞれの特徴や攻略ポイントを解説します。ハマチやサゴシといった定番から、思わぬ大物まで秋ならではの魅力があります。
ハマチ・ツバス
ハマチやツバスと呼ばれるブリ(ブリ族)の若魚は、秋の堤防青物釣りで最も定番のターゲットです。30~60cm程度のサイズが群れで回遊し、小型でも引きが強いため初心者でもスリリングなファイトが楽しめます。関西では9月頃からツバスサイズ(30cm前後)の群れが接岸し始め、10~11月にかけて群れの数も魚のサイズも増していきます 。シーズン後半には50~60cm級のハマチクラスが混じることもあり、一日に複数本釣れる日も珍しくありません 。彼らはイワシなどベイトボールを追って表層近くでボイル(激しい捕食)を起こすこともあります 。ナブラが立ったら絶好のチャンスなので、素早くメタルジグを投げ込んで狙いましょう。基本的にはベイトがいる層(表層〜中層)を意識し、広範囲に探るとヒット率が上がります。
サゴシ(サワラの若魚)
サゴシはサワラ(サゴシより大型の成魚)の若魚で、体長50~60cmほどの細長い青物です。銀色のスマートなボディに鋭い歯を持ち、秋の堤防で人気のターゲットとなります 。引きも強く食味も良いため、タチウオと並んで初心者におすすめされる青物です 。サゴシを狙う際には、その鋭い歯に注意が必要です。ワイヤーリーダーを使用するなどして、ラインを噛み切られないよう対策しておきましょう 。
サゴシは活性が高い時にはメタルジグのただ巻き(一定速度で巻くだけ)でも積極的に追尾してきます。高速リトリーブで引くと細かな振動を伴ってジグが泳ぎ、小魚の群れが逃げる様子に近いため、サゴシやサバなどが違和感なく食いつきやすい動きになります 。専門的なテクニックを使わなくてもヒットさせられる点は初心者には嬉しいところです。また、ワインド釣法(専用のジグヘッド+ワームを使いロッドを小刻みにシャクるダートアクション)でもサゴシは狙えます。夜明けや夕暮れには表層近くまで接岸しやすい魚なので、朝夕マズメにただ巻きやワインドで広範囲を探れば高確率でヒットが期待できるでしょう。なお、シーズンは9月~11月頃までが目安で、水温が下がる12月以降は浅場に寄りにくくなります 。秋のハイシーズンを逃さず狙ってみてください。
その他のターゲット
ハマチ・サゴシ以外にも、秋の堤防では様々な魚との出会いがあります。アジやサバなど小型回遊魚の群れに付く青物もその一つです。堤防周りにマアジや小サバが大発生しているときは、それらを捕食するフィッシュイーター(肉食魚)が潜んでいることがあります。実際、秋(9〜11月)は岸寄りするベイトに伴ってイナダ~メジロクラス(ブリの若魚)が数釣りできるシーズンで、初心者でもチャンスが多い時期です 。小魚の群れめがけて青物が突然ボイルを始めることもありますので、ベイト反応があるエリアでは常に大物の気配を意識しましょう。「青物の気配はないな…」と油断していると、不意に強烈なアタリが出ることも珍しくありません。
こうしたサプライズに備えて、ラインセッティングはやや強めにしておくのがおすすめです。たとえばメインラインPE1.5号+リーダー25lb程度を使っていれば、不意の大物にも比較的対応しやすく安心です。実際、秋も深まる頃には堤防からでも50〜60cm級の青物がヒットする可能性があり 、細すぎるラインだと切られてしまう恐れがあります。せっかく掛けた念願の一尾を逃さないためにも、タックルバランスは余裕を持った強度にしておきましょう。
初心者でも扱いやすいタックルとジグ
青物ショアジギングで成果を出すには、初心者にとって扱いやすいタックル(道具)選びが大切です。適切なロッドやリールを使えばキャストやファイトが安定し、結果的に釣果アップにつながります。ここでは入門者向けに最適な基本タックルのスペックと、おすすめのジグ・ルアー、さらに揃えておきたい小物類について紹介します。
基本タックル
初心者がまず揃えるべき基本的なショアジギングタックルは次のとおりです。
- ロッド: 9フィート前後のM〜MHクラスのショアジギングロッド
遠投性能と魚とのやり取りのバランスに優れ、初心者にも扱いやすい長さ・硬さ 。 - リール: 4000〜5000番台の中型スピニングリール
ドラグ力が5kg以上あるモデルが望ましい。ハイギアタイプなら手早く巻けて便利 。 - ライン: PEライン 1.0〜1.5号(約20〜30lb相当)
細すぎず太すぎない号数で飛距離と強度のバランスが良い。200m前後巻いておく。 - リーダー: フロロカーボン 20〜25lb(5〜6号程度)
青物の歯擦れ対策に必須。約1ヒロ(1.5m前後)をPEライン先端に直結する。
この組み合わせであれば、遠投が必要な場面にも対応でき、40〜50cm級の青物にも十分太刀打ちできます 。初めての一本を選ぶ際は、各メーカーから発売されている入門向けモデル(例:ダイワ「ジグキャスター」、シマノ「コルトスナイパーBB」など)もコストパフォーマンスが高くおすすめです。
おすすめジグ&ルアー
ショアジギングの主役となるルアーはメタルジグです。初心者のうちは信頼できる定番ジグを数種類用意すると良いでしょう。以下は実績豊富で扱いやすいおすすめメタルジグです。
- メジャークラフト「ジグパラ」 – 初心者定番のメタルジグ。価格が手頃でカラーやサイズ展開も豊富です。ショートからロングまでバリエーションがあり、その時のベイトサイズに合わせて選べます。
- ジャッカル「ビッグバッカー」 – 飛距離重視のロングジグで、青物実績が非常に高いルアーです。空気抵抗の少ない細身形状により遠投性能が抜群で、沖のナブラ撃ちにも最適。高速リトリーブでも安定して泳ぐためサゴシ狙いにも向いています。
- ダイワ「サムライジグ」 – 長年愛される定番ジグ。クセのない動きで扱いやすく、ただ巻きでもしっかりアピールしてくれます。比較的コンパクトなシルエットなので小型青物からタチウオまで幅広く対応でき、タックルボックスに一本入れておくと安心です。
メタルジグの重さは、まず30~40g前後を基準に考えましょう。堤防から狙う青物ならこのレンジが投げやすく操作もしやすいためです。状況に応じて遠投が必要な場合は50~60gの重めも用意し、逆に足元の小型回遊魚狙いには20g程度の軽めもあると安心です 。またカラー選びも重要ポイントです。一般的にベイトに合わせたブルー系やシルバー系が定番ですが、朝夕マズメの薄明かりの時間帯にはグロー(夜光)や赤金といった視認性の高いカラーが効果的です 。日中の晴天時で水が澄んでいる場合はナチュラル系、曇天や濁りがある場合はチャート(黄緑)など派手色など、数種類のカラーを持って状況に合わせて使い分けると良いでしょう 。
初心者が揃えるべき小物
タックルとルアーが準備できたら、次は安全かつ快適に釣りをするための小物類も揃えておきましょう。初心者が特に用意しておきたいアイテムは以下のとおりです。
- フィッシュグリップ – 掴みづらい青物を安全につかむための道具。歯のあるサゴシや暴れる青物を素手で触ると怪我の恐れがあるため、しっかりホールドできるグリップがあると安心です。陸に上げた後の暴れによる針外れ防止にも役立ちます。
- プライヤー(ペンチ) – 釣れた魚に掛かったフック(針)を外す必須アイテム。特に青物は暴れやすいので、手でフックを外そうとすると危険です。先が細く錆びにくい釣り用プライヤーを用意しましょう。ラインカッター機能付きならライン切断にも使えて便利です。
- タモ網(ランディングネット) – 足場の高い堤防で青物を取り込むにはタモ網が欠かせません。大物ほど抜き上げ時にラインブレイクのリスクがあるため、サイズ60cm以上の枠を持つランディングネットを用意しましょう。伸縮式や振り出し式の柄(ポール)ならコンパクトに持ち運べます。
- ワイヤーリーダー – サゴシやタチウオなど、歯の鋭い魚を狙う可能性がある場合はワイヤーリーダーも準備します。フロロカーボンリーダーの先端に約10cm程度の細めのワイヤーを結束しておくことで、鋭い歯による瞬時の噛み切りを防げます。特にサゴシ狙いではワイヤー使用で貴重なジグのロストを減らせるでしょう。
これらの小物を揃えておけば、釣り上げた魚の安全な取り扱いやトラブル防止に役立ちます。せっかくの釣果を無駄にしないためにも、道具の準備は入念にしておきましょう。
釣果を伸ばす時間帯とアクション
青物釣りで「いつ・どんな風に釣るか」は、釣果を大きく左右する重要ポイントです。秋のショアジギングで効率良く釣果を伸ばすために、初心者が押さえておきたい時間帯の狙い目と基本アクションのコツを解説します。朝夕のマズメ時はもちろん、日中でも条件次第でヒットを狙えますので、ぜひ参考にしてください。
時間帯
朝マズメ・夕マズメは鉄板 – 青物狙いで最も実績が高い時間帯は、やはり朝マズメ(夜明け前後)と夕マズメ(夕暮れ時)です。特に夜明け頃は、夜の間おとなしかった小魚が動き出し、それを追って青物も浅場の表層近くまでやって来ます 。日の出前後の約1時間は、海中で一気に捕食活動が活発化するゴールデンタイムです。実際、朝まずめには堤防近くまでツバスやサゴシの群れが寄りやすく、短時間で連続ヒットすることも珍しくありません。薄暗い時間帯にはグロー系や赤金系のジグが目立ちやすく効果的なので、暗いうちから準備しておきましょう 。また夕マズメも狙い目です。日没前後の薄暗い時間帯は魚の活性が再び上がり、朝ほどではないにせよ青物が岸寄りでエサを追うチャンスがあります 。日中より人のプレッシャーも下がるため、夕方に思わぬ大物がヒットすることもあります。
潮のタイミングを狙う – 時合いをさらに細かく見るなら潮汐(潮の満ち引き)にも注目しましょう。一般的に潮が動き始めるタイミングは魚の活性が上がりやすくなります。満潮・干潮前後のいわゆる潮止まり前後は、回遊魚が一気に回ってくる好機となる場合があります。特に潮位変化が大きい大潮・中潮の日は水中の流れがしっかり効くため、昼間でも青物が口を使いやすく釣果が出やすい傾向があります 。逆に小潮・長潮のようにあまり潮が動かない日はやや不利ですが、その場合でも潮通しの良い岬状の地形や水道筋(海峡部)を狙えばチャンスはあります。実際、和歌山の地磯や明石海峡周辺など潮流が早いポイントでは、真昼でも青物がヒットする例が報告されています。要は**「潮が動くタイミング」に「潮通しの良い場所」**を攻めることが重要ということです。釣行前には潮見表を確認し、「○時頃に満潮だからその前後を狙おう」といった計画を立てると良いでしょう。
基本アクション
ショアジギングではルアー(メタルジグ)の動かし方ひとつで釣果が大きく変わります。難しそうに聞こえるテクニックも、基本を押さえれば初心者でも十分実践可能です。ここでは代表的な3種類のアクションとそのコツを紹介します。
ワンピッチジャーク
最も基本となるアクションがワンピッチジャークです。ロッドを1回シャクる毎にリールハンドルを1回転させるリズミカルな動作で、ジグをキビキビと泳がせます。ジグが左右にヒラヒラとスライドしながら上下に泳ぐため、小魚が逃げ惑う様子を演出でき、ハマチやサゴシなど青物のリアクションバイト(反射的な捕食)を誘発する定番の動きです 。コツは「ロッドのシャクリとリール巻きを同期させる」こと。最初は「シャクって巻いて、シャクって巻いて…」と声に出しながら一定のリズムを刻むと良いでしょう。ワンピッチジャークは疲れにくく長時間続けやすいメリットもあるので、まずはこの動きをマスターして青物にアピールしてください。
リフト&フォール
ジグを一旦沈めて持ち上げ(リフト)ては落とす(フォール)動作を繰り返すアクションです。文字通り**「持ち上げて落とす」シンプルな動きですが、ヒラメ・マゴチなどの底物からサゴシまで幅広く有効なテクニックです。ボトムまでジグを沈め、ロッドを煽ってジグを跳ね上げたら、次の瞬間ロッドを下げてジグをフリーで落とします。このフォール中にアタリが出やすい**のが特徴で、砂地に潜むヒラメやマゴチは弱った小魚が沈むようなこの動きに敏感に反応し、フォール中に食いつくことが多いです 。サゴシもリフトでジグを追わせてフォールで食わせるパターンがハマりやすく、いったんジグを見切った魚も落ちてくる瞬間にスイッチが入るケースがよくあります 。フォールで食わせるコツは、ラインテンションを張りすぎず緩めすぎず適度に保つこと。違和感があれば即アワセを入れる準備をしておきましょう。なお、夕マズメ以降に狙うタチウオもリフト&フォールに好反応を示すことで知られます。暗くなってからはボトム付近より中層~表層でフォールを織り交ぜるとタチウオにアピールできます。
ただ巻き
文字通りルアーを一定速度で巻いてくるだけのシンプルな方法です。アクションを加えないことでジグが安定した泳ぎを見せ、これはまるでイワシなどの小魚が群れで游いでいるかのような状態になります。小型回遊魚や活性の低い青物に特に有効で、ハイアピールなジャークに反応しない時でも、一定のスピードで巻くだけなら魚が違和感なく追尾しやすい利点があります 。実際、アジ・サバ・小型青物などはただ巻きで安定して泳ぐジグにスッと寄ってきてそのまま食ってしまうことがよくあります 。メタルバイブレーション系のルアーやジグパラマイクロなど軽量ジグはただ巻きでしっかり泳ぐ設計なので、初心者にも扱いやすいでしょう 。テクニックいらずで攻められるため、ナブラが出た時の手返し勝負や、逆に足元で食ってくる魚を拾う際にも試してみたい基本動作です。
関西でおすすめの堤防ポイント
最後に、秋の関西エリアで初心者に特におすすめしたい堤防のショアジギング人気スポットをエリア別に紹介します。足場の良さや青物実績の高さで選んだスポットばかりなので、まずはお近くの釣り場に足を運んでみましょう。
大阪湾エリア(泉大津フェニックス・貝塚人工島)
大阪湾岸は関西ショアジギングのメッカとも言える地域で、多くの釣り人が秋の青物を狙って集まります。泉大津フェニックスや貝塚人工島といった釣り場は、いずれも埋立地や人工島に整備された堤防で、駐車場や足場の平坦なエリアがあり初心者に優しいポイントです。護岸に手すりが設置されている箇所もあるなど安全面でも安心でき、電車・車ともアクセス良好なので思い立ったらすぐ出かけられる手軽さも魅力です 。
肝心の青物実績も申し分ありません。これら大阪南部のポイントでは毎年秋になるとツバス~ハマチクラスの青物が多数釣果報告されています。特に朝マズメに強く、沖向きの消波ブロック帯ではナブラが発生することもあります 。シーズン序盤は小型(ツバス中心)ですが、シーズン後半になると50~60cm級が混じり始め、好調な日には数本のハマチを手にする人もいます 。実績が高い反面超人気スポットでもあるため、条件の良い日には夜明け前から釣り座が埋まってしまうことも珍しくありません。周囲と譲り合いマナーを守って、気持ち良く釣りを楽しびましょう。
兵庫エリア(南芦屋浜・神戸港・明石港)
兵庫県内にも初心者向きの堤防ポイントが多く存在します。阪神間で代表的なのは南芦屋浜(通称:芦屋ベランダ)、播磨方面では明石港周辺(大蔵海岸など含む)や神戸港エリアが有名です。南芦屋浜ベランダは一帯が綺麗に整備された公園的釣り場で、足場が良くフェンスも設置されておりファミリー層にも人気です。ここではツバス・サゴシといった回遊青物から、グレ(メジナ)・チヌ(黒鯛)、メバル・ガシラ(カサゴ)などの根魚まで多彩な魚種が狙えることで知られています 。秋の朝夕には青物狙いのルアーマンで賑わい、夜には電気ウキ釣りでタチウオを狙う光景も見られます 。
一方の明石港周辺(大蔵海岸など)は、明石海峡の激しい潮流がすぐ近くを流れるため青物はもちろんヒラメなど底物やシーバスの実績も高く、ルアーフィッシング全般で人気のエリアです 。いずれの釣り場もアクセスが良く駐車場やトイレが整備されているため、ショアジギング入門の場所として最適です 。週末ともなると多くのアングラーで混雑しますが、地元釣具店主催のイベントや清掃活動なども行われており、初心者が情報を得たりマナーを学んだりしやすい環境が整っています 。周囲のベテランにわからないことを聞いてみるのも上達への近道です。コミュニケーションを取りながら、安全に楽しく釣りを始めましょう。
和歌山エリア(加太周辺・水軒鉄鋼団地)
紀伊半島の付け根に位置する和歌山エリアも、秋は青物シーズン真っ盛りです。和歌山市近郊では田ノ浦漁港や水軒鉄鋼団地の岸壁が特に有名なポイントです。田ノ浦漁港の沖向き防波堤は夏~秋にショアジギングでハマチなど青物が狙える人気釣り座で、シーズン中は大変賑わいます 。また水軒鉄鋼団地の一直線に伸びた岸壁周辺も、秋にはサゴシやハマチが接岸しやすいスポットとして知られています 。夕方から夜にかけては太刀魚狙いの釣り人も多く、和歌山沿岸はタチウオの聖地とも呼ばれるほど秋の夜釣りが盛り上がるエリアです 。
さらに和歌山県西部の加太(かだ)周辺も屈指の青物ポイントとして名高いエリアです。紀淡海峡(和歌山と淡路島の間の海峡)に面しており、潮通しが抜群に良いため回遊魚の通り道になっています 。特に加太大波止(赤灯台の波止)は一級ポイントとして知られ、ハイシーズンにはブリやサワラなど大型魚の回遊もあります 。人気が高いが故に、青物の釣果情報が流れるとシーズン中の週末はおろか冬場の平日でも満員御礼になることもあります 。先端付近は絶好の釣り座として知られ、前夜から泊まり込みで場所取りをする猛者がいるほどです 。加太へ釣行の際は余裕をもって早めに現地入りし、安全第一で挑みましょう。
淡路島エリア(福良港・洲本港)
青物天国とも呼ばれる淡路島も、秋のショアジギングでは外せないエリアです。島全体が海に囲まれている立地上、四方に好ポイントが点在していますが、初心者にも行きやすい主要港としては南あわじ市の福良港や洲本市の洲本港が挙げられます。秋の淡路島はブリ系青物はもちろん、夜釣りではタチウオも狙え、さらにエギング(ルアー釣り)でアオリイカも釣れるなどターゲットが非常に豊富です 。例えば夕まずめに青物を狙い、暗くなったらワインド釣法でタチウオを狙う…といった風に、一度の釣行で二度美味しい釣りが楽しめます 。港湾部の常夜灯周りには新子(その年に生まれた小型のアオリイカ)も集まるので、青物の合間にエギを投げてみるのも一興でしょう。
福良港は深い入り江(福良湾)の入口に位置し、洲本港も大阪湾と紀淡海峡の境目付近にあります。そのため両港とも回遊魚が回ってくるルート上に当たっており実績が高いのが特徴です 。港の外向きは急深で足元から水深があるため、メタルジグを遠投せずとも十分深場を探れます 。初心者でも着底の感覚がつかみやすく、底近くを狙っていたら不意に大物青物がヒットした…ということも起こり得るでしょう 。洲本港や福良港は駐車場・トイレも整備されアクセスも良好なので、釣行プランに組み込みやすいのも利点です。南岸は比較的穏やかな海況の日が多いので、秋の行楽がてら淡路島の堤防でショアジギングを楽しんでみてはいかがでしょうか。
初心者が気をつけたい注意点と安全対策
秋の堤防ショアジギングは初心者にもチャンスが大きい釣りですが、安全対策とマナーの徹底も忘れてはいけません。最後に、これから青物釣りを始める方に向けて注意すべきポイントをまとめます。
ライト(照明)の携行: 秋は朝夕マズメや夜間に釣りをする機会が多いため、足元を照らすライトは必須です。堤防には街灯がない場所も多いので、ヘッドライトや強力な懐中電灯を用意しましょう。暗い中での移動やキャスト時の安全確保はもちろん、夜釣りでヒットした魚の取り込み時にもライトがないと大変危険です。予備の電池やバッテリーもお忘れなく。
ライフジャケットの着用: ライフジャケット(救命胴衣)は大人・子供問わず必ず着用してください。堤防だからと油断は禁物で、足を滑らせて海に落水する事故は毎年発生しています。実際、小型船舶では乗船者にライフジャケット着用が法律で義務化されていますし、堤防釣りでも落水のリスクがある以上、着用しないのは非常に危険です 。万一海に転落してもライフジャケットを着けていれば浮力で命が助かる可能性が飛躍的に高まります。釣りに行く際は恥ずかしがらず、面倒がらず、全員がライフジャケットを身につけましょう。
釣り場のマナーと環境配慮: 釣り人として守るべきマナーも心掛けてください。ゴミは必ず持ち帰るのが大原則です。使用済みのラインや仕掛け、ルアーパッケージやエサの容器など、そのまま放置すれば環境汚染や生物への被害につながります。実績ある人気釣り場ほど多くの人が訪れるため、一人ひとりの心掛けが重要です。釣り場によっては地元有志や釣具店による定期的な清掃活動が行われている所もありますが、利用する私たち自身が汚さないことが何より大切です。また場所取りやキャスティングの際の配慮も忘れずに。他の人を押しのけて割り込んだり、至近距離にルアーを投げ込むような行為はトラブルの元です。混雑時こそ周囲と譲り合い、声を掛け合って、お互い気持ちよく釣りができるよう心掛けましょう。人気スポットが今後も開放され楽しく釣り続けられるよう、マナー遵守と安全対策は万全にお願いします。
まとめ
秋は関西の堤防から青物を狙うのに最高のシーズンと言えます。豊富なベイトと安定した水温のおかげで魚影も濃く、タイミングさえ合えば初心者でも大物を仕留めるチャンスが十分にあります。タックル選びやジグの使い方、そして釣れる時間帯の攻略法を意識すれば、経験の浅い方でも釣果を大きく伸ばせるでしょう。本記事で紹介したコツやポイント情報を参考に、ぜひこの秋は堤防ショアジギングデビューを成功させてください。きっと浅瀬に疾走する青物の強烈な引きを味わい、大興奮間違いなしです!安全対策とマナーを守りつつ、秋の青物ゲームを存分に楽しみましょう。


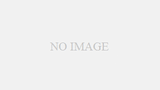
コメント