「砂浜でのんびり釣りを楽しみたい」「竿を振って遠くへ投げる爽快感を味わってみたい」――そんな釣り初心者におすすめなのが**「ちょい投げ釣り」**です。仕掛けもシンプルで堤防や砂浜から気軽に始められ、しかも釣れる魚は天ぷらにして美味しいシロギス(キス)やハゼが中心。 筆者も釣りデビュー後まもなくこのちょい投げ釣りにハマりました。キャスト(投げる動作)の爽快感と、思わぬ大物が掛かったときのワクワク感にすっかり魅了されたからです。
本記事では、初心者がゼロから始められる道具選び・仕掛けの作り方・エサの付け方・釣果を伸ばすコツなどを徹底解説します。さらに、初心者に優しい釣り場(関西エリア)や注意点も紹介。この記事を読めば最低限のタックルで安全に釣りを楽しみ、キスやハゼをしっかり釣るコツが分かります。
結論:まずはちょい投げ釣りでキャストの楽しさを覚えましょう。道具立ても簡単で初心者でも自然の中でのんびり釣果を味わうことができます!
ちょい投げ釣りとは?初心者におすすめの理由
ちょい投げ釣りは、その名の通り「ちょっと投げて釣る」手軽な釣法です。サビキ釣りなどの足元の釣りから一歩進み、自分で竿を振って仕掛けを遠くへ投げる体験ができるため、初心者にとって絶好のステップアップとなります。 キャストする動作自体がゲーム性を高めてくれ、美味しい魚も狙えるのが魅力です。
ちょい投げ釣りの基本スタイル
ちょい投げ釣りは堤防や砂浜、河口など様々な場所で楽しめます。波止(堤防)からであれば足場が安定していて初心者も安心。砂浜(サーフ)からなら遠浅の地形で根掛かり(海底の障害物への引っかかり)が少なく、思い切り投げても仕掛けを失うリスクが低いです。河口付近では海と川が交じる汽水域となり、小魚や甲殻類を求めてハゼなどが集まります。つまりどのポイントでも軽いオモリを投げ込むだけで魚が狙えるのがちょい投げ釣りの基本スタイルです。
また、狙う場所は海底が砂地であることがポイント。キスを中心に狙う場合は海底がきれいな砂地の場所を選びましょう 。底が砂地ならば砂浜はもちろん、堤防や河口近くの護岸でも釣果が期待できます。どこで釣るにしても、周囲に人がいないことを確認し、安全に注意してキャストすることが大前提です。
初心者が楽しみやすい理由
ちょい投げ釣りが初心者に向いている最大の理由は、そのシンプルな仕掛けと釣れる対象魚の手軽さにあります。仕掛けは後述するようにオモリと針のついたごく基本的なもので、専門的なテクニックや高価な道具がなくても始められます 。また、キスやハゼといったターゲットは沿岸の浅場に多く、生息数も多いため初心者でも比較的簡単に釣果が得られるのです 。
さらに、ちょい投げ釣りは費用面でも始めやすいのが魅力です。釣具店にはロッド・リールから仕掛けまで一式入った「ちょい投げセット」が安価(3,000〜5,000円程度)で販売されています 。これを購入すれば迷うことなく道具が揃い、思い立ったその日に釣り場へ行くことも可能でしょう。コストも抑えられているので「まず試してみたい」というライトな気持ちで始めやすい釣り方と言えます。
キャストする魅力と達成感
サビキ釣りでは味わえない**「自分で投げる」爽快感こそ、ちょい投げ釣り最大の醍醐味です。最初は10mも飛ばせなかった仕掛けが、練習するうちにスルスルと遠くまで飛ぶようになる——その上達が実感できる達成感は格別です。狙ったポイントに仕掛けを着水させられたときは、ゲームのようなコントロールの喜び**を味わえるでしょう。
そして、キャスト後に穂先に「コツコツ」と小気味良いアタリが出た瞬間は思わず笑みがこぼれます。自分の投げた先に魚がかかったという事実に、釣り人としての自信と喜びを感じられるはずです。時には本命以外の魚や思わぬ大物がヒットすることもあり、「何が釣れるかわからないワクワク感」もキャスト釣りならではの魅力です。
ちょい投げ釣りで必要な道具と仕掛け
ちょい投げ釣りに必要な道具は意外と少なく、最低限のタックルで十分に楽しめます。ここでは初心者に適したロッド(竿)とリール、基本的な仕掛け構成、そしてあれば便利なアイテムを紹介します。必要なものを揃えてしまえば、あとはフィールドで実践あるのみです。
竿とリールの選び方
ロッドは2メートル前後から3メートル未満程度の長さで、軽量かつ適度な柔軟性があるものが扱いやすいです。具体的には8〜9フィート(約2.4〜2.7m)のルアーロッドやエギングロッドなどが流用できます 。硬すぎる竿よりも、しなやかで竿先が敏感にアタリを伝えるライトな竿がキスやハゼの小さなアタリを感じ取りやすく初心者向きです。
リールは**小型スピニングリール(サイズ目安:1000〜2500番台)**を用意しましょう。小型で軽いリールの方が竿とのバランスが良く、長時間の釣りでも疲れにくいです。道糸(ライン)は最初からナイロン製の3号前後(約10lb程度)が巻かれているセットも多く、それで問題ありません。もし自分で糸を巻くなら、ナイロンライン2〜3号を50〜100m程度巻いておけば十分です。細い糸ほど遠くに飛びますが、2号(約8lb)以下だと根ズレで切れやすくなるので初心者は避けた方が無難でしょう。
基本仕掛け
ちょい投げ釣りの仕掛けはとてもシンプルですが、専用のものを使うとトラブルが減ります。一般的にはキス釣り用の市販仕掛けを購入するのがおすすめです 。市販仕掛けには絡みを防止するための**「テンビン(天秤)」**というオモリ付きパーツと、2〜3本の針がセットになっています 。初心者の場合、全長が短め(仕掛け全長80cm前後)のものを選ぶと扱いやすいです。
市販のキス・ハゼ用ちょい投げ仕掛けの一例。天秤オモリ(赤い部分)にハリス付きの針が連結されたシンプルな構造です。初心者は2本針程度の仕掛けから始めると扱いやすいでしょう。
テンビンオモリの重さは**5号前後(約15〜20g)**が一般的で、使用するロッドの適合オモリ負荷に合わせて選びます 。オモリが軽すぎると飛距離が出ず、重すぎると竿が折れる危険があるので注意しましょう。砂浜など遠投したい場面では少し重め(5〜8号程度)、足元中心なら軽め(3号程度)といった具合に調整します。
仕掛けは道糸の先にスナップ付きサルカン(糸ヨレ防止のための小さな金具)で接続します。市販のセット仕掛けにはハリス(針のついた糸)も結んでありますので、パッケージから出して道糸に結べばすぐ使える手軽さが魅力です 。初めは仕掛けを自作するより市販品を使った方が、糸絡みなどのトラブルが少なく釣りに集中できるでしょう 。
初心者向け便利アイテム
より快適にちょい投げ釣りを楽しむために、いくつかあると便利なアイテムも紹介しておきます。必須ではありませんが、あると格段に釣りやすくなります。
- 竿立て(ロッドスタンド):砂浜で釣るときは、ロッドを立てかけておける三脚タイプの竿立てがあると便利です。エサを付け替える際やアタリを待つ間にロッドを地面に直置きせず済むので、汚れ防止や仕掛けの絡み防止になります。堤防であればクーラーボックスに取り付ける簡易ロッドホルダーでも代用可能です。
- クーラーボックス:釣れた魚を新鮮に持ち帰るための小型クーラーボックスは用意しましょう。キスやハゼは鮮度が落ちやすいため、氷と海水で冷やして保存します 。さらに飲み物やエサの保存にも使えるので一石二鳥です。10リットル前後の小型のもので十分ですが、長めの竿を運ぶ際は腰掛け兼用サイズ(20L程度)があると座れて楽です。
- その他:タオルや手拭き用の水、仕掛けや小物を整理するタックルボックス、魚を掴むフィッシュグリップや針外し(プライヤー)も用意しましょう。エサで手が汚れてもタオルがあれば拭けますし、針外しがあればハゼのように小さい魚でも手早く針を外せます。これらも初心者のうちに揃えておくと便利です。
ちょい投げ釣りで使うエサと選び方
ちょい投げ釣りでは主に**生きた虫エサ(ゴカイやイソメ類)**を使用します。生エサに抵抗がある方もいるかもしれませんが、扱いやすい種類を選べば初心者でも安心して使えます。ここでは代表的なエサの種類と特徴、初心者向きの選び方や保存方法、そして釣果アップにつながるエサ付けのコツを解説します。
代表的なエサ
キス・ハゼ狙いの定番エサは、ゴカイやイソメといった砂泥地に生息する多毛類の虫エサです。釣具店で販売されているものでは、「アオイソメ」「イシゴカイ」「ジャリメ」などの名前を目にするでしょう。
- アオイソメ(青イソメ):やや大きめで太さもあるポピュラーな虫エサ。動きが活発で臭いも強く、キスだけでなく様々な海魚にアピールします。丈夫で餌持ちが良い反面、太いためキスやハゼ相手には噛み切られやすく、一匹を贅沢に付けると食い込みが悪い場合もあります。
- イシゴカイ:アオイソメに似ていますが、やや細めでキス釣りには特に人気のエサです。関西では「青イソメ」と呼ぶ場合、実際にはこのイシゴカイを指すこともあります 。匂いが強く集魚効果に優れ、かつ細身なのでキスが違和感なく喰いつきます。
- ジャリメ:最も細く小さな部類の虫エサです。キス釣りのエサとしては最高峰とも言われ、食い渋りのときにもジャリメなら反応する、と言われるほど。ただし非常に繊細で弱く、価格もやや高め。初心者が最初に使うには入手性の面でアオイソメやイシゴカイに比べ手に入りにくいかもしれません。
いずれのエサも購入時は小分けのパックに入っています。イシゴカイは1パック500円前後で売られていることが多く、細かく切って使えば半日近く楽しめる量が入っています 。初めてでどれを買うか迷ったら、釣具店の店員さんに「キス釣り用のエサをください」と相談すれば適切なものを用意してくれるでしょう。
初心者でも扱いやすいエサの種類と保存方法
生きた虫エサが苦手な初心者には、人工エサや加工エサという選択肢もあります。たとえば**「パワーイソメ」**等の商品名で売られている人工餌(疑似虫エサ)は、本物の虫のような見た目と匂いを持ちながら手が汚れにくく保存も簡単です 。冷蔵庫で保管すれば何度か使い回すこともできるので、虫が苦手な方やお子さんと一緒に釣る場合には強い味方となるでしょう 。
とはいえ、生エサの集魚力・即効性は人工エサにはかなわない場面もあります 。可能であれば生エサにも挑戦してみるのがおすすめです。虫エサを扱う際のポイントとしては、滑り止め用の「石粉」(専用の粉)を指先に付けると格段に掴みやすくなります 。エサ箱に少量入れておけば、ニョロニョロ動くイソメも簡単に掴めて針につけやすくなるでしょう。
エサの保存は基本的にその日のうちに使い切るのが理想ですが、余った場合は冷暗所で保管すれば数日は持ちます。湿った新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室に入れておく方法や、砂を入れた容器で飼っておく方法もあります。ただし弱ったエサは釣果に直結するので、次回の釣行まで日が空くようなら潔く処分し、新たに購入する方が無難です。臭いが出ないようビニール袋に密閉して燃えるゴミで捨てましょう。
釣果アップに繋がるエサ付けのコツ
エサ付けは釣果を左右する重要なポイントです。まず針への刺し方ですが、イソメ類の場合は針先をエサの頭部に刺し、そのまま針の軸に沿って真っ直ぐにエサを通します。針全体にしっかりとエサを馴染ませ、針先だけ少し出た状態にするのが理想です 。こうすることで魚に違和感を与えにくく、餌だけちぎられる無駄が減ります。
虫エサ(イソメ類)の正しい付け方一例。針先からまっすぐ刺して針の軸いっぱいに通し、針先を少しだけ出します 。垂らし(余り部分)は基本的に出さず、魚に飲み込ませるイメージで付けましょう。
エサの長さは狙う魚と針のサイズに合わせます。キス狙いの場合、エサが長すぎると先端だけついばまれて針掛かりしないことがありますので、針から1〜2cmほど垂れる程度にカットしましょう。逆に魚の活性が低く食い渋っているときはあえて少し長めにつけ、ゆらゆらと垂らしてアピールする手もあります(この垂れ下がった部分を「タラシ」と呼びます)。基本はタラシを出さず針全体に付け切るですが、状況に応じて調整してみてください 。
付け替えのタイミングも重要です。エサは海中で徐々にちぎれたり、フグなどに齧られて無くなったりします。15分〜20分に一度は仕掛けを回収してエサの状態を確認しましょう。なくなっていたら新しいものに付け替え、余裕があれば場所を少し変えて投げ直すと、魚のいるポイントに当たる可能性が高まります。
ちょい投げ釣りで狙える魚とシーズン
「ちょい投げ釣り=キス」と思われがちですが、実は狙える魚種は多彩です。ここでは初心者に特に人気のシロギス(キス)とマハゼ(ハゼ)について、その特徴やシーズンを解説します。また、ちょい投げで偶然釣れるその他の魚たちと、それぞれの適した時期についても紹介します。季節に応じてターゲットを変えれば、一年中ちょい投げ釣りを楽しむこともできます。
初心者に
人気のターゲット
- シロギス(キス):砂浜の女王とも呼ばれる白身魚で、その上品な味わいから食卓でも人気のターゲットです。ちょい投げ釣りでは主役とも言える存在で、遠浅の砂地に群れを作る習性があります。アタリは「プルプルッ」という小気味良い振動で伝わり、掛かった後も小気味良い引きが楽しめます。初心者でも数釣りが楽しめる魚であり、20cmを超える良型が釣れれば大いに自慢できるでしょう。
- マハゼ(ハゼ):河口の王様とも称されるハゼは、夏から秋にかけてファミリーに大人気のターゲットです。汽水域(川の河口周辺)の泥底に穴を掘って住んでおり、エサを落とすと素早く飛び出してきます。アタリは明確で、竿先をコツコツと叩くような振動です。引きは強くありませんが、次々に釣れるので初心者や子供でも飽きずに楽しめます。食べても香ばしく、唐揚げなどにすると絶品です。
どちらの魚も沿岸近くで生活するため、堤防や砂浜から手軽に狙えるのが特徴です。キスは塩分の高い海水域、ハゼはやや淡水が混じる汽水域を好む傾向がありますが、両方が混生するようなポイントも存在します。まずは自分の釣りたい魚をイメージしつつ、ポイント選びをすると良いでしょう。
シーズン別の狙い目
- 春:水温が上がり始める4〜5月頃、各地でキス釣りのシーズンが開幕します。春先のキスは型(サイズ)は小ぶりなことが多いですが、岸近くまで寄ってくるため初心者でも釣りやすいです。一方、ハゼはまだシーズン序盤で数は少なめですが、河口域でポツポツ釣れ始めます。
- 夏:6〜8月はキス・ハゼともに最盛期です。キスは産卵期を迎え群れが接岸し、砂浜からのちょい投げで数釣りが楽しめます(特に朝夕の涼しい時間帯は活発) 。特に夏休み時期は海水浴客が増えるため日中の釣りは制限されますが、早朝に狙えば入れ食い状態になることもあります 。ハゼも初夏から爆釣モードに入り、河川の河口域や浅場で入れ食い状態になることが珍しくありません。夏はファミリーフィッシングの花形ターゲットとも言えるでしょう。
- 秋:9〜10月になると、キスは引き続き釣れますが徐々に深場に移動し始めます。岸から狙えるのは10月頃までで、特に秋口は20cm級の良型が釣れるチャンスです。ハゼは秋がピークで、夏よりサイズも大きくなり15cm前後の大物が掛かることもあります(晩秋の11月頃まで楽しめます)。涼しくなるにつれて釣り人も過ごしやすく、秋のハゼ釣りは数・型ともに一年で一番楽しめるシーズンです。
- 冬:11月以降になるとキスは沖合へ去り、ちょい投げで狙うのは難しくなります。ハゼも水温低下で動きが鈍くなり、河川の深場に潜るため釣果は落ちます。ただ場所によっては初冬までポツポツ釣れることもあり、釣れたハゼは脂が乗って美味です。冬場は無理せず、暖かくなる春まで機材の手入れや情報収集に努めるのも良いでしょう。
その他に釣れる魚
ちょい投げ仕掛けを使っていると思いがけないゲストが釣れることもあります。砂地を好む魚以外にも様々な魚種がエサに食いついてくるため、何が釣れるか分からない楽しさがあります。例えば次のような魚たちが挙げられます。
- ベラ(キュウセンなど):カラフルな体色をしたベラ類は、岩礁帯や海藻周りに生息しますが、砂浜から投げても時折ヒットします。特に砂地に点在する石や消波ブロック周りで釣れることがあり、小型〜中型(10〜20cm)の個体が多いです。引きが強めで横に走るので、かかると意外にスリリングなファイトが楽しめます。
- カレイ:底生魚であるマコガレイやイシガレイが、ごく稀にちょい投げの仕掛けに掛かることがあります。特に初冬の時期、砂浜で投げていて小さなカレイが釣れることがあります(リリースサイズがほとんどですが)。専門に狙うにはより重いオモリで遠投する本格的な投げ釣りが必要ですが、偶然釣れたらラッキー程度に捉えておきましょう。
- カサゴ(ガシラ):根魚の代表であるカサゴも、防波堤際や沈み根があればエサに食いついてきます。夜行性ですが日中でも穴から出てエサを咥えることがあります。ただし岩場でのちょい投げは根掛かりと隣り合わせなので、あまり無理は禁物です。どうしても狙いたい場合は、足元に近い障害物周りを短く投げて探るようにしましょう。
- その他:この他にもフグ(小型のフグは頻繁に掛かりますが食用不可)、ヒイラギ(小さな銀色の魚で群れで掛かる)、セイゴ(小型のスズキがエサを横取りすることも)など、多種多様な魚がヒットします 。嬉しい外道もいれば困った外道もいますが、「何が釣れるかな?」と想像しながら仕掛けを回収する時間もまた、ちょい投げ釣りの楽しいひとときです。
初心者におすすめの釣り場
ちょい投げ釣りは足場の良い安全な場所を選べば初心者でも安心して楽しめます。ここでは関西エリアを例に、初心者に特におすすめの釣り場を紹介します。砂浜、河口、堤防とロケーション別にピックアップしますので、お住まいの地域や行きたい場所に合わせて参考にしてください。いずれもアクセスが比較的良く、魚影も濃いポイントばかりです。
砂浜で楽しむちょい投げ
**砂浜(サーフ)**はちょい投げ釣りの王道スポットです。関西で砂浜からキス釣りを楽しむなら、例えば以下のような場所が有名です。
- 須磨海岸(兵庫県神戸市):神戸市内から電車で行ける好アクセスの砂浜です。遠浅で砂地が広がり、海水浴場としても有名な場所だけあって施設も整っています。駅を出てすぐ浜辺なので家族連れにも人気で、キスやハゼの好釣場として知られています 。夏場(海水浴シーズン)の日中は遊泳客が多いため釣り禁止ですが、シーズン中でも朝早く行けばキスの数釣りが楽しめます 。投げる距離は30mも飛ばせば十分で、むしろ足元近くへのんびり投げて誘った方が釣れることもあります。
- 二色の浜海岸(大阪府貝塚市):大阪湾岸を代表するキス釣りポイントです。広大な海水浴場で駐車場やトイレも完備されており、ファミリーにも向いています 。遠浅の砂浜からのちょい投げで数釣りが期待でき、シーズンにはピンギス(小型のキス)が入れ食いになることも。ここも夏場の遊泳時間帯は釣りが制限されるため、朝夕や海開き前後の時期を狙うと良いでしょう。近隣の貝塚人工島の護岸も安全柵があり初心者に適したポイントです 。
この他、和歌山県の**片男波海岸(和歌山市)や淡路島・洲本海岸(兵庫県洲本市)**も関西では有名なキスポイントです 。洲本海岸は長大な砂浜と整備された護岸があり、良型のキスが狙える上に車で横付け可能なエリアもあり遠征する価値ありです 。砂浜は基本的にどこでもちょい投げが成立しますが、遠浅で人が少ない場所ほど初心者には釣りやすいでしょう。初めて行く場合は事前に駐車場やトイレの場所もチェックしておくと安心です。
河口で狙うハゼ
河口の穏やかな流れ込みはハゼ釣りの好適ポイントです。大阪近郊であれば、たとえば以下が知られています。
- 淀川河口(大阪市):大阪市を流れる淀川の河口周辺は、毎年夏〜秋にハゼ釣りで賑わいます。十三大橋付近から下流にかけての河川敷や伝法大橋周辺などが有名ポイントです 。浅い場所では延べ竿でも釣れますが、ちょい投げなら少し沖目を探れます。護岸も整備されており、足場が良く家族連れでも安心して楽しめます。週末には地域のハゼ釣り大会が開催されることもあるほどで、都会にいながら手軽に自然の釣りが味わえるスポットです。
- 大和川河口(大阪府堺市・大阪市):大阪と堺の境界を流れる大和川の河口もハゼ釣りの実績場です。河口右岸・左岸ともに広い河川敷があり、好きな場所で竿を出せます。河口域は潮の干満で水深が変化するので、干潮前後に浅場を狙うと効率よく釣れるでしょう。ハゼは岸際のほんの水深数十センチにもいるため、遠くに投げすぎず手前中心に狙うのがコツです。釣れたハゼはその場で唐揚げにして食べるイベントが行われるなど、こちらもファミリーに人気のポイントとなっています。
河口域で釣る際は、川の増水や急な潮位変化に注意しましょう。大雨の後は流木やゴミが多く釣りづらいこともあります。また、河川敷は足元が泥で滑りやすい場所もあるため、滑りにくい靴で行くことをおすすめします。淡水と海水が混ざるポイントだけに、生息する生物も多種多様で、ハゼ以外にもセイゴ(スズキの若魚)やボラ、小エビなどが見られて観察も楽しいエリアです。
堤防・護岸で安心して釣れる場所
堤防や護岸は足場が安定しているため、初心者には最も安心な釣り場と言えます。関西では海釣り公園や整備された岸壁が多数ありますが、ちょい投げ釣りに適した代表例を挙げます。
- 舞洲(大阪市此花区):大阪北港エリアにある人工島・舞洲の護岸は、有名な夢舞大橋下を中心にキス釣りスポットとして知られています。護岸には柵もあり、安全面でファミリーに最適です。駐車場からすぐ釣り座に行ける手軽さも魅力で、ちょい投げでキスや小型のカレイが狙えます。 橋の真下は根が荒いので少し外した場所を探りましょう。ここは短い距離のちょい投げで釣れるので、シーバスロッドやエギングロッドでもOK。ピンギス(小型のキス)が主体なので、仕掛けは6〜7号といった小さめの針が掛かりやすいです。朝夕マズメがベストですが、潮が動いていれば日中でも釣果が期待できます。
- 淡路島・岩屋港周辺(兵庫県淡路市):淡路島北部の岩屋エリアには、明石海峡大橋を望む釣りポイントが点在しています。中でも岩屋港周辺の護岸は足場が広く、トイレや駐車場も整っていて初心者に人気です。ここではキスだけでなく、カレイやガシラ(カサゴ)なども狙えるため五目釣りが楽しめます。淡路島全体で見ると洲本をはじめ各所に砂浜や護岸があり、キスの魚影が非常に濃いことで有名です 。少し遠征にはなりますが、初心者でも数・型ともに満足できる釣果を得やすいエリアと言えるでしょう。
そのほか、大阪南港魚つり園や兵庫県の南芦屋浜ベランダなど、柵付きで安全な海釣り公園的スポットもおすすめです。堤防や護岸では足元の穴や隙間に注意し、夜間は照明器具を持参するなど安全対策を万全にして釣行してください。足場が良いからといってライフジャケットを怠ることなく、事故ゼロで釣りを楽しみましょう。
キャストの基本と投げるコツ
ちょい投げ釣りの醍醐味である「キャスト」をマスターすれば、釣りの楽しさは倍増します。初心者でもできる基本的な投げ方から、狙ったポイントに投げ込むためのコツ、さらにはトラブルを減らす工夫まで解説します。キャストは練習すればするほど上達するスキルですので、正しいフォームを身につけて安全かつ快適に投げましょう。
初心者でもできる基本の投げ方
初心者にまず覚えてほしいのは**オーバースロー(上投げ)**と呼ばれる基本の投げ方です。これは野球のピッチャーのように竿を真後ろに振りかぶり、頭上から前方へ振り抜いて仕掛けを飛ばすフォームです。手順としては、
- 構え:利き手で竿を持ち、リールのベール(糸を放出する金具)を起こして人差し指でラインを軽く押さえます。もう一方の手で下部(リールシート付近)を支え、竿を後方へ倒します。仕掛けは竿先から1〜2m垂らした状態で、後方に誰もいないことを確認しましょう。
- 振りかぶり:振りかぶった竿を一気に前方へ振り出します。このとき肘を伸ばしすぎず、竿全体をしならせるイメージで力を伝えます。
- リリース:竿が約45度前方を指したタイミングで指を離し、ラインを解放します。これで仕掛けが飛んで行きます。
- フォロースルー:仕掛けが飛んだ後、竿を急に止めずそのまま前方へ倒し、ラインがスムーズに出るようにします。仕掛けが着水したらすぐにベールを戻し、余分な糸ふけを巻き取ってテンションを張っておきましょう。
もう一つ、近距離を狙う際に有効なのが**アンダースロー(下投げ)**です。竿を横または下から振る投げ方で、周囲に障害物があるときや、足場が低い釣り座で便利です。オーバースローに比べ飛距離は出ませんが、その分コントロールしやすい利点があります。まずはオーバースローで投げ、慣れてきたら状況に応じてアンダースローも試してみると良いでしょう。
距離よりも正確さを意識する理由
初心者のうちは「とにかく遠くへ飛ばそう」と力んでしまいがちですが、実は飛距離よりも正確なポイントへ投げることの方が大切です。魚は必ずしも遠くにいるとは限らず、むしろ岸近くのカケアガリ(海底の傾斜)や障害物周りに集中していることが多いです。30m先の何もない場所より、15m先の変化のある場所に投げ込む方がヒット率は上がります。
遠投を意識しすぎると、竿を振る際に力が入りフォームが崩れたり、指を離すタイミングが早すぎて真上に飛んでしまったりとミスが起こりやすくなります。まずは近場でも良いので狙った方向・距離に正確に投げる練習をしましょう。例えば、砂浜であれば目印になるもの(流木や浮遊物)が落ちていればそこをターゲットに投げてみると練習になります。狙い通りに仕掛けが入ると釣果にも直結し、「思ったところでアタリが出た!」という喜びにつながります。
また、正確さを意識すると結果的に無駄な根掛かりも減ります。ちょい投げ釣りでは「ここは安全」というコースを見つけたら、その範囲に投げ続けるのがコツです。闇雲に遠くへ届かせるより、ポイントを絞って釣る方が効率的であることを覚えておきましょう。
ライントラブルを防ぐための工夫
キャスト時に起こりがちなトラブルとして、ラインの絡まり(バックラッシュや高切れ)があります。これを防ぐための工夫をいくつか紹介します。
- スプールの糸巻き量を適正に:リールに巻くラインは多すぎても少なすぎても絡みの原因になります。スプール縁から1〜2mm下がりくらいのライン量が適量です。巻きすぎるとキャスト時に糸が暴走してバックラッシュを起こしやすくなります。
- キャスト前後のひと手間:投げる前にラインがらみがないか竿先〜仕掛けまで確認しましょう。投げた後は手でベールを戻し、ラインを軽く引いてしっかり巻き取るクセをつけます。こうすることでリールのたるみが取れ、次のキャストでの糸噛み(絡み)を防げます。
- 道糸とショックリーダー:重めのオモリを投げる場合やPEラインを使う場合は、ショックリーダー(先糸)を結ぶと安心です。ナイロンやフロロの太めの糸を数メートルつなぐことで、投擲時の負荷や根ズレに強くなり、高切れ(キャスト切れ)防止につながります。初心者であればナイロンラインのみでも十分ですが、もしPEライン(細くて強い編み糸)を使う場合は必ずリーダーを付けましょう。
- 風向きに注意:向かい風が強いときは無理に投げず、斜め方向から風を受けるように投げるか、風が弱まるのを待ちます。強風時はラインが煽られて放出時に絡みやすくなるため、飛距離も含め無理は禁物です。
万一トラブルが起きても、落ち着いて対処することが大事です。バックラッシュした糸は、リールのベールを起こして糸を引っ張りながらほぐしていけば直せます。絡んだ仕掛けは、一度回収してから解いても構いません。初心者のうちは失敗も付きものですから、トラブルも経験のうちと前向きにとらえ、ひとつずつ乗り越えていきましょう。
釣果を伸ばすコツと注意点
同じ場所で同じ道具を使っても、ちょっとした工夫で釣果に差が出るのが釣りの奥深いところです。初心者でも覚えておきたい、ちょい投げ釣りの釣果アップのコツと、注意すべきポイントを紹介します。これらを実践すれば、「今日はたくさん釣れた!」という嬉しい体験に一歩近づけるでしょう。
仕掛けを動かす誘い方
投げてアタリを待つだけでなく、仕掛けを意図的に動かして魚にアピールすることを「誘い」と言います。キス釣りでは特にこの誘いが効果的とされます。具体的には、仕掛け着底後にリールをゆっくり巻いて仕掛けを引きずる「ズル引き」という誘い方があります。オモリが海底の砂を引きずることで砂煙が上がり、それに気付いたキスがエサを見つけて食いつくという寸法です。一定の距離を引いたら糸ふけを取り、また数秒静止してアタリを待つ、という動作を繰り返すと効果的です。
ハゼ釣りの場合も、小まめに仕掛けを動かしてみましょう。ハゼは好奇心旺盛なので、エサが動くと追いかけてきます。竿先を小さく上下に動かしてチョンチョンとエサを跳ねさせたり、ゆっくり1〜2m巻いてみたりと変化をつけることで反応が得られることがあります。ずっと静止させるよりも、程よく動かしてアピールした方が魚とのコンタクトチャンスが増えると覚えておきましょう。
潮や時間帯を意識する
魚の活性は時間帯や潮汐によって大きく変わります。特に狙い目なのが朝夕のマズメ時(日の出前後と日没前後の薄明るい時間帯)です。この時間帯は小魚が動き出すため捕食者であるキスやハゼも活発になり、岸近くまで寄ってきます。夏場であれば、朝は5〜8時頃、夕方は17〜19時頃が一つの目安です。炎天下の真昼間よりも、マズメ時に集中して釣った方が効率的に釣果を上げられるでしょう。
また、潮汐(潮の満ち引き)も釣果に関係します。一般に、潮が動き始めるタイミングで魚の食い気が上がると言われます。干潮から満潮に向かう上げ潮のタイミングや、満潮から下げに転じるタイミングは狙い目です。特に河口域のハゼは、干潮時には深場に避難していても上げ潮で浅場に戻ってきます。潮見表を確認して潮が動く時間帯を狙うと良いでしょう。もっとも、初心者のうちはあまり難しく考えず、釣りやすい時間・都合の良い時間に出かけて経験を積むことが大事です。釣れない時間帯も「魚が休憩中かな?」くらいに前向きに捉え、次のチャンスタイムに備えましょう。
根掛かりを防ぐための投げる位置と工夫
ちょい投げ釣りで悩ましいのが根掛かりです。せっかくの仕掛けが海底の障害物に引っかかってロストしてしまうと、時間もお金ももったいないですし気持ちも萎えてしまいます。根掛かりは完全には避けられませんが、ある程度防ぐ工夫はできます。
まず、投げる位置を工夫しましょう。初めての釣り場では、遠投せず手前から探るのが基本です。特に足元近くに沈み根(岩や消波ブロック)がある場合、いきなり遠くへ投げると回収時に根の上を通って引っかかることがあります。最初は短い距離で試し、根掛かりしないか確認してから徐々に距離を伸ばすと安全です。また、左右に少し投げ分けてみて、根掛かりが少ないコースを見極めることも大切です。
もし根掛かりしてしまったら、無理に引っ張らないことです。竿をあおって外そうとすると糸が切れたり竿が折れたりする原因になります。一旦糸を緩めて仕掛けの重みで外れるのを待つ場合もあります。それでもダメなら、ラインを手に巻き付けてゆっくり一定の力で引っ張り、ハリスや仕掛けの弱い部分から切るようにしましょう。仕掛けを回収できなくても慌てずに、予備の仕掛けに付け替えて再開すればOKです。
根掛かり対策として、捨てオモリ式(オモリを細いラインで付け、根掛かり時はオモリだけ切れるようにする)の仕掛けや、遊動式テンビン(引っかかりにくい構造の天秤)を使う手もあります。しかし初心者のうちは、仕掛けはシンプルな固定テンビンで十分です。貴重な仕掛けを失わないよう、地形を読みつつ慎重に攻める——これも釣りの腕の見せ所です。
釣った魚を美味しく食べる方法
釣りの楽しみはやはり「食べること」。自分で釣った魚を自分で調理して食べるのは格別です。キスもハゼも小ぶりながら味は抜群で、初心者でも簡単な料理で美味しくいただけます。ここでは代表的なキス・ハゼ料理と、初心者におすすめのシンプルレシピを紹介します。釣って楽しい、食べて美味しい、二度美味しい体験をぜひ味わってください。
キスの天ぷら・フライは定番!
シロギス(キス)は天ぷらの定番です。釣りたてのキスを捌くのはとても簡単で、ウロコを軽く落として頭とワタ(内臓)を取るだけ。身が柔らかいので三枚おろしにしなくても、そのまま開いて背骨を外す「背開き」にすればOKです。あとは市販の天ぷら粉を冷水で溶き、開いたキスにくぐらせてカラッと揚げれば完成。上品な白身がホクホクふわふわで、塩を振るだけでも絶品です。釣り場でさばいて持ち帰れば、家で調理がぐっと楽になります。
もう一つの人気メニューはキスフライ。下処理したキスに小麦粉・溶き卵・パン粉の順で衣をつけ、油で揚げます。天ぷらよりもしっかり揚げ色がつくまで加熱することで、骨まで丸ごと食べられるのがフライの利点です。タルタルソースやレモンを添えれば、お子さんにも喜ばれるご馳走になります。
キスは他にも塩焼きや南蛮漬け、刺身(鮮度が極めて良ければ)など多彩な料理にできますが、まずは天ぷらとフライから試してみるのが間違いありません。シンプルな料理ほど素材の味が際立つので、新鮮な釣り魚ならではの美味しさを感じられるでしょう。
ハゼの唐揚げ・甘露煮で骨ごと美味しく
ハゼは唐揚げが一番手軽で美味しいです。ヌメリを取るために塩でもみ洗いし、ウロコと頭と内臓を取り除いたら下処理完了。小ぶりなものは丸ごと、大きめなら開いて背骨を取っても良いでしょう。キッチンペーパーで水気を拭き、醤油・酒・おろしニンニク少々で下味をつけておきます(時間がなければ省略可)。あとは片栗粉をまぶして油でカラリと揚げるだけです。二度揚げすると骨までバリバリ食べられて香ばしさ抜群。揚げたてを頬張れば、ビールが進むこと間違いなしです。
もう一品、釣り人に愛されるハゼ料理が**甘露煮(佃煮)**です。たくさん釣れて持ち帰りきれないほど…という場合には甘露煮にして保存すると長く楽しめます。小〜中型のハゼをウロコ・内臓処理して素焼きにし、醤油・砂糖・みりん・酒・生姜を合わせた煮汁でコトコト煮詰めます。骨まで柔らかくなり、濃厚な味が染みたハゼはご飯のお供やお茶請けに最高です。冷蔵庫で日持ちしますので、お正月のおせち料理にする地域もあります。
ハゼは他にも天ぷらや南蛮漬け、味噌汁の具などにも向いています。特に小さなハゼは出汁がよく出るので味噌汁にすると美味しいです。いずれにせよ、自分で釣った魚は残さず食べるのが釣り人のマナーであり楽しみ方。最初は勝手が分からないかもしれませんが、料理も経験です。ぜひ色々なレシピに挑戦して、釣果を味わい尽くしてください。
初心者におすすめのシンプルレシピ
釣りたての魚はシンプルな料理で十分美味しいもの。凝ったことをしなくてもできる簡単レシピをいくつか紹介します。
- キスの塩焼き:キスを3枚おろし(または開き)にして塩を振り、グリルや魚焼き器で焼くだけ。レモンを絞れば爽やかな風味に。小骨が気になる場合は開いて骨を抜いてから焼くと食べやすいです。
- ハゼの味噌汁:下処理した小型のハゼを、水から煮出して出汁を取ります。アクをすくい、具材はハゼのみでもOK。味噌を溶き入れ、お好みでネギを散らせば完成です。ハゼの旨味が溶け出した上品な味噌汁になります。
- キスとハゼの混ぜ寿司:唐揚げや天ぷらにしたキス・ハゼをほぐし、甘酢で味付けしたご飯に混ぜ込めば即席の混ぜ寿司に。白ごまや刻み海苔を散らして見た目を整えれば、釣魚パーティーの一品にもなります。
最初のうちは難しく考えず、「揚げる・焼く・煮る」の基本調理で十分です。新鮮な魚はそれだけで旨みがありますから、自信がなくてもシンプル調理でぜひ味わってみてください。
まとめ
最後に、本記事のポイントをまとめます。
- ちょい投げ釣りは初心者がキャストの楽しさを味わいながら魚を釣ることができる入門釣法。サビキ釣りと並んで手軽で人気の釣り方です 。
- 道具立てはシンプルかつ安価で始めやすいです。ロッドとリールのセットに、オモリと針の付いた市販仕掛けがあればすぐに始められます 。
- 狙える魚はキス・ハゼを中心に多彩。キスは遠浅の砂浜で数釣りが楽しめ、ハゼは河口域でファミリーにも人気のターゲットです。その他にもベラやカレイなど思わぬ魚が掛かることもあります 。
- 釣り場選びは重要。砂浜・河口・堤防など関西には初心者向けの好ポイントが豊富です(例:須磨海岸、二色の浜、淀川河口、舞洲、淡路島洲本海岸など) 。
- キャストのコツや誘い方、潮時などテクニックを覚えれば釣果アップが期待できます。基本を押さえて経験を積むことで、釣れる量もどんどん増えていくでしょう。
- 釣ったキス・ハゼは天ぷらや唐揚げにして絶品。自分で釣った魚を味わう体験は、釣りの満足感をさらに高めてくれます。
以上、初心者向けにちょい投げ釣りの始め方と攻略法を紹介しました。シンプルな仕掛けで手軽に始められるちょい投げ釣りは、釣りの楽しさを存分に感じられる素晴らしい方法です。ぜひこの記事を参考に、安全第一でチャレンジしてみてください。自然の中でのんびり竿を振り、美味しい魚を手にする喜びは、きっとあなたを釣りの虜にしてくれるでしょう。


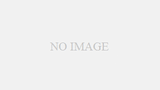
コメント