「淡路島で夜釣りに挑戦してみたい!」そんな人におすすめなのが、アジング&メバリングを中心とした“ライトゲーム”。軽いタックルで気軽に始められ、アタリの感触やヒットの瞬間をダイレクトに楽しめるのが魅力です。特に淡路島は潮通しの良い海域が多く、堤防や常夜灯周りで初心者でも十分に釣果を出せる絶好のフィールド。この記事では、淡路島でのライトゲームの基本、釣れる魚・時期、ポイント選び、釣り方のコツをわかりやすく解説します。これを読めば、あなたも夜の淡路島でアジやメバルの引きを楽しめるはず!
ライトゲームとは?アジング&メバリングの魅力
まずは「ライトゲームって何?」というところからスタートしましょう。アジやメバルなどを狙うこの釣りは、道具も軽くて扱いやすく、初心者でも始めやすいのが特徴です。小さな魚でもライトタックルならしっかりと引きが味わえ、夜の静かな海で手元に伝わるアタリの興奮は格別です。また仕掛けやポイントを工夫することで、他の釣り方では狙いにくい魚も手軽に釣れるのも魅力です。
ライトゲームとは?どんな魚が狙える釣り?
ライトゲームとは、その名の通り軽量なタックル(道具)を使ったルアーフィッシングのことです。主に堤防や岸壁から、アジ(マアジ)やメバルをはじめとする比較的小型の魚をターゲットにします。アジング(アジ狙い)やメバリング(メバル狙い)が代表的で、他にもガシラ(カサゴ)やチヌ、セイゴ(スズキの若魚)などもヒットすることがあります 。とにかくライトな装備で気軽に始められるため、初心者やファミリーでも楽しみやすい釣りスタイルです。
ライトタックルなら小さなアタリも敏感に感じ取れ、夜釣りならではの静けさと興奮が味わえます。
ライトゲーム最大の魅力は、小さな魚でも大きな手応えを楽しめることです。ライトロッドが大きく曲がり、手元に「ググッ」という力強い引きが伝わると、小物釣りとは思えないスリルがあります。またルアー釣りなのでエサのニオイも気にならず、道具もコンパクトにまとめられて機動力抜群です。夜釣りなら日中より人も少なく涼しい中で釣りに集中できるのもポイントです。「魚を釣る楽しさ」と「手軽さ」を両立したのがライトゲームなのです。
アジングとメバリングの違いと共通点
ライトゲームの中でもアジング(アジ狙い)とメバリング(メバル狙い)は二大ジャンルです。共通する点は、どちらも小型ルアー(ワームや小型プラグ)を用いる夜釣りが中心で、タックルも似たような構成になること。ただし狙う魚の習性の違いから、釣り方や道具選びに若干の違いがあります。
まずアジングは回遊魚であるアジを狙う釣りで、アジは群れで中層〜表層を回遊しながらプランクトンや小魚を捕食します。アジングロッドは非常に感度が高く作られ、わずかなアタリも取れる先調子(ティップが硬め)の調子が多いです。一方メバリングは根魚であるメバルがターゲットで、メバルは岩場や堤防際に潜み、夜になると表層近くまで浮いてエサを追います。メバリングロッドは魚に違和感を与えにくい胴調子(全体にしなやか)のものが多く、引き味を楽しめる余裕もあります 。つまりアジングロッドは感度重視で掛けにいく調子、メバリングロッドは魚に乗せて掛ける調子という違いがあります 。
とはいえ、どちらのロッドでもアジ・メバル両方狙うことは可能です。実際ライトゲーム愛好家は1本のロッドで両方の魚種を釣ることも多く、ルアーも共通するものがあります。ただし、大型の尺メバル(30cm級)が掛かる可能性がある場面ではパワーのあるメバリングロッドが安心、といった具合に狙う魚の大きさやスタイルに応じて使い分けるのが理想です。またアジとメバルは生態も異なるため、釣り方のコツや効果的なアクションも少しずつ違うのです(これについては後述するコツの章で詳しく解説します)。
淡路島でライトゲームが人気の理由
淡路島がライトゲームの聖地と言われるほど人気なのには、地形と海況の恵まれた条件があります。まず淡路島は大阪湾・播磨灘・紀伊水道に囲まれた立地で、周囲を流れる海流が非常に豊富です 。明石海峡や鳴門海峡といった強い潮流が発生するエリアに近く、プランクトンやベイトフィッシュ(小魚)が豊富に育つため、アジ・メバルを含む魚影がとても濃いのです 。実際、淡路島は関西圏でもトップクラスのアジングフィールドとして知られ、一年を通してアジが狙えるほど魚影が安定しています 。メバルも例外ではなく、冬から春にかけては大型が狙える好漁場となります。
さらに釣り場の多さとアクセスの良さも人気の理由です。淡路島には島全体に数多くの港や波止が点在し、車での移動もしやすいので短時間のナイトゲームにも向いているのです。堤防には照明(常夜灯)が設置されている場所も多く、夜でも比較的安全に釣りやすい環境が整っています。たとえば岩屋港などは駐車場やトイレも完備され足場も良好で、家族連れにも人気の釣り場です 。このように魚影の濃さ×釣り場環境の良さが相まって、淡路島はライトゲーム初心者にもうってつけのエリアとなっているのです。
淡路島でライトゲームを楽しめるシーズンと時間帯
「いつ行けば釣れるの?」というのは多くの初心者が抱く疑問。淡路島では季節や時間帯で狙える魚が変わります。ここではベストシーズンと狙い目の時間を解説します。季節ごとの魚の動きと、それに合わせた釣行タイミングを知ることで、無駄なく効率よく釣果アップを狙いましょう。春夏秋冬それぞれの特徴を押さえて、淡路島のナイトゲームを攻略してください。
春〜初夏
春から初夏(3月〜6月頃)にかけては、メバルが好調に釣れるシーズンです。水温が徐々に上がり始める春先、冬の間じっとしていたメバルが活発にエサを追い始めます 。特に3〜4月はメバルにとって一年で最も釣りやすい時期の一つで、産卵前後の個体が荒食いするため高活性になります 。サイズも良型が混じりやすく、寒い冬を越えた大物メバル(尺メバル)を狙えるチャンスでもあります 。
この時期のメバル狙いは、なんといっても常夜灯周りが外せません。日没後、港の明かりにプランクトンや小魚が集まると、それを狙ってメバルも表層近くまで浮いてきます 。常夜灯の明暗がくっきり分かれる境目付近は絶好のヒットポイントです。ライトゲーム初心者は、明かりの下を丹念に探るだけでも比較的簡単にメバルの反応が得られるでしょう。実際、ナイトゲーム中心のメバル釣りでは「まず常夜灯を探せ」が鉄則と言われるほどで 、安全面でも明るい場所の方が足場確認がしやすいメリットもあります。
春先はまだ夜間冷え込みますが、防寒さえしっかりすれば釣果に恵まれる可能性大です。日中水温が上がった夕マズメから夜の始めにかけて活性が上がりやすいので、仕事帰りの短時間でも狙ってみる価値があります。メバルは群れでなく単発で付いていることも多いので、一匹釣れたら周辺のレンジ(層)を集中的に攻めると連発しやすいでしょう。
夏〜秋
夏から秋(7月〜10月頃)はアジングのベストシーズンと言えます。水温が高い夏場は港湾部に豆アジ(5〜10cm程度の小アジ)が大量接岸し、数釣りが楽しめる時期です 。日中のサビキ釣りでも入れ食いになるほど小アジが群れていますが、夜間にライトゲームで狙うとよりアクティブに数・サイズともに狙えることがあります。「サビキで十分では?」と思われがちですが、ルアー(ワーム)で誘うアジングでは活性の高いアジを効率よく釣り分けられるため、結果的にサビキ以上の釣果やサイズアップに繋がるケースもあるのです。
特に**秋口(9月〜10月)**になると、夏に育った小アジが15cm前後に成長し、小アジ釣りの最盛期を迎えます 。この頃のアジは夜行性が強く、夕暮れから夜にかけて一斉に接岸してきます。常夜灯の明かりに無数のアジが群れてライズ(捕食で水面をパシャつくこと)する光景も珍しくありません。こうなればアジング天国で、ほぼ入れ食い状態になることもあります。ルアーに反応する活性の高い個体はサイズも比較的大きめで、釣って楽しく食べても美味しい20cm級も期待できます。
夏〜秋にアジングをする際は、群れの回遊パターンを読みましょう。群れが回ってくるタイミングでは連続ヒットしますが、抜けるとパタリと止むことがあります。回遊待ちの時間でも焦らず、レンジ(タナ)を変えてみたりジグヘッドの重さを調節したりして探ってみてください。またこの季節はタチウオなど他のフィッシュイーターも常夜灯周りに入ってきます。タチウオが多いとアジが散ってしまうため、もし夜の海面にギラつくタチウオの姿が見えたら、群れが去るまで待つかポイントを変える決断も大切です 。
冬
冬(11月〜2月)は寒さで釣り人も減りますが、実は一年で最もメバルが熱い季節です。メバルは冬〜初春がハイシーズンであり 、特に11〜12月には産卵前の荒食いで大型メバルが狙いやすくなります 。水温が下がる12〜1月頃は一時的に渋くなることもありますが、その分釣れればサイズが良いのが冬の特徴です。実績では尺メバル級が出るのも冬場ということが多く、寒さに耐えてでも出会う価値のあるターゲットと言えるでしょう。
冬場のライトゲームは夜釣りとはいえ非常に冷え込みますので、防寒対策は万全にしてください。手先がかじかむと繊細なアタリも取りづらくなるので、カイロや防風インナーで寒さを軽減しましょう。釣り方としては、活性が低い冬メバルにはスローな誘いが鉄則です。極力ルアーをゆっくり見せて食わせるイメージで、一定レンジをただ巻きしたり、時折小さくさびいて誘いを入れたりすると効果的です。「寒いから今日は釣れないかも…」と諦めず、ポイントと釣り方を工夫すればしっかり応えてくれるのが冬のメバル釣りの醍醐味です。
一方、冬のアジングもポイント次第では可能です。淡路島の場合、西岸よりも水深のある東岸エリア(洲本〜津名エリア)の方が冬もアジが残りやすい傾向があります 。真冬の1〜2月でも、深場の漁港や橋脚周りではアジが釣れた例もあります。ただし数も少なく難易度は高めなので、冬は無理せずメバル狙いにシフトした方が効率的かもしれません。寒い季節に無理に長時間粘るのは体にも良くないので、防寒着を着込んで短時間勝負でポイントをランガン(移動)するのも手です。
夜釣りのベストタイムは?夕マヅメ〜夜半過ぎを狙え
夜釣りにおいて最も釣果が上がりやすい時間帯は、日没前後から夜の前半にかけてです 。具体的には夕マヅメ(日が沈む直前〜直後の1〜2時間)から、夜9時〜深夜0時頃までが一つの山場となります 。夕マヅメにエサを追い始めた魚たちが活発化し、日没後の暗闇に乗じて浅場まで出てくるため、このタイミングで一気に食い気が立つのです 。実際、アジ・メバルともに日没直後〜数時間で時合(短期的によく釣れる時間)が訪れることが多く、「まずはその時間帯を逃さず狙う」ことが大切です。
常夜灯の下にはプランクトンや小魚が集まり、それを追ってアジも接岸します。日没後しばらく経った頃から活発に捕食を始め、写真のような良型アジがヒットすることも 。
夜半(深夜0時)を過ぎると、一度活性が落ち着く魚もいます。しかし常夜灯の効いたポイントでは、真夜中でもポツポツと釣れ続くことがあります。さらに早朝近くになると朝マヅメ前の3時〜5時に再度活性が上がる魚もいます 。特に夏〜秋のアジは朝まずめまで釣れるケースもあるので、体力と相談して狙ってみるのも良いでしょう。ただし、人間の集中力や体温も夜更けには低下します。慣れないうちは無理せず夜10時〜11時頃までにしておき、余裕が出てきたら朝まずめまでチャレンジしてみるのがおすすめです。
また、月明かりや天候も夜釣りの釣果に影響します。月が明るい満月前後の夜は海中も明るくなりすぎて魚が警戒しやすい反面、月明かりがない暗い夜(新月や曇天)は魚が大胆に浅場まで出てきて釣れやすい傾向があります 。淡路島のように街明かりの少ない場所では月明かりの影響も大きいので、「今日は月が暗いからチャンスだ」といった視点で釣行日を選ぶのも面白いでしょう 。いずれにせよ、潮の満ち引きも含めて自然条件に目を配り、その日その時間のベストを狙うことが夜釣り成功の近道です。
淡路島のおすすめ釣りポイント
淡路島はエリアによって海の表情がガラッと変わります。ここではアジング・メバリングにおすすめの堤防や漁港を、北・中・南エリア別に紹介します。地形や潮通し、常夜灯の有無などポイントごとの特徴も解説するので、自分の行きたい場所を見つけてみてください。ただし釣り禁止区域や夜間立ち入り制限もあるので、ルールとマナーを守って安全に楽しみましょう。
北淡エリア
淡路島北部(北淡エリア)は明石海峡に面し、潮通し抜群の好ポイントが集まっています。代表格は岩屋港です。岩屋港は淡路島北端に位置し、明石海峡大橋の真下にある大きな港です。ここは速い潮流の恩恵で魚影が非常に濃く、一年中多彩な魚種が狙える人気スポットです 。堤防からアジ・イワシ・サバはもちろん、メバルやガシラ、青物までヒット実績があり初心者から上級者まで賑わいます 。足場が良く駐車場やトイレも整備されているため家族連れにも安心で、ライトゲームの入門に適した釣り場と言えるでしょう 。常夜灯も港内各所にあり、夜間でも明るく釣りやすいのが嬉しい点です。
もう一つ北淡エリアで名前が挙がるのが仮屋漁港です(淡路市仮屋)。こちらは東側に位置し、大阪湾に面した漁港で、かつてアオリイカやアジングで有名でした。しかし近年、防波堤にロープが張られて立ち入り禁止となっているとの情報があります 。具体的な理由は定かではありませんが、釣り人のマナー問題などが影響したとも言われています 。仮屋漁港を訪れる際は、立入禁止エリアの有無を現地で確認し、絶対に侵入しないようにしましょう。堤防付け根や周辺の岸壁から竿を出せる場所もありますが、安全第一とルール厳守でお願いします。
北淡エリアには他にも、岩屋港沖に渡船で渡る岩屋一文字や、浦港・尾崎港といった小規模漁港が点在します。これらの多くは明石海峡の潮通しが良く、常夜灯も整備されたポイントが多いです。潮の流れが速い分、魚の活性も高い反面、初心者はオモリ(ジグヘッド)の重さ調整や足元の安全に注意が必要です。釣り禁止区域については、岩屋港でも東波止の先端はフェンスで封鎖され立入禁止になっています ので、現地の看板やフェンスがあれば従ってください。総じて北淡エリアはアクセスが良く人気も高いですが、その分ルールも整備されています。マナーを守って気持ちよく釣りを楽しみましょう。
中淡エリア
中淡エリア(淡路島中央部)には、島内最大の港である洲本港があります。洲本港は淡路島有数の規模を誇る港で、港内の場所によっては水深が10mを超える深場もあり、太刀魚や青物まで釣れるポテンシャルを持ちます 。広大な港内には常夜灯も設置され、夜のアジング・メバリングでも実績十分です。特に秋の小アジシーズンや晩秋〜初冬の尺アジ狙いで訪れる釣り人も多く、四季折々で狙える魚種が豊富な点で初心者にもおすすめできます 。釣具店が近くにあるなど利便性も高く、何かと安心して釣りを楽しめるポイントです。
洲本港では沖向きの防波堤や岸壁沿いが狙い目です。常夜灯周辺には回遊アジが溜まりやすく、また水深がある分昼間でもアジやイワシの反応があることがあります。夜のメバル狙いでは、港内にある係留船の影や足元の壁際をスローリトリーブで誘うとヒットすることがあります。広い釣り場ゆえにポイントの見極めが難しい場合は、他の釣り人が多く竿を出している場所=魚影の濃い場所と判断して入れてもらうのも一つの手でしょう。もちろん地元の方への挨拶と配慮は忘れずに。
中淡エリアもう一つの注目は江井漁港(淡路市江井)です。江井漁港は西浦(瀬戸内海側)に位置する小さな港ですが、近年エギング(イカ釣り)の名所として脚光を浴び、訪れる人が増えています 。秋のアオリイカだけでなく、サビキ釣りでのアジ・イワシの釣果も良好なためファミリーにも人気です 。ライトゲームの観点でも、夏〜秋には豆アジ・小アジが回遊し、夜にはメバルやガシラも狙えます。港内に常夜灯が複数あり夜釣りしやすい点も魅力です。江井といえばお香(線香)の生産地として有名で、港周辺にもほのかに香りが漂っています。釣りをしながらそんな土地柄を感じるのも一興かもしれません。
中淡エリアには他にも、志筑や都志、育波など規模大小様々な漁港があります。いずれも初夏〜秋にかけてはアジの回遊があり、冬場も風裏になって釣りやすい場所が点在しています 。各港ごとに駐車スペースや禁止区域が異なるため、訪れる際は下調べをしておきましょう。中淡エリアは島の中央に位置するためどこからもアクセスしやすく、その日の風向きや潮に合わせて東岸・西岸を選べるという利点もあります。状況に応じてフットワーク軽く釣り場を移動するのも、釣果アップには有効です。
南淡エリア
淡路島南部(南淡エリア)は、南あわじ市を中心としたエリアで、福良湾をはじめ大小の漁港や波止が点在するエリアです。観光地のイメージが強い南淡ですが、実はライトゲームの隠れた好ポイントが多く存在します。
まず外せないのは福良港(福良湾)です。福良港は南あわじ市の西側にある天然の良港で、湾内は波静かで足場も良好なポイントが多いです。特筆すべきは常夜灯の数の多さで、港内各所に明かりがあり夜釣りにも最適な環境となっています 。湾内は一部立入禁止区域もありますが、釣り可能なエリアも多く島内外から多くの釣り人が訪れる人気スポットです 。アジングでは秋に20cmオーバーのアジが接岸することもあり、メバリングでも堤防沿いに良型が潜んでいます。足場が平坦なケーソンや、手すりが整備された護岸もあるため、初心者でも安心して夜釣りを楽しめるでしょう。
次に注目したいのが**伊毘漁港(いび)**です。伊毘は南淡エリアの南東端、大鳴門橋にほど近い場所にあります。どちらかというと青物(回遊魚)やエギングの実績が多い港ですが、景色が良く穴場感のあるポイントです 。潮通しも良いのでアジ・メバルも回ってきますし、規模が小さい分人も少なめでのんびり釣りができます。夜は橋のライトアップを眺めながら釣り糸を垂れるという贅沢も味わえます。
さらに阿万漁港(あま)も南淡の隠れスポットです。阿万地区の河口部にある波止で、隣接する砂浜は夏場海水浴場になります。シーズンによって差はありますが、秋から初冬にかけて25cmオーバーのアジが回遊してくることがある穴場です 。普段は釣り人が少なくプレッシャーが低いため、ハマれば良型連発ということも。夏場は海水浴客で釣りどころではないですが、シーズンオフの平日は貸切状態で釣りが楽しめます。足場はテトラ帯や砂浜が混在するので夜間は注意が必要ですが、その分探せば自分だけのポイントを見つけられる魅力もあります。
南淡エリア全体に言えるのは、他エリアに比べ釣り人が少なめでマイペースに楽しめることです。一方で、釣り禁止や立入り制限情報が少ないため、現地での自己判断も求められます。地元漁協の看板やロープなどを見つけたら絶対に立ち入らない、民家が近い場所では夜間は極力静かにするなど、より一層のマナー遵守を心がけましょう。「隠れスポット」とはいえ地元の方あっての釣り場です。ルールを守ってこそ長く楽しめることを忘れないでください。
注意点
淡路島内の各釣り場には、近年いくつかの立入禁止区域や夜間釣り禁止エリアが設定されている場所があります。これは一部の心ない釣り人の迷惑行為や事故防止のための措置です。例えば前述の仮屋漁港の防波堤封鎖もそうですし、佐野漁港では一部エリアが地元民以外立入禁止となっています 。佐野漁港では過去に釣り人が漁協の水道を無断使用したり、夜通し騒いだりしたことが原因で禁止措置が取られたと言われています 。このように、マナー違反が積み重なれば釣り場そのものが失われてしまうことを肝に銘じましょう。
釣行前にはインターネットや釣具店で最新の釣り禁止情報を調べるのがおすすめです。また現地に「釣り禁止」「立入禁止」の看板やロープが張られている場所があれば、絶対に立ち入らないでください 。そればかりか、路上駐車やゴミ放置など地元に迷惑となる行為も厳禁です 。釣り場によっては夜間○時以降は釣り禁止というルールがあったり、花火や大声などを禁止する貼り紙があったりします。自分の身を守る意味でもルールは遵守し、注意書きには必ず従うようにしましょう。
最後に、夜釣り特有の注意としては懐中電灯(ヘッドライト)の使い方があります。真っ暗な堤防で明かり無しは危険ですが、だからといって強いライトで海面を照らし続けると魚が散ったり周囲の迷惑になります。足元を照らす最低限の使用に留め、海に向けて常時ライトを当てない、車のライトを岸壁に向けっぱなしにしない、といった配慮も必要です。近くに民家があるポイントでは夜分にライトが差し込むだけでも不快に感じる方もいます。安全確保とマナーの両立を心がけて、気持ちよく夜釣りを楽しみましょう。
ライトゲームに必要なタックルとおすすめルアー
「どんな竿を使えばいい?」「ジグヘッドの重さは?」初心者が悩みやすいタックル選びをわかりやすく解説します。ライトゲームは道具選びが釣果に直結しやすい釣りです。ロッドやラインの太さ、ルアーの種類によってアタリの出方が変わるため、自分に合った基本装備を整えましょう。ここでは**ロッド&リール、ラインシステム、ルアー(ワーム)**について、初心者に向けた選び方のポイントを紹介します。
ロッドとリールの選び方
ライトゲーム用のロッド(竿)は全長6〜7フィート前後(約1.8〜2.1m)の軽量ルアーロッドを使用します。アジング専用、メバリング専用と銘打たれたロッドも多いですが、初心者であればどちらか一方のロッドで兼用して構いません。長さは扱いやすい7ft前後、硬さはルアー重量表示でだいたい0.5〜8g程度のモデルが汎用性が高いです。ロッドはとにかく感度が命。手元に伝わるわずかなアタリを拾う必要があるため、カーボン素材で張りのあるロッドが適しています。ただし先端が硬すぎるとメバルの食い込みを弾く恐れもあるので、穂先はある程度柔軟なソリッドティップのものが初心者には扱いやすいでしょう。
リールは小型スピニングリールの1000番〜2500番クラスを合わせます。アジング主体なら軽量な1000〜2000番、メバルまで視野に入れるなら2000〜2500番が目安です 。ドラグ性能が良いものを選ぶと、細いラインでも大物の引きに耐えられます。近年ではドラグの滑り出しが滑らかなライトゲーム向けリールが各社から出ているので、店頭でハンドルを回してみて違和感なく動くものを選ぶと良いでしょう。予算的にはロッド・リールそれぞれ1万円前後から手に入りますが、長く続けるつもりならもう少し上位機種にすると快適さが違います。軽さとバランスの良さも重要なので、ロッドにリールをセットして持ってみてしっくりくる組合せを探してみてください。
なお、ロッドはアジングロッドとメバリングロッドで調子が違うと前述しましたが、初心者のうちは気にしすぎなくてOKです。どちらで始めても両方の魚は釣れますし、後々専用ロッドが欲しくなったら買い足せば良いでしょう。「まずは一本」で始めたい方には、感度高めのアジングロッドの方がどちらかと言えばおすすめです (アジングロッドの方が掛けていく釣りのため違和感なくメバルにも流用できるため)。ただしその場合もメバルが掛かった時にバレ(針外れ)やすい点だけ注意が必要です。逆にメバリングロッドでアジを狙うなら、アタリをしっかり掛けにいくテクニックを磨きましょう。
ライン・リーダーの基本構成
ライトゲームで使うラインは、大きくPEライン(編み糸)かエステルラインかフロロカーボンラインの3択になります。初心者には扱いやすさと汎用性の高いPEラインがおすすめです。PEラインはとても細くて強度がある上、水に浮く性質があるため表層〜中層の釣りに向いています。アジング・メバリングともに号数は0.3〜0.6号程度(強度で約2〜8lb)が標準で、迷ったら間を取って0.4号前後を巻いておけばほぼ対応できます 。PEラインは伸びが極めて少ないため感度が良く、遠投性能にも優れるので淡路島のように広い釣り場でも安心です。
PEラインを使う場合、先端に**1m前後のリーダー(ハリス)**を結ぶのが一般的です。リーダーにはフロロカーボンラインの6〜8lb(1.5〜2号程度)を使うと良いでしょう。リーダーを付ける理由は、岩や堤防との擦れ防止と、ルアーを結ぶ際の結び替えを容易にするためです。PEラインは擦れに非常に弱いので、ショックリーダーでカバーします。結束(ノット)は最初は難しいかもしれませんが、FGノットや電車結びなどシンプルで強い結び方を覚えましょう。一方、エステルライン(ポリエステル製の極細ライン)はアジング上級者に人気ですが、非常に切れやすく扱いがシビアです。まずはトラブルが少ないPEから始めることをおすすめします 。
もし「ラインシステムなんて難しそう…」と感じる方は、フロロカーボンの通し(直結)ラインで始める方法もあります。4lb前後のフロロラインをリールに直接巻いて使えば、ノットを組む必要はありません。フロロラインは沈みやすいためレンジキープがしやすく、根ズレにも強いというメリットがあります。ただしPEと比べると太さの分飛距離が落ち、伸びがあるため感度も劣ります。まずはPE+リーダーに挑戦してみて、どうしても難しければフロロ直結で再スタートするくらいの気持ちで良いでしょう。最近はメーカーから初心者向けにあらかじめ糸付きのリールやセット商品も出ていますので、釣具店で相談してみるのも手です。
アジング用・メバリング用ルアーの違い
ライトゲームで使用するルアーの主役はソフトルアー(ワーム)です。小さなゴカイや小魚に似せた柔らかいプラスチック製の疑似餌で、これをジグヘッド(鉛のおもり付きフック)に刺して使います。実はアジング用とメバリング用ではワームの設計コンセプトが微妙に異なり、これを知ると釣果アップに繋がります。
アジング用ワームは総じて非常に柔らかく細身に作られています 。アジは口が小さく吸い込みバイト(吸い込んで捕食)をする魚なので、柔らかくて抵抗の少ないワームほど違和感なく吸い込み、フッキングしやすいからです 。例えばストレート系やピンテール系と呼ばれる細長いワームが典型で、サイズも1.5〜2インチ程度の小ぶりなものが主流です。カラーはプランクトンを模したクリアや夜光(グロー)系が人気で、夜間は白やピンク、オレンジなど明滅しやすい色が定番です。
一方、メバリング用ワームはアジ用ほど極端に柔らかくなく、適度な張り(硬さ)を持たせたものが多いです 。メバルはアジに比べて口が大きく、エビや小魚を一気に丸呑みする捕食をします。そのためワームにある程度コシがあっても問題なく吸い込め、むしろただ巻き(一定速度の巻き)で安定した泳ぎを出すために少し硬めに設計されているケースが多いのです 。形状も多彩で、尾にヒレ状のパドルが付いた「シャッドテール型」や、くるくる回る「カーリーテール型」など、アクションでアピールするデザインがよく使われます。カラーはアジ用と共通するものも多いですが、メバル狙いでは**シルエットをはっきり見せるため濃い色(黒や茶)**が効く場面もあります。
また、ジグヘッドにも違いがあります。アジング用ジグヘッドはフックが細軸で小さめ、ヘッド形状もダートしやすいもの(尖った形など)が多いです 。一方メバリング用はフックがやや太軸で大きめ、ヘッドもゆっくり沈めるための丸形などが主流です。これは狙う魚の口の硬さや釣り方の違いによるものです(アジは軟らかい口を確実に貫通させるため細いフック、メバルは根に潜られないよう多少強引に寄せられる太いフック等)。ただ初心者のうちはあまり深く考えず、まずは扱いやすい形状・重量のジグヘッドを選ぶと良いでしょう。
まとめると、アジング=柔らか細身ワーム×小型ジグヘッド、メバリング=少し厚みのあるワーム×安定したジグヘッドが基本形になります。ただ、実際には互いに流用可能な部分も多く、「アジング中にメバルが釣れた」「メバリング中にアジが掛かった」なんてことも日常茶飯事です。あまり難しく考えすぎず、まずは手持ちのワームで両方狙ってみて、反応を見ながら専用タイプを試すくらいの感覚でOKです。
初心者におすすめのワーム&ジグヘッドセット
ライトゲーム初心者が最初に用意するルアーとしては、オールマイティに使える定番ワーム&ジグヘッドがおすすめです。具体的には、長さ1.5〜2インチ程度のストレート系ワームと、重さ1g前後のジグヘッドの組み合わせが一セットあるとよいでしょう。色は夜釣りで実績の高い白(パールホワイト)やピンク、クリアにラメ入りなどを揃えておけば間違いありません。例えば「夜光ホワイトの2インチワーム+1gジグヘッド」はアジ・メバル両方に実績抜群の組み合わせです。常夜灯下の明るい場所ではクリア系、暗い場所ではグロー系と使い分けても効果的です。
ジグヘッドの重さは、ポイントの水深や風の強さで調整します。港内で風も弱い日は0.6〜0.8gなど軽めでふわっと落とすと喰いが良く、少し波っ気や風がある時や水深がある場所では1.2〜1.5gにアップして沈下速度を稼ぎます。基本は1g前後から始めて、反応がなければ軽く、届かなければ重く、と現場で変えてみましょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、この重さの使い分けがライトゲームの醍醐味でもあります。
最近は釣具店に「ライトゲーム用スターターキット」のような形で、人気ワーム数種とお勧めジグヘッドがセットになった商品も売られています。どれを選んでいいかわからない場合、そうしたセットを購入するのも一案です。慣れてきたらメタルジグや小型プラグ(小さいミノーやシンキングペンシル)にも挑戦してみましょう。特に活性が上がる秋には小さなメタルジグでアジを狙ったり、表層でメバルがライズしているときに小型トップウォータープラグで狙うなど、バリエーションが広がります。ただまずはワーム+ジグヘッドの基本セットで確実に釣果を出し、自信を付けることをおすすめします。
釣果アップのためのアクションと誘い方
アジやメバルは繊細な魚。動かし方ひとつで釣果が変わります。ここではルアーのアクションの基本と、実際に釣れる誘い方を紹介します。ただ巻きひとつにしてもスピードで明暗が分かれ、アクションを加えるタイミングでも魚の反応が激変します。魚の気持ちになってルアーを演出するつもりで、ぜひ色々な誘い方にチャレンジしてみてください。
アジングの基本アクション
アジングで頻出するテクニックがリフト&フォールです。文字通りルアー(ジグヘッド+ワーム)を持ち上げて落とす動作で、具体的にはロッドを小刻みに上下させてワームをヒラヒラと跳ね上げ、フッと力を抜いて沈下させる動きを指します。アジはエサが不規則に動いたあとフワッと落ちる瞬間に思わずバイトする習性があるため、リフト&フォールは非常に有効な誘い方です。やり方は簡単で、まずキャストして狙いたいレンジまで沈めたら(例えば中層なら5秒カウント沈める等)、「チョンチョンチョン」とロッドを小さく煽ってワームを持ち上げます 。するとワームが数十センチ急上昇した後、ロッドを止めるとまたヒラヒラと落ちていきます。このフォール中(落下中)にアジが食ってくることが多いので、ラインの変化に注意しながらアタリがあればすかさず合わせます。
もう一つ基本となるのはトゥイッチ&ただ巻きです。トゥイッチとはロッドを小刻みに震わせてルアーに細かいダート(左右への動き)を与えるアクション。アジングでは、スローにただ巻き(一定速度巻き)している最中に「チョンチョン」と軽くロッドを動かしてルアーに変化を付けるような使い方をします。これによりワームが弱った小魚のようにヒラつき、追っていたアジに捕食スイッチを入れる効果があります。アジは群れでいるとき、ルアーへの追尾はするもののなかなか食いきらないことがありますが、最後の一押しでトゥイッチを入れると途端にヒットに持ち込めることがあるのです。
もちろんただ巻き(ストレートリトリーブ)だけで釣れる場面も多々あります。特に活性が高いときは余計なアクションは不要で、一定の速度で巻くだけで次々ヒットします。「まずはただ巻きで探り、反応がなければリフト&フォール、さらに渋ければトゥイッチ混じりの巻き」と段階的に試すと効率的です 。アジングはパターンを見つける釣りとも言われます。ヒットが出たアクションやレンジを再現し、連発に持ち込めばしめたもの。逆にアタリが遠のいたら別の誘い方に切り替えて、新たなパターンを探ることを繰り返しましょう。
メバリングの誘い方
メバリングではできるだけゆっくり誘うことが基本になります。メバルは警戒心が強く、急な動きよりもナチュラルな動きに反応しやすいためです 。まず試したいのが**スローリトリーブ(超ゆっくりのただ巻き)**です。ルアーがギリギリ泳ぐかどうかの速度で巻いてくると、メバルがふわっと後を追い、パクッと食わえてくることがあります。ポイントによって適切なレンジは異なりますが、常夜灯周りなら表層〜中層、テトラ帯なら中層〜ボトム付近など、魚のいそうな層を想像しながらゆっくりルアーを引いてみましょう。暗闇の中、ラインに「コツン」と重みが伝わったらメバルのアタリです。
誘いのバリエーションとしては、ストップ&ゴーも有効です。一定のスロー巻きの途中で一瞬巻くのを止めます。ワームがふわっと漂うように沈む間にメバルが食うイメージです。止める時間は1〜2秒で充分で、あまり長く止めすぎると根掛かりの原因にもなるので注意しましょう。これは一種のリフト&フォールに近いですが、アジングほど大きな動きは必要ありません。メバルはエサに対してじっくり間をとってから食いつくことも多いので、「間(ま)を与える」誘いが効果的なのです。
もう一つ覚えておきたいのはレンジキープです。メバルは群れで定位していることがあり、ある特定の深さでポンポン当たることがあります。ヒットレンジを掴んだら、その層をキープするよう工夫しましょう。具体的にはキャスト後カウントダウン(ルアーを沈める秒数を数える)して狙いのレンジまで沈め、あとはロッドの角度や巻き速度でなるべく同じ深さを泳がせます。浮き釣りのようにウキ(フロートリグ)を使って一定の深さを狙う手もありますが、初心者には少し難しいので、まずはカウントで調整する方法で十分です。逆に表層近くでメバルがライズしている場合などは、あえて沈めずすぐ巻き始めて表層を引くのも手です。臨機応変に魚の動きに合わせたレンジとスピードを見つけましょう。
潮・風・ベイトを読んだ釣り方の工夫
さらに釣果を伸ばすには、**その日の潮・風・ベイト(餌となる小魚やエビ)**の状況を読むことが重要です。ただ闇雲にキャストするのではなく、自然の要素を味方につけましょう。
まず潮(流れ)です。淡路島のように潮流がある釣り場では、魚は基本的に潮上(しおかみ:流れに向かって頭を向ける)に泳いでいます。従って、潮の流れに対して上流側にキャストし下流へ流すようにルアーを通すと魚に違和感なくアプローチできます。いわゆるドリフト(流し)釣法で、流れに乗せて自然にルアーを漂わせるイメージです。特にメバルは潮通しの良い岬や堤防先端が好きなので、潮上にキャスト→潮に乗せて誘う、を意識してみてください。逆に流れが効いていないタイミング(いわゆる潮止まり)は魚の活性も下がりがちなので、潮が動き出すのを待つか思い切ってポイント移動するのも一つの判断です 。
次に風です。夜の港は風向きで釣りやすさが大きく変わります。向かい風が強いと軽量ルアーでは飛距離が出ず思ったポイントに届きません。またラインが煽られてアタリも取りづらくなります。そういうときはジグヘッドの重量を普段より上げる(例えば0.8g→1.5gにUP)、もしくはフロートリグ(遠投ウキ)を付けて飛距離を稼ぐといった対策が有効です。どうしても厳しい場合は無理をせず、風裏になるポイントへ移動することも検討しましょう。淡路島は地形がある程度複雑なので、同じ南あわじ市内でも風裏になる湾奥の漁港があったりします。天気アプリなどで風向きをチェックし、その風を背中から受けられる場所を選べばキャストも楽になります。
そしてベイト(餌生物)の存在も見逃せません。常夜灯下をのぞいて小魚が群れていたり、水面にナミナミとプランクトンが沸いていたりすることがあります。そういう場合はそのベイトに合わせたパターンがハマることが多いです。小魚がたくさんいるならサイズ感を合わせて少し大きめのワームにしてみる、プランクトンパターン(極小のエサ)なら1インチ級の極小ワームやクリアカラーでアピールを抑える、といった具合です 。実際、春先にアミ(プランクトン)が大発生する時期は、アジがアミに夢中になって大型ワームに反応しづらくなることがあります 。そんな時は思い切ってただ巻きの超スロー引きでアミを演出したり、逆に動きのあるプラグでリアクションバイトを誘ったりと工夫が必要です 。
最後に、大型捕食者の存在も釣果に影響します。先述したタチウオの例 がまさにそうですが、他にもシーバス(スズキ)や青物が回ってくると小魚やアジが散ってしまうことがあります。その場合は場所や時間をずらすしかないので、「今は自分が狙う魚の活性が低いな」と判断したら深追いせず切り替えましょう。釣りは自然相手ですから、状況判断と柔軟な対応が何より大切です。潮の流れを読み、風を味方にし、ベイトや周囲の気配にアンテナを張っていれば、必ずや釣果アップという形で応えてくれるでしょう。
釣りをもっと楽しむためのコツと注意点
淡路島でのナイトゲームを快適に楽しむには、安全とマナーも大切。初心者が気をつけるべきポイントを紹介します。せっかく釣りを楽しむなら、トラブルなく笑顔で帰りたいものです。ライフジャケットなどの安全装備の準備、釣り場での立ち居振る舞い、そして釣り人として守るべきマナーを改めて確認しておきましょう。基本的なことですが、これらを徹底することが釣果以上に大事です。
ライトゲームの安全装備
夜釣りには安全装備が欠かせません。まず必須なのが**ヘッドライト(ヘッドランプ)**です。暗い夜の釣り場で手元を照らす明かりがないと、仕掛け交換もままなりませんし、足元の確認もできず非常に危険です。両手が使えるようにおでこに装着するヘッドライトを用意しましょう。最近は明るさ調整機能や赤色灯モード(魚が驚きにくい)が付いたものもあります。周囲に他の釣り人がいるときは、直接相手の目にライトを向けない配慮も忘れずに。
そしてライフジャケット(救命胴衣)は命綱です。堤防とはいえ海辺に立つ以上、万一の転落に備えて必ず着用しましょう 。特に夜間は足場を踏み外すリスクが高く、暗い海に落ちてしまうと泳ぎに自信があってもパニックになる可能性があります。実際、「ちょっとだから」と着けなかった釣り人が足を滑らせて…という事故例も少なくありません。国土交通省認定の桜マーク付きライフジャケットなら信頼性も高いですし、膨張式のモデルなら動きの邪魔にもなりません。迷わず付ける、それが大前提と覚えておきましょう。
そのほか、滑りにくい靴(スパイクブーツやフェルトソール)も用意できれば万全です。テトラポッド上や苔の生えた堤防は非常に滑りやすいので、靴底のグリップ力で安全性が段違いに変わります。また、夜は気温が下がるため防寒着も重要です。夏でも海風に当たると意外と冷えることがありますし、冬ならなおさら厚着が必要です。動きやすさとの兼ね合いもありますが、防風性のあるアウターや手袋・ニット帽などでしっかり防寒しましょう。寒さを我慢して釣りをしていると思わぬケガや判断ミスにも繋がりかねません。
最後に、携帯電話は防水ケースに入れ首から下げておくと安心です。万一転落した際にすぐ助けを呼べますし、釣り場によっては街灯もなく真っ暗になる場所もあるので、ライト代わりやGPSでの位置確認にも役立ちます。ライトゲームは手軽とはいえ自然相手のレジャーですから、備えあれば憂いなしの精神で安全装備を整えてください。
立ち位置とキャスト時の注意点
夜釣りでは自分の行動が思わぬ事故を招くことがあります。特に立ち位置やキャスト時の注意はしっかり持ちましょう。
まず、釣り座(立ち位置)は足場の安定した場所を選んでください。堤防の先端は釣れそうに思えますが、狭かったり柵がなかったりする場合があります。初心者はできるだけ柵がある場所や広いスペースで釣りましょう。また、同じ堤防で釣り人が複数いる場合はお互い十分な距離を取ることが大切です。暗い中ではキャストのタイミングや方向が見えづらく、近すぎるとオマツリ(お互いの仕掛けが絡まる)や、最悪相手にルアーを引っ掛けてしまう危険もあります。最低でも横に2〜3m、斜め前には人がいない状態を確保し、狭い場所では順番に投げ合うなど譲り合いましょう。
キャスト(投げ動作)時は、後方と周囲の安全確認を必ず行います。後ろに人が立っていないか、荷物が置いていないか、夜だと見落としがちです。とくに堤防は散歩中の人がいたり、後ろに自分のクーラーボックスがあったりします。バックキャストしたときにフックが引っ掛かる事故が起きないよう、投げる前に「後ろ良し!横良し!」と確認するクセをつけましょう。仲間同士で釣行しているなら、「投げまーす」と一声かけるのもアリです。
釣りをしている最中も、自分の立ち位置を時々見直してください。満潮に向かって潮位が上がると、いつの間にか立ち位置が波を被る高さになっていた…なんてこともあります。また、夜は潮位感覚が掴みにくいので、予想以上に水が迫っていることがあります。テトラの上なら、帰り道のルートを見失わないようライトで都度確認しつつ行動しましょう。焦らずゆっくり移動し、絶対に跳んだり走ったりしないことです。暗闇では距離感も狂いやすいので、一歩一歩を確実に。
最後に、仕掛けを回収する際も注意です。夜釣りでは、絡んだラインを解こうとして後ろ向きに歩き、足を踏み外すケースがあります。ライントラブル時は無理な姿勢を取らず、一旦安全な場所に移動してライトでよく見ながら処理しましょう。どんなときも「自分の足元半径1m」を意識し、安全マージンを取った行動をすることが大切です。
釣り人としてのマナーとゴミ持ち帰りの意識
釣りを楽しむ者として、マナー遵守は絶対条件です。まず何より、ゴミは必ず持ち帰りましょう。使用済みのワームのパッケージ、ラインの切れ端、飲食物の容器など、釣り場に一切のゴミを残さないことが基本中の基本です 。可能であれば「来た時よりも美しく」を心がけ、周辺に落ちている他人のゴミも拾って帰るくらいの意識が望ましいでしょう 。淡路島の美しい海岸線を守るためにも、一人一人が徹底する必要があります。
また騒音問題にも配慮が必要です。夜釣りの際、興奮して大声で話したり音楽を大音量で流したりすると、静かな夜に響き渡り近隣住民の迷惑になります 。港は音が反響しやすく、少しの声でも遠くの民家に届くことがあります。特に深夜は静かに、会話も必要最低限の音量で楽しみましょう。車のドアの開閉音やエンジン音にも気を使い、長時間アイドリングなどは避けるべきです。
さらに、地元の漁業関係者へのリスペクトも忘れずに。漁港はあくまで仕事場であり、釣り人は場所をお借りしている立場です。漁船や養殖いかだ付近では絶対に仕掛けを投げ込まない、作業の邪魔になる場所には立たないようにしましょう 。朝方に漁師さんが出船する時間帯には速やかに道を譲り、挨拶もきちんと交わすといったコミュニケーションも大切です。そうした小さな積み重ねが地元の理解に繋がり、釣り場が末永く開放されることに直結します。
そして前述の通り、釣り禁止区域には絶対に立ち入らないこと 。一人が破れば「あそこは釣り人がマナーを守らない」となり、他の釣り場まで閉鎖される悪循環を招きます。暗黙の了解で「ここは夜○時まで」など地元ルールがある場合も、先行者に確認したりして従いましょう。釣り人のマナーの良さは自分たちで示すしかありません。幸い淡路島の多くの釣り場は好意で開放されており、マナーを守っている限り楽しむことができます。この恵まれた環境を壊さないよう、一人一人が釣り人の自覚を持って行動しましょう。
釣った魚を美味しく食べよう!簡単レシピ紹介
アジやメバルは、釣っても食べても最高のターゲット!釣りたてを楽しむ簡単レシピを紹介します。新鮮な魚はシンプルな料理でも驚くほど美味しく、釣果が食卓に並ぶ喜びは格別です。ここではアジとメバルそれぞれの定番料理をいくつかピックアップ。釣り初心者でも挑戦しやすいものばかりなので、ぜひ調理にもチャレンジしてみてください。美味しくいただくための持ち帰り方法も合わせて解説します。
アジの南蛮漬け・刺身・フライ
アジ(マアジ)は日本人に馴染み深い大衆魚で、料理のバリエーションも豊富です。ライトゲームで釣れるサイズのアジなら、まずおすすめしたいのが南蛮漬け。小〜中型アジ(10〜20cm程度)を開いて唐揚げにし、熱々のうちに甘酢タレに漬け込む料理です。玉ねぎや人参と一緒に漬ければ彩りも良く、骨まで丸ごと食べられるのでカルシウムもたっぷり。釣れたその日に調理すれば、翌日には味がしみ込んで絶品のおかずになります。揚げ物はちょっとハードルが…という方も、小アジなら片栗粉をまぶして油で揚げるだけと簡単なのでぜひ挑戦してみてください。
新鮮な中〜大型アジが手に入ったら、やはり刺身(お造り)は外せません。透き通った身は美しく、釣り人だけの特権とも言える味わいです。アジは傷みが早い魚ですが、釣ってすぐに氷締めした個体なら生食も可能です 。三枚におろして皮を引き、お好みで薄造りや叩きにしましょう。薬味は生姜やニンニク醤油がアジの甘みによく合います。自分で釣った魚を刺身にして食べる瞬間は感動ものですよ。ただし刺身にするなら鮮度管理は特に徹底し、傷んだものは加熱調理に回すなど無理のない範囲で味わってください。
そして忘れてならないのがアジフライです。言わずと知れたソウルフードですが、釣りたてのアジで作るアジフライは別次元の美味しさ。20cm前後のアジを開いてパン粉を付け、カラッと揚げれば外サク中ふわでたまりません。タルタルソースをかけても良し、醤油を垂らして白ご飯と頬張るも良し。多めに釣れたときは下処理だけして冷凍保存し、食べたいときに解凍してフライにすれば長く楽しめます。アジは和・洋・中どんな味付けにも合う万能選手なので、南蛮漬けや刺身・フライ以外にも、アジのなめろう(味噌叩き)やアジの梅煮などぜひレパートリーを増やしてみてください。
メバルの煮付け・塩焼き・唐揚げ
メバル(対象は主に黒メバル・金メバルなど)は、その姿からも想像できる通り身に甘みがあり、古くから煮魚の王様として親しまれてきました。釣れたてのメバルを手に入れたら、まずぜひ試してほしいのが煮付け(煮魚)です。下処理はウロコを落として内臓を出すだけとシンプル。鍋に醤油・砂糖・みりん・酒・水・生姜を入れて煮立たせ、メバルを投入して落とし蓋をしてコトコト煮るだけでOK。身がほろりと崩れる頃合いが食べ頃です。メバルの煮付けは身から出る旨味とコラーゲンたっぷりのゼラチン質がたまりません。煮汁をご飯にかけて食べると何杯でもイケる美味しさです。
次に簡単なのが塩焼き。こちらも下処理後、塩を振ってしばらく置き、水分が出たら軽く拭いてから遠火の弱火でじっくり焼くだけ。皮がこんがり焼けて、香ばしい香りが立ったら出来上がりです。メバルは適度に脂が乗っているのでシンプルな塩焼きで素材の味を楽しめます。はらわた(内臓)は少々苦味がありますが、好きな人はそのまま残して焼いても通好みの味になります。焼き魚にできるほどのサイズが釣れたこと自体がご褒美ですから、レモンや大根おろしを添えてじっくり味わいましょう。
小ぶりのメバルが複数釣れた場合は**唐揚げ(からあげ)**もおすすめです。これはアジと同様、下処理をしたメバルを素揚げする調理法。醤油・酒・ニンニク・生姜で下味を付けて片栗粉をまぶし、カラリと二度揚げすれば骨までサクサク食べられます。メバルはヒレが鋭いので、調理前にハサミで背ビレ・腹ビレを切り落としておくと食べやすいです。唐揚げにするとメバル特有の上品な旨味がギュッと凝縮され、ビールのお供にも最高の一品になります。
他にも、メバルはアクアパッツァ(イタリア風煮込み)や潮汁(うしおじる:あらで出汁を取った汁物)にしても美味しい魚です。洋風にも和風にもアレンジが利くので、釣って楽しい・食べて美味しい喜びを存分に享受してください。
持ち帰り時の鮮度キープ術
釣った魚を美味しく食べるには、鮮度管理が肝心です。釣った直後の処理で味が大きく左右されると言っても過言ではありません。ここでは簡単にできる鮮度キープのコツを押さえておきましょう。
まず、アジでもメバルでも**釣れたらすぐ締める(絞める)のが理想です。具体的には、釣れた魚のエラぶた辺りにナイフやキリを刺して脳を破壊(脳締め)し、エラを切って血抜きをします 。難しければエラにナイフを入れてしばらく海水に浸けるだけでも血抜き効果があります。血が抜けたらすぐに氷水に入れて急速に冷やす(氷締め)**のがポイントです 。海水と氷をクーラーボックスに入れて即席の氷海水を作り、その中に魚を入れると短時間でキンと冷えます。真水は魚にダメージを与えるので使わないようにしましょう 。小型魚ならこれで十分ですが、可能なら内臓も早めに取り除いておくとさらに鮮度が保てます(特に夏場は内臓腐敗が早いため現地でワタ抜き推奨です)。
クーラーボックスは必携で、氷は多めに持っていくようにします。発泡スチロールの簡易クーラーでも良いので、とにかく釣れた魚は常に冷やしておくこと。暑い時期はクーラーに日光が当たらないようタオルをかけるなど工夫しましょう 。帰宅後も、すぐに捌かない場合は魚体を新聞紙やキッチンペーパーで包み、冷蔵庫で保管すると余分な水分が抜けて鮮度が維持できます 。ただし基本的には「釣ったその日に処理、できれば調理」が一番です。特に刺身狙いの魚は釣行当日中に捌いておくのがベターでしょう。
もし釣り場が遠方で長時間持ち歩く場合などは、簡易的でもエアポンプ付きの生け簀バッカンに活かしておく手もあります。ただし夏場は水温上昇ですぐ弱ってしまうので氷投入が必要だったりと手間がかかります。氷締め→クーラー保管が最も確実です。以上の点を心がければ、釣果を最高の状態で持ち帰れます。自分で釣った魚を美味しくいただくためにも、鮮度管理までが釣りだと思って丁寧に扱ってください。
まとめ
この記事では、淡路島で楽しむライトゲーム(アジング&メバリング)の魅力と実践ポイントを紹介しました。
✅ 春〜秋はアジ、冬はメバルが主役! 各季節で狙い目の魚種が異なり、春〜秋は回遊するアジが釣りやすく、冬場は大型メバルの好機です。それぞれのベストシーズンを押さえることで効率よく釣果アップが期待できます 。特に夕マズメから夜にかけてが狙い目で、アジ・メバルとも活発にエサを追います 。季節と時間帯を味方につけましょう。
✅ 常夜灯周りが初心者でも釣りやすい ポイントです。淡路島の漁港は常夜灯のある場所が多く、明暗の境目に魚が集まります 。明かりがあると安全面でも安心なので、初めての夜釣りはまず常夜灯ポイントから攻めてみてください。堤防や港内の安全柵がある場所ならファミリーでも安心して竿を出せます。
✅ 軽いタックルで気軽に夜釣りを満喫 できるのがライトゲームの醍醐味。専用ロッドでなくても7ft前後のルアーロッドとスピニングリールがあればOKで、仕掛けもシンプルなワーム+ジグヘッドだけで始められます。軽量タックルなら小さなアタリもダイレクトに感じられ、釣れた魚は料理で美味しくいただけるという二重の喜びがあります。淡路島という最高のフィールドで、ぜひライトゲームの世界を堪能してください。
この記事を参考にすれば、あなたも淡路島の夜釣りライトゲームを安心して実践できるはずです。次の週末は、ぜひ淡路島でナイトゲームデビューを!ライトな仕掛けで、あなたも“夜の一匹”を味わってみてください 。きっとその手に伝わる小さな大物との出会いが、アウトドアライフをさらに豊かにしてくれることでしょう。楽しみながら、安全第一で、素敵な釣りの時間をお過ごしください!


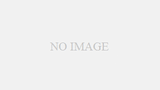
コメント