「ロックフィッシュって難しそう…」「アコウ(キジハタ)は高級魚って聞くけど初心者でも釣れるの?」 そんな疑問を持つ方も多いでしょう。実は、秋はアコウ釣りのベストシーズン! しかも堤防からでも十分狙えるんです。本記事では、アコウの生態や釣れる時期・時間帯、必要なタックルやルアー、関西のおすすめ堤防ポイントまで徹底解説します。初めてのロックフィッシュ挑戦でも釣果を狙える「最強メソッド」をお届けします!
秋はアコウ釣りのベストシーズン!その理由とは?
秋はアコウ(キジハタ)釣りの絶好シーズンといわれます。その理由を理解するために、まずアコウという魚の特徴を押さえましょう。さらに、秋がロックフィッシュゲームに向いている季節的な条件についても解説します。
アコウ(キジハタ)ってどんな魚?
アコウ(キジハタ)はハタ科に属する沿岸性の根魚で、関西では「アコウ」と呼ばれ高級魚として人気です 。最大で60cmを超える個体もいますが、岸から釣れるサイズは30cm前後が平均で、50cmを超えると“超大型”とされます 。茶褐色の体に橙色の斑点模様が特徴で、見た目の美しさから「雉羽太(キジハタ)」の和名が付きました。
アコウは強烈な引きを見せるファイターとして釣り人に人気があります。カサゴ(ガシラ)など他の根魚とは比べ物にならないパワフルなファイトを楽しめるため、「根魚の王様」と称されることもあります 。ヒット直後に岩場やテトラの隙間へ突っ込もうとする習性があり、根に潜られてラインブレイクするスリリングなやり取りが醍醐味です 。その強烈な引きと食味の良さで近年ますます人気が高まっています。
また、アコウは生息数が少なく高級魚として扱われ、市場にはあまり出回らない「幻の魚」とも呼ばれてきました 。関西や瀬戸内海では昔から珍重され、店頭に並ぶことなく高級料亭に直行するほどです 。しかし各地で稚魚の放流事業が行われるなど保護策が進み、近年は岸釣りでも狙いやすい魚になりつつあります 。初心者でも扱いやすい専用タックルが充実してきたこともあり、「高級魚だけど意外と釣れるターゲット」として注目されています 。
秋がロックフィッシュに適している理由
では、なぜ秋がアコウ釣りに適した季節なのでしょうか? それはアコウの産卵サイクルと水温に関係しています。アコウのハイシーズンは初夏と秋で、海水温が約25℃前後になる時期が活発に動くタイミングです 。初夏(梅雨時期)に産卵のため浅場に接岸し、その後の秋には産卵後の荒食い期に入るため、再び岸近くで活発にエサを追うようになります 。産卵で体力を消耗した個体が、秋にかけて餌をたくさん食べて回復しようとするためです。
また、真夏の盛り(8月頃)は水温上昇で一時的に活性が落ちる傾向がありますが、秋は水温が安定して適温になるため再び活性が上がります 。地域差はありますが、堤防からのアコウ狙いでは6月~11月がシーズンで、特に9月~10月の初秋は好機とされています 。例えば水深の浅い釣り場では、梅雨明けの6~7月と9~10月がベストシーズンとなり、盛夏の8月は水温が上がり過ぎて一旦釣果が落ちるケースもあります 。そのため、暑さが和らぎ始め小魚(ベイトフィッシュ)の群れも多くなる秋は岸近くまで良型アコウが寄りやすい時期なのです 。
さらに秋は昼夜の長さが変化し、水中のプランクトン量や小魚の動きにも変化が出る季節です。夕マズメ(夕方の薄明時間)から夜にかけてアコウの活性が上がりやすく、岸壁付近までエサを追ってくる個体も増えます。朝夕の涼しい時間帯に動きが活発になり、堤防からでも十分にチャンスがあるのが秋シーズンの魅力です。
つまり秋は、アコウが岸寄りでエサを求めて活発に動く絶好のタイミングというわけです。この機会を逃さず、ぜひ堤防からのロックフィッシュゲームに挑戦してみましょう。
まず揃えたい!アコウ狙いに必要なタックル&ルアー
初心者がアコウ(キジハタ)を狙うなら、まずは専用タックルとルアーの基本を押さえましょう。ロッド・リール選びからライン設定、そして実績の高いルアーについて解説します。適切な道具立てで臨めば、高級魚アコウも手の届くターゲットになります。
ロッド&リール選びの基本
アコウ釣りでは感度とパワーを兼ね備えたロッドと、強力なリールが欠かせません。根魚ゆえ岩礁帯でのゴツゴツした感触を捉える必要があり、さらにヒット後は根に潜られないよう一気に引き剥がすパワーも求められます。
ロッドは7.5~8フィート前後の長さでMH(ミディアムヘビー)クラスが扱いやすいでしょう 。7~8ft程度であれば堤防足元のポイントから少し遠投したい場合まで対応でき、取り回しも良好です 。初心者であればまずこの長さ・硬さを目安に選ぶとよいです。もちろん足場が高い堤防やより遠くを探るシーンでは9ft前後のロッドも有効ですが、まずは8ft前後のMHロッドがオールラウンドに使えます 。ロッドパワーは硬め(ファストテーパー~スローテーパーの硬め)で、底質の変化や僅かなバイトも感じ取れる高感度なものが理想です 。
リールは2500番~3000番クラスのスピニングリールが一般的で使いやすいです(ベイトリールでもOKですが初心者にはスピニング推奨) 。ドラグ性能が優れ、巻き取り力の強いモデルを選びましょう。特にアコウは根に向かって強烈に引くため、パワーのある高ドラグ力のリールが望ましいです 。ドラグはファイト中に滑りすぎないようやや強めに設定できるものが良く、最近の中型スピニングリールなら実用ドラグ5kg以上の機種も多いので安心です。ハイギアタイプ(巻き取り速度が速い)だと根に突っ込まれた際のリカバリーが早く、手返し良く探るのにも向いています 。
💡 豆知識:エギングロッドで代用可?
実は30cm級までの中小型アコウがターゲットなら、イカ釣り用のエギングロッド(Mクラス)+2500番スピニングといったライトタックルでも十分釣りが可能です 。エギングロッドは感度が高く根魚のアタリも取りやすいため、まず手持ちのタックルで試したい場合は代用してみても良いでしょう。ただし大型狙いや根の荒いポイントではやはり専用タックル(MH以上)が安心です。
ライン&リーダーのセッティング
根魚狙いではラインシステムも重要です。メインラインには**PEラインの1.0号前後(強度約20lb前後)**がおすすめ 。PEラインは引っ張り強度が高く伸びが少ないため、アコウの微かなアタリも逃さず捉えられます 。一方でPEは根ズレ(岩との摩擦)に弱いので、先端にショックリーダーを必ず結びましょう 。
リーダーには**フロロカーボンの16~20lb(4~5号程度)を1ヒロ(1.5m前後)ほど取ります 。フロロは摩擦に強く岩に擦れても切れにくいため、根の多いポイントでの安心感が段違いです 。特に大型アコウとのファイトや、鋭いテトラや貝殻に触れるリスクを考えると太めのリーダーが保険になります。強引に根から引き剥がすためにもリーダーは太め設定(16~25lb)**が基本です 。実際、根掛かりや魚に潜られた際にリーダーが擦れてボロボロになることも珍しくありません。
ラインシステムはPEとリーダーの結束(ノット)が肝心です。FGノットなど信頼性の高いノットでしっかり繋ぎ、キャスト時にすっぽ抜けたりファイト中に切れたりしないよう丁寧に組んでおきましょう。根に潜られにくい操作性を重視して、普段ライトゲームよりワンランク太めのラインを使うのがアコウ攻略のコツです 。
おすすめルアー|ワーム&ジグヘッド系
アコウ狙いのルアーフィッシングではソフトルアー(ワーム)が定番です 。中でも実績が高いのはエビやカニなど甲殻類を模したホッグ系ワームや、小魚を模したシャッド系ワームです。それぞれ3~4インチ程度のサイズを用意しましょう。甲殻類系(クローワームやホッグワーム)はアコウの大好物で、ボトム付近を狙う釣りで抜群の釣果を誇ります 。シャッドテール系ワームも小魚に似せたシルエットとテールの振動でアピールでき、有効です。カサゴ狙い用ワームより一回り大きめ(3インチ以上)を使うと良型アコウに効果的です。
リグ(仕掛け)は根掛かり回避能力が高いテキサスリグやフリーリグがおすすめです 。オフセットフック(#1~2/0程度)に10~20g前後のシンカーを組み合わせ、根周りを丁寧に探れます。シンカー重量はポイントの水深や潮流に合わせますが、できるだけ軽めで底を取れる範囲にするのがコツです 。例えば水深5~10m程度なら10~14g、もう少し深ければ18~21gといった具合です。軽いシンカーはフォール(落下)がゆっくりになるため喰い込みが良く、根掛かりも減ります 。ただし軽すぎると底が分からなくなるので、**「ギリギリ底が取れる最小の重さ」**を選びましょう 。
テキサスリグはシンカー先行で着底感が明確、かつオフセットフックで**障害物をかわしやすい(ウィードレス効果)**のが強みです 。フリーリグもシンカーがラインを自由に移動することでナチュラルに誘え、甲殻類ワームなどとの相性が良いです。ジグヘッドリグも有効で、10~14g程度のジグヘッドにワームを付けてボトムをズル引きしたりリフト&フォールで誘います。ジグヘッドはシンプルな分扱いやすく、根掛かりも意外と回避してくれるため初心者にも使いやすいでしょう 。
ルアーカラーは状況に応じて使い分けます。定番はブラウンやオレンジ、レッド系など底棲エビ・カニに近いナチュラル色です。特に赤系は昔からロックフィッシュに実績があり、濁りや深場でも目立ちます 。アコウにはクリアレッド系も効きやすいとされ、透明感のある赤色はベイトフィッシュを捕食する習性の表れとも言われます 。水質がクリアな日中はグリーンパンプキンやウォーターメロンなど地味目のカラーが警戒されにくく効果的です 。一方、水質が濁っている時や夜間はチャートリュース(黄緑)やグロー(夜光)など明るく発光するカラーがアピール力を発揮します。例えば夜釣りではグロー系ホワイトやパールピンクが定番です 。
💡 ワーム以外では?
アコウはハードルアー(バイブレーションやミノー)でも釣れないことはありませんが、根掛かりが多発するため初心者にはあまりおすすめできません 。まずは安価で根掛かりしても諦めのつくワーム+シンカーで攻めるのが賢明です。慣れてきたらメタルジグやトッププラグで狙う上級テクニックもありますが、基本的にはワームが最強メソッドと言えるでしょう。
アコウを引き出す!効果的なアクションと狙い方
道具が揃ったら、次はアコウをバイトさせるためのアクションとポイントの攻め方です。根魚特有の習性を踏まえ、狙いの「的」を外さない攻め方を身につけましょう。ここでは、根回りの攻略法、基本的なルアーアクション、そしてヒット後のアワセ・ファイトのコツを解説します。
根回りをしっかり攻めるのが基本
アコウ釣りにおいて最も重要なのは、障害物周り(根周り)を丁寧に攻めることです。アコウは岩礁やテトラポッド帯の穴・隙間に潜んで獲物を待ち伏せる習性があります。日中は岩陰やテトラの穴でじっとしていることが多く、簡単にはその場を離れません 。したがって、まず「魚が居着いていそうな場所」を見極め、そこにルアーを届けることが肝心です。
堤防では足元に敷石が入っていたり、消波ブロック(テトラ)が積まれていたりします。そうした変化のある場所こそ一級ポイントです。テトラ帯や岩場のエッジ、捨て石が沈んでいるエリア、桟橋の脚周り、係留船の下など、アコウが身を潜めやすいストラクチャーを重点的に狙いましょう。たとえばテトラ帯では、テトラブロックの隙間にワームを落とし込む「穴釣り」的な攻めも有効です 。実際、大阪湾岸の樽井漁港でもテトラの穴釣りで30cm級のアコウが上がった例があります 。怖がって障害物から離れた場所ばかり狙っていると、肝心のアコウにアピールできません。根掛かりを恐れず、ポイントの真芯にルアーを送り込むくらいの気持ちで攻めましょう。
攻め方のコツは、一点に固執せず角度やレンジを変えて探ることです。同じテトラ際でも、立ち位置を変えて斜めから入れる、少し沖にキャストしてから手前まで引いてくる、ボトムだけでなく中層まで誘ってみる等、アプローチを多彩にしましょう。根周りの複雑な地形ではわずかなコースの違いでヒットに繋がる場合があります。根にタイトに付いている個体を引き出すには「ルアーを目の前に通す」必要があるため、ピンポイントかつ繰り返しの攻撃が奏功します。
📝 メモ:魚影が薄い場合は移動も大切
アコウは基本的に縄張りから大きく動かない居着き魚ですが、場所によって個体数密度が全然違います。いくら攻めても反応がなければ魚影が薄い可能性もあります。その場合は思い切ってポイント移動(ランガン)し、別のストラクチャーを探ることも必要です。ただし一つ一つのポイントはじっくり探るのが鉄則。ランガンするにしても「狙いを絞った移動」を心掛けましょう。
アクションの基本|スローなズル引き&リフト&フォール
アコウを誘うルアーアクションの基本は、**スローな「ズル引き」と「リフト&フォール」**の組み合わせです 。これはロックフィッシュゲーム全般で定番の動かし方で、特にアコウには有効とされています。
ズル引きとは、文字通りルアーを底を引きずるようにゆっくり動かす手法です 。具体的にはキャスト後にワームを着底させ、ロッドをゆっくり引いて海底を這わせるように移動させます。2~3m引いたら動きを止め、再び数秒ステイ(静止)させます。海底の起伏を感じながら、この「引いては止める」を繰り返すことで、エビやカニが岩場を歩いているようなナチュラルな動きを演出できます。アコウは活発な時でも餌を追い回す距離は短いので、このように目の前をチョロチョロ動く獲物に対して食いつくことが多いです。
ズル引き中に違和感(モソッと重くなる等)を感じたら一呼吸おいて合わせるか、違和感がなくても数メートルに一度は軽くロッドを煽ってみましょう。これがリフト&フォールの動きになります。ロッドをサッと持ち上げてルアーを少し跳ね上げ(リフト)、その後ラインテンションを緩めてルアーを沈める(フォール)動作です 。この跳ね上げと落下によってルアーに変化を付け、リアクションバイト(思わず口を使ってしまう反射的な食いつき)を誘発します 。
特にフォール中にバイトが出ることが非常に多いのがアコウ釣りの特徴です 。ワームがフワッと落ちていく瞬間に「ゴンッ!」と重みが伝わることがよくあります。したがってフォール中もラインを注視し、少しでも動けば即アワセできるよう集中しておきましょう。「止めているときほどアタリが出る」と心得て、ステイ中やフォール中に気を抜かないことが大切です 。
基本的な誘い方の一例をまとめると:
- 着底させる – キャスト後、ルアーがボトムに着くまで糸ふけを出しながら待つ(カーブフォールで自然に沈める)。
- ズル引き – 底を感じながらリールをゆっくり1~2回転させ、ロッドで引きずるように移動。ゴツゴツとした感触や急な軽さ(根掛かり外れ)を感じ取る 。
- ステイ(ポーズ) – 数秒間ルアーを止めて様子を見る。岩陰から魚が出てくる間を作るイメージ。
- リフト – ロッドを小さく(もしくは3段シャクリで)煽ってルアーを底から浮かせる 。
- フォール – ロッドを元に戻し、ラインテンションを張りすぎないようにしながらルアーを再び落下させる(テンションフォールかフリーフォールで状況に応じて使い分け)。
- 着底したら糸ふけを巻き取る – フォール後、着底を感じたらロッドを下げながらスラックを巻き取り、再度底の状態を把握 。
- 以降、繰り返し – 再びズル引き~ステイ~リフト&フォールを繰り返し、足元まで探る。
この一連の動作で、ゆっくり誘いながら時折変化を付けることができます。スロー&ストップ、そして小さなジャンプという組み合わせが、警戒心の強いアコウにも口を使わせやすいパターンです。「エサが逃げそうで逃げない…でもちょっと目の前からフワッと消える」という状況に弱いと言われますので、フォールの瞬間でしっかり食わせるイメージです 。
なお、活性が高いときはルアーをスイミングさせて広範囲を探るのも有効です。軽めのジグヘッドに替えて中層をゆっくり泳がせたり、ミノーでテクトロ(堤防際の引き釣り)をしてみると、思わぬ良型がヒットすることもあります。ただし基本はボトム中心の釣りになりますので、まずはズル引きとリフト&フォールをマスターしてみてください 。
アワセとファイトのコツ
待望のアタリが出たら、次は確実にフッキングしキャッチする技術です。アコウ相手のアワセとファイトには、他の釣り以上にスピードとパワーが要求されます。いくつかコツを押さえておきましょう。
①アタリが来たら即アワセ!
アコウは一瞬でエサを吸い込むと同時に岩穴に逃げ込もうとします。特にテキサスリグなどでワームを丸呑みさせるパターンでも、アタリを感じたら一拍も置かずにビシッと合わせるのが基本です 。ズル引き中に「コン」という小さな当たりを感じたり、フォール中にラインがフッと止まるような違和感があれば、即座に強めのフッキング動作を取ります。遅れてしまうと、岩の隙間に逃げ込まれて根擦れでハリ外れ・ラインブレイクするリスクが跳ね上がります。**「掛けたらすぐ浮かせる」**を鉄則に、迷わず竿を煽りましょう。
②主導権を渡さず一気に引き離す
フッキングが決まった直後から、全力で魚を根から引き離すファイトに入ります 。アコウは掛かると本能的に根に潜ろうとするため、ここで躊躇すると一瞬で岩穴に持ち込まれてしまいます。ロッドを立ててグイグイ巻き取り、可能なら魚の頭をこちらに向けた状態で水深のある沖側へ誘導します。ドラグはあらかじめ強めに設定しておき、多少無理にでもリフトできるようにしておきます 。理想はヒットから数秒以内に底から離すこと。根から出てしまえばあとは落ち着いてやり取りできます。逆に底に潜られると引きずり出すのは容易ではありません。
③もし根に潜られたら…
万一、根に潜り込まれてラインが止まってしまった場合は、慌てず対処しましょう。よくある手段として、ラインテンションを一旦緩めて魚が出てくるのを待つ方法があります 。魚は身動きできない状態が続くと、自分から穴から出ようとすることがあるためです。ラインをフリーにして数十秒待ち、再びゆっくりテンションを掛けてみます。それでも動かない場合は、ロッドのバットでコンコンと叩いて刺激を与えたり、ラインを指で弾くようにして魚を驚かせるテクニックもあります 。これで運が良ければ再び動き出します。最後は根ズレでラインが傷んでいる可能性が高いので、丁寧に巻き上げて取り込みます。
④取り込みは確実に
足元まで寄せたら、抜き上げられるサイズなら一気に抜きます。迷って魚が暴れると再びテトラに潜られかねません。大型で抜き上げ困難ならタモ網を用意してすくいます。いずれにせよ、寄せてからがバタバタしないよう手順をイメージしておきましょう。
アコウとのファイトはまさに「短期決戦」。最初の突っ込みを制すれば勝利です 。ドラグ調整は強め+ロッドワークでショックを吸収し、ラインブレイクを防ぎます。根擦れでリーダーが傷んでいることも多いので、キャッチ後は早めに結び直すなどしておくと次の一匹に備えられます。
堤防でも狙える!関西のアコウ釣りおすすめポイント3選
秋のベストシーズン、関西エリアの堤防でアコウを狙うならここ!というおすすめ釣り場を3つ紹介します。いずれも実績が高く、足場も比較的良いので初心者にもトライしやすいポイントです。それぞれの特徴と狙い目を押さえておきましょう。
和歌山・加太港
和歌山市北部に位置する**加太港(加太大波止)**は、関西でも屈指の人気釣り場です。紀淡海峡(紀伊水道)に面して潮通し抜群で、多彩な魚種が狙えるポイントとして有名です 。青物から根魚まで年中釣り人が押し寄せ、アコウも例年夏~秋に実績があります。足場の良い大波止先端部はファミリーからベテランまで竿を出す人気スポットで、一級ポイントとして知られています 。
加太港でアコウを狙うなら、朝夕のマズメ時や夜間が狙い目です。夕マズメ~日没後にかけて活性が上がり、常夜灯付近に小魚が集まるとそれを追ってアコウが回遊してくることがあります 。港内の水深は浅めですが、敷石や沈み根が点在しているため足元でも意外に釣れます 。特に大波止の赤灯台周辺は水深もあり、潮の変化も出るため好ポイントです。テトラ帯の穴を丹念に探れば日中でも釣果が期待できますし、夜釣りではテトラ際を中心にルアーを通してみましょう。実績としては**ノマセ釣り(小アジの泳がせ)**でも30cm台のアコウが上がっており、堤防根魚ポイントとして確かなポテンシャルがあります。
なお、加太港は人気ゆえ混雑することも多いので、マナーを守って釣り座を確保しましょう。潮の流れが速い日もあるため、シンカーは少し重め(20g以上)も用意しておくと安心です。朝まずめの青物狙いの人たちが引き上げた後の時間帯などは比較的空いて狙いやすいでしょう。潮が緩むタイミング(潮止まり前後)はアコウが動きやすいので狙い目です 。加太大波止は有料駐車場・トイレも整備されており初心者にも優しい釣り場ですが、テトラ上は穴があって危険なので、テトラに降りる際は十分注意してください 。
兵庫・淡路島 岩屋港周辺
淡路島北端の**岩屋港(岩屋一文字含む)**は、明石海峡に面した超一級ポイントです。明石海峡大橋のすぐ脇に位置し、日本有数の好漁場だけあって魚影の濃さは折り紙付き 。特に沖堤防(岩屋一文字)は渡船利用が必要ですが、メバル・ガシラなど根魚の宝庫で、良型アコウの釣果もしばしば聞かれます。
岩屋一文字では堤防の基礎部分(ケーソン周り)を丹念に探ると、昼間でもガシラが連発するほど根魚の活性が高いです 。その延長で、強い引き込みからラインブレイクしてしまうような“化け物級”も潜んでおり、「きっと大型アコウだろう」と思わせる場面もしばしば報告されています 。まさに良型アコウが潜むロケーションと言えるでしょう。水深も十分深く、10~15mラインを中心にテトラ帯を攻めれば実績があります。テキサスリグで底を取っているとガツンと重みが乗るアタリがあり、40cm級が顔を出すことも。沖堤防だけでなく、対岸の岩屋港港内から狙っても25~30cmクラスが上がった例があります 。
狙い目の時間帯はやはり朝夕マズメ~夜です。明石海峡の激流エリアゆえ、潮止まり前後のタイミングが釣りやすく魚も動きやすいです 。常夜灯周りはチヌ(黒鯛)やメバルが多い印象ですが、アコウもベイトが溜まれば回ってきます 。日中狙うならテトラ際の穴や、堤防先端付近の沈み根周辺をじっくり探ると良いでしょう。岩屋一文字では青物やマダイもヒットする可能性があるため、ドラグはやや強め&ラインは太めで臨みます。実際、40cm近いアコウや50cm超のマハタがルアーで釣れた例もあり、何が食ってくるか分からない面白さがあります。
アクセス面では、岸からの釣りなら岩屋港の護岸エリア(大和島周辺)が比較的安全でおすすめです 。足場の良い岸壁からテトラ帯を狙えるので、初心者はまずこちらでも良いでしょう。沖堤防へ行く場合は渡船代がかかりますが、その分釣果は出やすいです。淡路島渡船を利用して早朝一番船で渡れば、人の少ないうちに好ポイントを攻められます。潮通しが良いぶん上級者向きとも言われますが、装備とやる気があれば初心者でも十分チャンスがあります。
大阪・泉南 樽井漁港周辺
大阪府南部、泉南市にある樽井漁港は、足場の良さと魚影の点で初心者に優しい穴場的ポイントです。港自体は南北に長い長方形の形状で、内側は水面まで高さがあまりなく非常に釣りやすい堤防になっています 。外側は一部テトラ帯がありますが、先端手前まで防波堤の上を歩いて行けて、初心者やファミリーでもアクセスしやすい釣り場です。
樽井漁港でのアコウ狙いは、敷石+岩場エリアを重点的に攻めるのがポイントです。港内の西側護岸沿いには沈みテトラや捨て石が入っており、その石の隙間に根魚が付きやすい構造になっています 。実際、テトラ帯の穴釣りではガシラ主体にメバル、そしてアコウも釣れる実績があります 。夕方~夜にかけては常夜灯の明かりが届く範囲で小魚が回遊し、それを狙ってアコウが接岸してくることも。足場の安定した港内側から、敷石周りに沿ってワームを通したり、テトラ際に落とし込んだりして誘ってみましょう。
特に港の曲がり角付近(北側カーブのテトラ帯)はチヌやグレのポイントとして知られ、根も荒い好ポイントです 。この周辺で夜にライトゲームをすると、20cm台後半のアコウがヒットした例が報告されています 。サイズこそ大物狙いの場ではありませんが、数釣りも期待でき、初めての一匹にはもってこいです。7~8月の梅雨時期から10月頃までがターゲットシーズンで、釣具店の持ち込み釣果でも梅雨アコウ(25~30cm)が報告されています 。
樽井漁港は隣接して「タルイサザンビーチ」という海水浴場があり、夏場は海水浴客で賑わいます 。釣りをする際は周囲のレジャー客にも配慮し、安全第一で楽しみましょう。比較的人が少ない夜間や早朝なら落ち着いて釣りができます。風の強い日はうねりが入ってテトラ帯は危険なので、そういう時は港内側の安全な場所から狙うようにします。ライトゲーム感覚で始められる釣り場ですが、アコウが掛かったら周囲のテトラにラインを擦られないよう、一気に浮かせるファイトを心がけてください。
初心者が気をつけるべきポイント&釣果アップの秘訣
最後に、初めてアコウ(キジハタ)を狙う初心者向けに注意点と釣果アップのコツをまとめます。時間帯の選び方、釣り方の姿勢、そして安全対策まで網羅してチェックしましょう。基本を守れば、高級魚アコウとのファーストコンタクトもきっと成功率が上がるはずです。
時間帯はマズメ+夜も狙い目!
アコウは夕マズメから夜間にかけて特に活発になる傾向があります 。日中は岩陰でじっとしている彼らも、薄暗くなってくると餌を求めて動き出します。初心者はぜひ夕方~夜の釣行を計画してみてください。具体的には日没前後の1~2時間(夕まずめ)と、21~24時頃までの常夜灯が効いてくる時間帯が狙い目です。夕まずめにはまず浅場に出て小魚や甲殻類を捕食し、暗くなった後は夜行性スイッチが入ってさらに活性が上がることがあります 。
夜釣りの場合、防波堤の常夜灯(街灯)の明暗境はベイトフィッシュ(イワシやアジなど)が集まるため、その付近はアコウの回遊ルートになりやすいです 。明かりの下そのものより、少し暗い側の陰に潜んで獲物を狙っていることが多いので、光が届く範囲の境目をルアーで通すと効果的です。もちろん潮通しも重要で、潮が動き出すタイミング(上げ始めや下げ始めなど)は捕食行動が活発になります 。潮見表を確認し、潮が緩む時間帯(止まり前後)と動き出しを意識して釣ると良いでしょう。
一方、朝マズメもチャンスはあります。夜の間に浅場に出ていたアコウが、明るくなる前にひと暴れしてから岩に戻ることがあるためです。特に夏~初秋は夜明け前後に実績報告もあります。ただし一般的に夜釣り派が多い魚ですので、無理に早起きせずとも夕方以降で十分です。
初心者の方は明るいうちに釣り場に入り、夕方から夜にかけての時間帯を狙うと安全面でも安心です。暗くなると足元も見えにくくなるので、明るいうちにポイントの状況を把握しておくと良いでしょう。また、夜釣りではヘッドライトで海中を照らしすぎないよう注意します。光を嫌う個体もいるため、足元を探る時以外は極力ライトは下向きに、海面を直射しないようにしましょう。
ランガンより「1級ポイントを丁寧に」!
アコウは縄張り性が強く、一定の好みの場所に居着く魚です 。そのため、シーバスのように回遊待ちで広範囲をテンポよく探る釣りとは少し異なります。どちらかと言えば「この岩陰にはいるはずだ」というポイントをじっくり攻め切る戦略が有効です。
初心者にありがちなのが、「釣れない…次の場所へ」と移動(ランガン)を繰り返してしまうこと。しかしアコウの場合、短時間で結果が出なくても粘ったほうがいいことが多々あります。なぜなら、単にタイミングが合っていないだけで魚自体はそこに潜んでいる可能性が高いからです。例えば一つの障害物に対し、角度を変え5投10投と繰り返すうちに急にゴンッと来る、といったことが起こります。「居れば食う」のではなく、「居ても最初は食わない」が前提の魚とも言えますので、ポイントのポテンシャルを信じて丁寧に誘い続けることが肝心です。
もちろん闇雲に粘れば良いわけではなく、魚が居そうな一級ポイントに絞って粘るのが大事です。具体的には「ここは絶対いる」と思える岩やテトラの際、前述したような地形変化のスポットです。そこではワームのカラーやリグを変えたり、アクションを速くしたり止めたりと変化をつけながら探ります。逆に、砂地ばかりで根がない場所や水深が浅すぎる場所など明らかに条件が悪い所は、見切りをつけて移動する判断も必要でしょう。
効率的な探り方として、「止め」を長く取るメリハリ釣法もおすすめです。5mほどズル引きしたら10秒止める、といった極端な間を与えることで、居場所から出てくるのを待つ作戦です。特に大型個体ほど警戒心が強く、喰い気が乗るまで時間がかかることがあります。焦らずじっくり攻めることで、思いがけない大物に巡り会えるかもしれません。
まとめると、「点」を攻めるイメージで釣りを組み立てると良いでしょう。広範囲を探るより、ここぞというポイントを順番に潰していくイメージです。その際、それぞれのポイントは可能な限り丁寧に攻め尽くす──これがランガン主体の釣りとの大きな違いであり、アコウ攻略の鍵です。
安全&快適な釣行のための注意点
最後になりましたが、安全対策は何より大切です。堤防や磯でのロックフィッシュゲームは足場が悪かったり夜間だったりと、危険が伴う場合があります。初心者の方は以下の点に十分注意して釣行してください。
ライフジャケットの着用
防波堤から海に落水する事故は毎年発生しています。必ずライフジャケット(できれば自動膨張式など信頼性の高いもの)を着用しましょう。釣り場によってはライジャケ未着用だと釣り禁止の場合もあります。命を守る基本装備ですので、面倒がらず必ず身につけてください。
滑りにくい靴&グローブ
テトラポッドの上や濡れた岸壁は滑りやすく非常に危険です。フェルトスパイク底のブーツや滑り止めシューズを履きましょう。また、魚の棘や怪我から手を守るためのフィッシンググローブも着用すると安心です。テトラ帯で手をついてバランスを取ることも多いので、手袋があると怪我防止になります。
ヘッドライトと予備灯
夜釣りでは明かりが命綱です。明るめのヘッドライトを用意し、予備のハンドライトやケミホタルなども携行してください。暗闇でのランディング時や帰路の照明としても役立ちます。電池残量のチェックもお忘れなく。
根掛かり時の対応
根掛かりを外そうとして無理に煽った際、突然外れて後ろに倒れそうになることがあります。足場の悪い場所では特に注意が必要です。根掛かりしたら慌てず、ラインを手に巻き付けて引っ張る、違う角度から外す等、安全な方法で対処しましょう。ロッドを大きくあおりすぎるとバランスを崩す原因になります。
天候・海況のチェック
波が高い日、強風の日、また台風通過後などは無理に釣行しない勇気も必要です。特に外向きの波止や磯は高波にさらわれる危険があります。釣行前に天気予報と波浪予報を確認し、安全を最優先してください。夜間は昼間以上に状況把握が難しいため、少しでも異常を感じたら中止・退避しましょう。
単独行動の回避
初心者のうちは可能なら釣り慣れた人と一緒に行動しましょう。夜釣りも単独より複数人の方がトラブルに対処しやすいです。やむを得ず単独で行く場合は、家族や友人に行き先と帰宅予定時刻を伝えてからにしてください。
安全に気を配りつつ、適度に休憩や水分補給もしながら釣りを楽しみましょう。焦って移動中に転倒したりしないよう、余裕を持った行動が肝心です。高級魚を手にした喜びも、安全あってこそです。
まとめ
秋はまさにアコウ(キジハタ)を堤防から狙う絶好のシーズンです!初心者でもポイントと釣り方のコツを押さえれば、憧れの高級根魚を手にすることも夢ではありません。まずはタックルを万全に揃え、根掛かりを恐れず一級ポイントを攻めてみましょう。スローな誘いと素早いアワセでアコウとのファイトを制し、安全に気をつけて釣り上げれば、その達成感と美味しさは格別です。
ぜひ本記事の内容を参考に、秋の堤防ロックフィッシュゲームにチャレンジしてみてください。最初の一匹が釣れた瞬間、強烈な引きとともにきっと釣りの魅力に取り憑かれることでしょう。楽しい釣行と大物との出会いを願っています。さあ、高鳴る胸をおさえつつ、秋の海へアコウ狙いに出かけましょう!


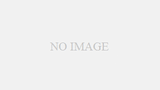
コメント