「淡路島でアオリイカを釣ってみたい!」そう思っていませんか?手軽に始められるうえ奥が深い“エギング”は、初心者からベテランまで大人気の釣法です。特に淡路島は潮通しが良く、秋・春にはアオリイカの好ポイントが点在する関西屈指のエリア。筆者自身も淡路島でエギングを続け、多くのアオリイカを釣り上げてきました。この記事では、アオリイカが釣れる時期やおすすめポイント、エギ選び、シャクリのコツまでをわかりやすく解説します。これを読めば、あなたも淡路島で待望の“初アオリ”を手にできるはずです!
エギングとは?淡路島で人気の理由
まずはエギングという釣りの基本を押さえましょう。エギングとは、餌木(エギ)と呼ばれるイカ用ルアーを使ってアオリイカを狙う釣り方です。シンプルな仕掛けながら非常に奥深く、獲物との駆け引きがクセになる魅力があります。淡路島がエギングの聖地と呼ばれる理由もあわせて紹介します。
エギングの基本と釣りの魅力
エギングでは魚の形をした**餌木(エギ)**というルアーを用いてイカを誘います。ロッド(釣竿)をシャクってエギを跳ね上げ、その後フォール(沈下)させる動作を繰り返すことで、エビや小魚が泳いでいるように演出します。アオリイカはその動きに興味を持ち、抱きつくようにエギにアタックします。仕掛けがシンプルで道具も比較的少なく始められる一方、エギのアクションやカラー選び、潮の読み方次第で釣果が大きく変わる奥深さが魅力です。ヒットした瞬間のずっしりとした手応えや、透明感のある美しいイカを手にしたときの感動は格別で、これがエギング人気の最大の理由でしょう。
淡路島がアオリイカ釣りに最適な理由
淡路島はエギングファンにとって憧れのエリアです。その理由の一つが潮の流れ。島の北端には明石海峡、南端には鳴門海峡があり、これらから流れ込む速い潮流が島周辺の海を満たしています 。潮通しが良いことでプランクトンが豊富になり、小魚や甲殻類などアオリイカのエサとなるベイトも多く集まります。さらに淡路島は東西南北で地形が変化に富み、深場のある港、ゴロタ石のシャロー(浅場)、潮通し抜群の地磯など多彩なポイントが点在します。こうした潮流と地形の相乗効果で一年を通じてアオリイカが狙え、春秋のシーズンには良型から数釣りまで楽しめるのです。また本州や四国からアクセスが良いことも人気の理由です。車や高速バスで気軽に行けるうえ、島内は海沿いに釣り場が密集しており短時間でランガン(次々ポイント移動)もしやすく、釣果も安定しています 。こうした条件が揃う淡路島は、まさにエギング天国と言えるでしょう。
初心者が始めやすい季節と時間帯
エギングを始めるのにおすすめの季節は秋です。秋は春に生まれた小型のアオリイカ(新子)が成長して岸寄りに増え、数釣りが楽しめるベストシーズンとなります。サイズは200~500g程度と小さめですが活性が高く、初心者でもエギに果敢に抱きついてくれるため釣りやすいのが特徴です。逆に春の大型狙いは経験やテクニックが求められるため、まずは秋から始めると成功体験を得やすいでしょう。また時間帯は朝マヅメ・夕マヅメ(夜明け前後と日暮れ前後)が狙い目です。このゴールデンタイムはイカの活性が上がり岸近くまで捕食に来るため、初心者でもヒットの確率が高まります。まずは秋の夜明け頃や夕暮れ時に釣行し、アオリイカからの最初の一杯を目指してみましょう。
アオリイカが釣れる時期とおすすめの時間帯
アオリイカは季節によって釣れやすさやサイズが変化します。淡路島では「春」と「秋」が特に好シーズンとして知られています。ここでは季節ごとの釣果傾向と、狙い目となる時間帯について紹介します。
春エギング
春(3~6月頃)の淡路島は、産卵期を迎える大型の親アオリイカがターゲットです。秋に生まれ越冬した個体が1~2kg以上に成長し、沿岸の海藻帯に産卵のため寄ってくるのがこの時期。サイズが大きく引きも強いためスリリングですが、その分数は少なく警戒心も強い傾向にあります。狙い方としては3月下旬~5月にかけての産卵前の荒食いシーズンがチャンス。エギは3.5号以上の大型サイズを使い、じっくりと探ります。日中よりも朝夕や夜間のほうが良型が出やすく、満月前後の大潮の夜には大物の実績もあります 。特に潮通しの良い藻場(海藻が繁茂する浅場)や、水深のある堤防先端などが春イカの好ポイントです。淡路島では西岸エリア(例:育波や佐野など)に藻場が多く、大型実績が高いとされています 。ただし春イカ狙いは渋い釣りになることも多いので、一発大物狙いと割り切って粘る根気が大切です。ヒットすればずっしり重いトルクフルな引きを堪能できますので、ぜひ挑戦してみましょう。
秋エギング
秋(9~11月頃)は淡路島エギングのハイシーズンで、数釣りが期待できます。夏に生まれたアオリイカの新子たちが初秋には手のひらサイズ(胴長5~10cm程度)に成長し、9月中旬以降から釣れ始めます。10~11月には胴長15~20cmほどの食べ頃サイズが岸近くの堤防や磯で数多く狙えるようになります。エギは2.5~3号前後の小さめで沈下スピードの遅いタイプが新子には効果的です。活性が高いので明るい日中でも釣れますが、やはり朝夕マヅメは入れ乗り(入れ食い)の好機となります。秋はエギング初心者でも思わず「こんなに釣れていいの?」と驚くくらい連発することも珍しくありません。淡路島全域で釣果が期待できますが、漁港の港内や小磯など足場の良い場所でも釣れるため、初心者は安全な堤防内側から始めると良いでしょう。特に10月は各地の堤防でアングラーが竿を出し、至る所で墨跡(イカが吐いた墨のあと)を見ることができます。なお淡路島では7月1日~9月20日はアオリイカは全てリリースするルールが設定されており、通年で胴長15cm未満の個体もリリース対象です 。資源保護のため、秋の序盤に釣れ始める小さなイカは優しく海に帰してあげましょう。解禁時期を迎える9月下旬~11月が秋イカ本番です。エギングデビューにはこの秋シーズンが最適と言えます。
朝マヅメ・夕マヅメのゴールデンタイムを狙おう
アオリイカ釣りで欠かせないのが時間帯の攻略です。特に釣果を伸ばしやすいのが**朝マヅメ(夜明け前後)と夕マヅメ(日没前後)**の時間帯。これらは一日の中で海中の活性が上がりやすく、アオリイカもエサを求めて動き出すゴールデンタイムと呼ばれます。夜行性の強いアオリイカは暗いうちに岸近くまで接岸し、夜明け直前から明るくなりはじめる頃にかけて盛んにベイトを追います。同様に日没前後の薄明かりの時間帯も活発です。朝まずめでは、夜間に岸寄りしていたイカが明るくなる前にエサを捕食するチャンスなので、夜明けの30分~1時間前には現地で準備し、薄暗い中で釣り始められるとベストです。夕まずめは逆に日没前後1時間程度が勝負。日中は沖にいた個体が再び岸に寄り、暗くなる直前に活性が上がります。これらの時間帯にはエギへの反応も鋭く、派手なカラーや夜光(グロー)エギへのアタックも多いでしょう。なお夜釣り自体も大型狙いには有効ですが、初心者はまず朝夕の明るさが残る時間で慣れるのがおすすめです。マヅメ時に狙いを絞って釣行プランを立てれば、限られた時間でも効率よく釣果を上げられるでしょう。
淡路島のおすすめエギングポイント
淡路島には北から南までエギングに適した釣り場が数多く存在します。ここでは釣果実績の高い定番ポイントから、人が少なめの穴場スポットまでエリア別に紹介します。地形やアクセス、注意点も合わせてチェックしておきましょう。
北淡エリア(岩屋港・仮屋漁港)
北淡エリアは淡路島の北部(淡路市エリア)で、明石海峡に近いポイントが多いエリアです。代表的なのが岩屋漁港と仮屋漁港です。岩屋漁港は本州から淡路島に渡って最初にある港で、明石海峡大橋のすぐ近くに位置します。潮通し抜群でアオリイカの実績も高く、秋には新子の数釣り、春には回遊してくる良型狙いができます。ただし潮流が速いので長時間居座るより様子見程度に立ち寄り、ランガンの起点にする人も多いポイントです 。有料ですが駐車場・トイレが整備され足場も良いため初心者にも安心です。一方の仮屋漁港(かりや)は東浦地区にある漁港で、北と南に2本の波止があります。特に南側の大波止先端は一級ポイントで、沖に面したテトラ帯から実績の高いアオリイカが狙えます 。沖一文字(沖合いの防波堤)との隙間に潮の通り道(ミオ筋)があり、流れが効いている時はディープタイプのエギを流し込むとヒットすることもあります 。仮屋漁港は港内も含めて釣りが可能で、人が少ない時は港内の係留船周りで新子が釣れることもあります。北淡エリアは全体的に潮が速い分、エギの操作に工夫が必要ですが、その分コンディションの良いイカが揚がる魅力的なポイントです。
中淡エリア(洲本港・江井漁港)
中淡エリア(洲本市周辺)は淡路島の中央部にあたり、都市部に近い釣り場が多いエリアです。まず洲本港(炬口〔たけのくち〕漁港含む)は淡路島最大の港で、設備も整ったファミリーフィッシングのメッカです。広い湾内ではサビキ釣り客も多いですが、エギングも可能です。特に港南側のメインの長い防波堤が狙い目です。先端付近は当然好ポイントですが、根元近くにも沈み岩(シモリ)が点在しアオリイカが付きやすいため、防波堤付け根付近でも墨跡が多く見られます 。実績では、潮通しの良い南防波堤の外向きで秋に新子が数釣れ、春にはテトラ周りで大型も上がっています。ただし洲本港は人も多く、釣れる時と釣れない時の差がはっきりする傾向があります 。そこでおすすめなのが江井漁港(えい)です。江井漁港は洲本市の西側に位置する小さな港で、周囲に目立った観光施設がないため訪れる人が少なく穴場的存在となっています。道がやや狭く駐車場所も分かりにくいのですが、その分プレッシャーが低くエギング初心者には面白いポイントです 。大きな波止の先端付近はテトラ帯になっており足場に注意が必要ですが、そこを踏破すれば秋には未開拓の新子を拾えることも。水深は浅めですが、満潮前後には港内にもイカが入ってくるので、堤防の中腹あたりから港内を狙っても釣果が出ます。中淡エリアはアクセスの良い場所が多いので、まずは洲本港周辺で様子を見て、混雑や釣況に応じて江井など人の少ないポイントに移動すると良いでしょう。
南淡エリア(福良湾・伊毘・阿万海岸)
南淡エリア(南あわじ市方面)は淡路島南部一帯で、鳴門海峡に面したポイントが点在します。ここは島の中でも特に潮の流れが強烈なエリアで、大型アオリイカの実績も豊富です 。まず福良湾は南あわじ市福良地区の湾内で、波静かな環境ながら湾口付近は鳴門の激流が入り混じる好環境です。福良港の周辺は足場の良い岸壁から秋に新子が狙え、夜には常夜灯周りにイカが集まることもあります。大型狙いなら湾口寄りの阿那賀漁港(あなが)や丸山漁港方面が有名です(阿那賀・丸山は福良湾の外側沿岸に位置)。阿那賀漁港は鳴門海峡に直接面した漁港で、地磯やテトラ、砂浜が混在するため様々な攻め方ができます 。特に漁港南側にある河口周辺や砂利浜から伸びる波止は、潮のヨレ(淀み)ができイカが溜まりやすい一級ポイントです 。次に伊毘漁港(いび)は島南西部にある漁港で、北側の旧港と南側の新港に分かれています。新港の沖向き防波堤全体がエギングポイントで、先端から内側まで広範囲に探れます 。近隣にキャンプ場もあり、ファミリーで訪れても楽しめる釣り場です。伊毘周辺の磯場や小波止も含め、秋は数釣り、春は実績ある大物狙いが可能です。最後に阿万海岸は南淡エリアの最南端近く、阿万地区に広がる海岸線です。鳴門海峡に面したこの海岸は潮通しが良く、磯と砂混じりのシャローエリアが続きます。特に阿万川河口の南側にある砂浜沖の波止との間が超一級ポイントで、秋には新子が数多く、春には大型も期待できます 。アクセスはやや不便で釣り人も少なめですが、ポテンシャルは非常に高く「淡路島の最果ての穴場」と言われることもあります。南淡エリアで釣りをする際は、潮流が速いため安全に十分注意し、タイミング(潮止まり前後など)を見計らって釣行しましょう 。
立入禁止・夜釣り制限エリアの注意点
淡路島内の釣り場には、一部立入禁止になっている場所や夜間の釣りが制限されているエリアがあります。近年、釣り人のマナー問題や事故防止のため、堤防先端や波止場がフェンスで閉鎖されたり、看板で釣り禁止が明示されたポイントも出てきました。例えば洲本市内の古茂江の波止は先端への立ち入りが禁止となっています し、南あわじ市の丸山漁港でも公園近くの岸壁は釣り禁止区域です 。こうした場所では絶対に立ち入らないようにしましょう。また夜間についても、港によっては「夜釣り禁止」の看板やルールがある所があります。地元住民への配慮や自身の安全のため、ルールは必ず守ることが大切です。釣行前には現地の看板を確認し、不明な場合は地元の釣具店で情報収集するのも良いでしょう。さらに路上駐車やゴミの放置も釣り禁止につながる要因ですので、駐車場を利用しゴミは持ち帰るなどマナー遵守をお願いします。淡路島は釣り人歓迎の場所が多い反面、一部マナー違反で閉鎖された場所も存在します。釣り場を未来へ残すためにも、ルールとマナーを守って安全にエギングを楽しみましょう。
エギングに必要なタックルとエギの選び方
「どんな竿やリールを使えばいいの?」「エギのサイズや色は?」――初心者にとってタックル選びは悩みどころです。ここでは淡路島で実際に使いやすいエギングタックル一式と、エギ(ルアー)のサイズ・カラー選びのポイントを紹介します。道具を万全に揃えておけば、釣り場での不安も減りエギングに集中できます。
ロッド・リールの選び方
エギングには専用のロッドとリールを用いるのが理想です。ロッドは長さ8フィート前後(2.5m前後)、硬さはミディアムライト~ミディアムクラスが標準的。エギング専用ロッドはティップ(竿先)が柔軟でシャクリやすく、バット(元部分)に適度な張りがあって重めのエギも遠投できるよう設計されています。初心者には8.3ft~8.6ftくらいの長さでエギ2.5号~3.5号に対応したモデルが扱いやすいでしょう。リールはスピニングリールの2500~3000番台が一般的です。ハイギアタイプ(1回転で多く巻き取れる)だとシャクリ後の糸ふけを素早く回収できるので便利です。具体的にはシマノならC3000番、ダイワならLT2500番クラスがベストマッチ。ドラグ性能が良く滑らかに出るものを選ぶと、突っ込みが強いイカでも糸切れせず安心です。ロッドとリール合わせて実売価格1万円台から入手可能なモデルもありますが、長く楽しむなら中級クラス(ロッド1.5万円、リール1.5万円程度)も検討してみてください。手に持ってシャクリ動作が多い釣りなので、軽量でバランスの良い組み合わせにすると疲れにくいです。実際に釣具店で持ち重りを確かめ、自分にフィットするタックルを選びましょう。
PEライン・リーダーの基本構成
エギングではPEライン(編み糸)の使用がほぼ必須です。メリットは細くて強度が高く、伸びが少ないためイカの繊細なアタリも伝わりやすい点です。一般的にはPE0.6号~1.0号程度(強度で言えば10~20lb前後)をメインラインとして使用します。初心者には扱いやすさから0.8号前後がおすすめです。リールには150mほど巻いておけば十分でしょう。PEラインは摩擦に弱く切れやすいので、先端にはショックリーダーと呼ばれるハリス(ナイロンまたはフロロカーボン糸)を結束します。リーダーの太さはフロロカーボン2号前後(約8lb程度)が基準です。春の大型狙いでは3号(12lb)に上げてもOKです。長さは1.5m前後あれば十分ですが、初心者は結束をリール側に巻き込めるよう3~4m長めに取っておくと安心かもしれません。結束方法はFGノットや電車結びなど強度の出るノットで確実に。PEとリーダーを結ぶ作業は最初は難しいですが、慣れれば数分でできます。ラインシステムをきちんと組んでおけば、大物がかかっても安心してやり取りできます。ちなみにリーダーを結ばずPE直結だとエギの動きは良いですが、岩場やイカの鋭い歯で簡単にラインブレイクするので避けましょう。PE+フロロリーダーがエギングの黄金コンビです。
エギのサイズとカラー選び
エギ(餌木)はエギングの主役とも言える存在で、そのサイズとカラーの選択が釣果に直結します。サイズは主に「号数」で表記され、1号=約3.75cm(エギ全長ではなく擬似エビ部分の長さ)です。春の大型狙いには3.5号(全長約13~15cm)前後のエギが定番です。重さは20g前後で遠投しやすく、大きなシルエットが大型イカにアピールします。逆に秋の新子狙いには2.5~3.0号(全長10~12cm程度)の小型エギがマッチします。軽量で沈下速度が遅めなので警戒心の少ない新子でも抱きつきやすいからです。ただし秋が深まってイカが成長したら3.5号にサイズアップすると型狙いができます。カラー(色)は状況に応じてローテーションするのが基本です。エギにはボディの色と下地テープ(金/赤/虹/銀、ケイムラ、夜光など)が組み合わされています。セオリーとしては澄み潮・晴天の日中はオレンジやピンクといった派手色より、ブルーやグリーン、茶色などナチュラル系カラーが効くことが多いです。逆に濁り潮・曇天や夜間はピンク、オレンジ、チャート(黄緑)などのアピールカラーや、ボディが光を反射・発光するタイプ(ホログラムテープや夜光ボディ)が有効です。とはいえその日のイカの気分によってヒットカラーは変わるため、複数色を用意して試すことが重要です。例えば最初は目立つオレンジで探り、追いはあるが抱かない場合は地味なイワシカラーに変えてみる、という具合にローテーションしましょう。また春の親イカ狙いでは小魚パターンが多いのでエギもベイトフィッシュに似たカラーが好まれます。お気に入りのカラー4~5種類をローテーションさせて、その日の当たり色を見つけてください。
初心者におすすめのコスパセット
これからエギングを始める方には、手頃な価格で揃うタックルセットを利用するのも一つの手です。釣具店やネット通販では初心者向けにロッド+リール+ライン+エギ数本がセットになった**「エギング入門セット」が販売されています。1万円前後からあり、手軽にスタートできるのが魅力です。ただ安価なセットではロッドが重かったりリールの巻き心地が劣る場合もあるので、できれば信頼できるメーカーの入門モデルを組み合わせると良いでしょう。例えばダイワやシマノにはエギング専用の廉価モデルがあり、性能とコスパを両立しています。ダイワなら「エメラルダスX」シリーズのロッドやLT2500番の入門リール、シマノなら「セフィアBB」シリーズなどが初心者に人気です。これらを組み合わせれば総額2~3万円程度になりますが、長く使用できる品質です。またラインは最初からPEが巻いてあるスプール付きリールもあるため、結束の手間を省けます。エギもセットに数本ついていることがありますが、信頼性の高い国産メーカー製(ヤマシタやデュエルなど)のものを追加で用意することをおすすめします。カラー違いで3本程度持っておけば安心でしょう。最初は道具にあまりこだわりすぎず、「これなら釣りに集中できる」という安心感のあるセット**を揃えるのがポイントです。徐々に経験を積んでから、自分なりにタックルをグレードアップしていけばOKです。
シャクリのコツとアクションの基本
エギングで最も重要なのが**「シャクリ」**と呼ばれるロッド操作です。エギに生命感を与えてアオリイカを誘うシャクリの上手下手で釣果が大きく変わります。ここでは基本のシャクリ動作と応用テクニック、そしてイカがエギを抱いた時のアタリの見極め方と合わせ(フッキング)のタイミングについて解説します。
基本のシャクリ方
エギングにおける基本アクションは**「ダブルシャクリ」と「リフト&フォール」です。まずダブルシャクリとは、その名の通りロッドを2回連続でシャープに煽る動作です。具体的にはラインスラック(糸ふけ)を出した状態から手首のスナップを効かせて素早く2回、ロッドを上下に動かします。これによりエギが水中でピョンピョンと2回跳ね上がり、小魚が逃げるような動きを演出します。シャクリ終わりにはロッドを元の位置に戻し、再度糸ふけを出してエギをフリーフォール(自然沈下)させます。エギはフォール中にヒラヒラと沈み、アオリイカはこのフォール中に抱きつくことが多いです。したがってシャクリ後のフォール中はラインに注意を集中しましょう。これが一連の「ダブルシャクリ&フォール」の基本サイクルです。次にリフト&フォールですが、こちらはゆっくり大きくロッドを持ち上げてエギを持ち上げ(リフト)、その後フォールさせる方法です。ダブルシャクリが速い2段ジャンプなら、リフト&フォールはふんわりと1回ジャンプさせるイメージです。活性が低い時や、新子相手にエギを見せつけたい時に有効です。基本的なアクション手順としては、(1)キャストして着底まで待つ → (2)シャクリ上げる(ダブルまたはリフト) → (3)フォールでアタリを待つ**、これを繰り返します。フォール時間は水深や反応により3~10秒程度と様々ですが、底付近から中層まで探るイメージで調整しましょう。シャクリの強さは最初は小さめから始め、慣れてきたらエギが跳ねすぎない範囲で大きく鋭くしていくと良いです。重要なのは、シャクリでしっかりエギに動きをつけたら必ずテンションを抜いてフォールさせること。初心者はここで糸を張ったままにしがちですが、それだとエギが不自然に漂ってイカが抱きつきにくくなります。糸ふけを出してフリーに落とし、その間に糸を注視してアタリを取る、という一連の基本をまず身体に染み込ませましょう。
潮や風を利用したアクションの工夫
エギングでは常に自分からエギを動かすだけでなく、潮流や風を上手に利用してエギにアクションを与えることも釣果アップのコツです。潮が流れている場合、無理にガツガツとシャクらなくても、エギを潮に乗せることでナチュラルな動きを演出できます。例えば潮が右から左へ流れているなら、やや上流(右側)へキャストし、エギを沈めたあと大きく一度シャクって浮かせます。あとはテンションを掛けずにラインを送り出し気味にしてやると、エギは潮に押されて斜め方向へドリフト(流される)します。潮受けしながらゆっくりフォールするエギは、イカにとって絶好の捕食チャンスとなります。これはドリフト釣法と呼ばれ、特に潮の速い淡路島の地磯などで有効なテクニックです。また風も時に味方にできます。追い風時は飛距離が伸びるので広範囲探れますし、向かい風でラインが押される時はエギの動きが抑えられてフォールがゆっくりになるメリットもあります。ただし横風や強風は糸ふけが出すぎてアタリが取りづらいので、そんな時は思い切って**重ためのエギ(ディープタイプ)**に変更し早めに沈める、風に正対する向きに立ち位置を変える等の工夫をしましょう。潮目(流れの境目)やヨレ(渦状の流れ)ができている場所では、そうしたところにエギを送り込んでフォールさせるとヒット率が高まります 。エギを自分で動かす「マニュアル操作」と、自然の力に任せる「ドリフト操作」を上手に組み合わせることで、イカに「違和感のない動き」を見せることができます。淡路島のように潮が効いているフィールドでは、是非とも身につけたいテクニックです。
アタリの見極め方と合わせのタイミング
アオリイカは魚と違って餌木を「食い込む」というより抱きつく(掴む)動作で捕らえます。そのためアタリも魚のアタリとは少し異なり、しっかり意識していないと見逃してしまいがちです。アタリのサインとして代表的なのはフォール中のラインの変化です。沈下している最中にイカがエギに抱きつくと、ラインの動きに次のような変化が出ます。
- ラインがふっと止まる(本来もっと沈むはずなのに途中で止まる)
- ラインが不自然に横に走る(潮とは逆方向にツッと動く)
- わずかにラインが弛む(軽くなったように感じる)
これらはイカがエギを抱いてエギの沈下が止まったり、イカがエギを持って移動したりすることで起こる現象です。常にラインを注視し、少しでも「アレ?」と感じたらそれがアタリだと思ってください。慣れてくるとシャクリからフォールに移る瞬間、指先に「モゾッ」という微かな重みを感じることもあります。イカは警戒するとエギを離してしまうので、アタリを感じた次の瞬間が勝負です。合わせ(フッキング)のタイミングとしては、違和感を感じたら即座に糸ふけを巻き取り軽く鋭く竿を煽るようにします。魚のように力一杯合わせる必要はありませんが、イカの足にカンナ(エギの針)が刺さるようにシャープに竿を引くイメージです。合わせが決まるとずっしりとした重みとグイグイ引っ張る力が伝わってくるでしょう。掛かった後は一定のテンションを保って巻き続けることが重要です。イカは引き味は強いですが口があるわけではなく、エギを抱いているだけなので、糸を緩めてしまうと「フッ」と離して逃げられてしまいます。逆に強引に煽りすぎるとイカの足がちぎれてしまう恐れもあります。ドラグを適度に滑らせつつ、ポンピング(竿でためて巻く動作)はせず終始一定の速度で巻き取りましょう。最後に抜き上げる際(またはタモ入れ時)に一番バレやすいので、足元まで気を抜かないことも大切です。アタリを取ってから取り込むまで、最初は緊張しますが、それだけに一杯目を手にした時の喜びは大きいですよ。
淡路島で釣果を伸ばすための実践テクニック
同じ場所・同じ時間に釣っていても、ちょっとした工夫で釣果に大きな差が出るのがエギングです。ここでは淡路島のフィールドで釣果をさらに伸ばすための実践テクニックを紹介します。「あと一杯」が遠いと感じた時や、渋い状況を打破したい時にぜひ試してみてください。
潮流と風向きを読む
エギング上級者ほど潮の流れと風向きを気にしています。淡路島のように潮流の影響が大きい場所では特に重要です。まず釣りを始める前に、その日の潮汐(満潮・干潮時刻)と潮の干満差、風向きと強さをチェックしましょう。潮見表や釣り気象サイトで簡単に調べられます。潮が動き始めるタイミング(上げ潮が効き出す、下げ潮が効き出す)は絶好の時合いとなることが多く、その前にポイントについて準備しておくのが理想です。現場では海面の様子を観察し、潮目や波紋の広がりを探します。潮目にはベイトフィッシュ(小魚)が溜まりやすく、アオリイカもそうした場所に待ち構えています。潮目が岸近くに寄っているなら、その付近へエギを通すよう意識しましょう。反対にベイトも何も見えず生命感のない水面なら、ポイント移動も検討します。また風向きはキャストの飛距離やラインメンディングに影響します。追い風なら遠投が効くので広範囲を探れる一方、向かい風では狙える範囲が狭くなります。横風が強い日は糸が風に煽られアタリが非常に取りにくくなるため、可能であれば風を避けられる立ち位置に移動する、風裏のポイントに移るなどしましょう。淡路島は場所によって風の当たり方が違うので、島の東西南北を移動して有利な風向きの側で釣るという選択肢もあります。ベイトの動きに合わせるとは、小魚が風や潮でどこに溜まっているかを読むことです。堤防なら風下側の隅にベイトが吹き寄せられたり、磯なら岬の先端側に潮上から流されてきたりします。そんな場所はアオリイカの絶好のハンティング場なので、見逃さずエギを投入してみましょう。自然条件を読んでポイントを選び、攻めるコースを決めることで、何も考えず投げるより格段に釣果アップが望めます。
カラーローテーションとエギのチェンジタイミング
釣れない時間が続くときは、エギのカラーやタイプを変えるのが効果的です。アオリイカにもその時々で好みの色や動きがあるため、ヒットがない場合はダラダラと同じエギを使い続けずカラーローテーションを心がけましょう。具体的には、明るい色→暗い色、ナチュラルカラー→アピールカラー、といった具合に全くテイストの異なるカラーに変更してみます。例えばピンク系で反応がなければ次はブルー系、それでもダメならオレンジ系やパープル系…というふうに一巡させます。何投くらいで変えるかは状況によりますが、目安として5投〜10投ほど探って反応がなければチェンジして良いでしょう。同じカラーでも下地テープ(虹テープ、赤テープ、金テープ等)違いで微妙に印象が変わるため、バリエーションがあれば試します。またサイズ変更も有効な場合があります。全くアタリがない時はエギを一回り小さくすると小型イカが乗ってくることがありますし、逆に小さいのしか釣れない時は大型のエギに変えてサイズアップを図ることもできます。さらにエギの沈下スピード(シャロータイプ/ディープタイプ)も使い分けましょう。活性が低い時はスローシンキングに変えてフォール時間を長く取る、イカが浮いていると感じたらゆっくり落ちるタイプにする、といった判断です。エギを変えるタイミングについては、一箇所を探り終わったら変える、釣れていたのにパタリと止まったら変える、逆にチェイス(追尾)はあるのに乗らない時に変える、などケースバイケースです。特にチェイスがあるのに抱かない時はチャンスタイムなので、すぐ別の色・サイズに交換して再度狙ってみてください。1投ごとに違うエギを試す必要はありませんが、「今イカがエギを見ているかも?」という状況では、素早いエギチェンジが功を奏することが多いです。カラーローテーション用に、明暗2色ずつ計4種類程度のエギを常備しておくと安心でしょう。
釣れない時間の立ち回りと粘りどころ
エギングでは「この1投で出なければ移動」といった見切りの良さも大事ですが、一方で粘り強さが報われる瞬間もあります。釣れない時間帯の過ごし方としては、大きく分けて「我慢して時合いを待つ」か「思い切ってポイント移動する」かの二択です。淡路島のポイント選びでは、満潮・干潮や昼夜のタイミングによって“時合い”が来る場所が異なります。例えば朝まずめ直後、周りも含めて反応がない場合、それはイカがその場にいないか活性が低い可能性があります。そのときは見切って別のポイント(例えば日が昇ってから強いポイントや、逆に日陰になる深場ポイント)へ移動する決断も必要です。特に広い淡路島ではポイントを転々と変えるランガンも有効な戦略です。一方で、イカの気配(チェイスや墨跡、他の人が釣る等)があるのに自分には釣れない時は、すぐ移動せず粘りどころかもしれません。そういう場合は先述のようにエギを変えたりアクションを変えたり、キャスト方向を変えてみたりと試行錯誤しましょう。足元近くまで探っていなかったなら最後に足元も丁寧に探るとヒットするケースもあります。特にアオリイカは群れで行動することもあるため、1杯釣れた後はその場で続けざまに釣れることがあります。釣れたからといってすぐ移動せず、少し粘って追加を狙いましょう。逆に長時間ノーヒットが続くようなら環境を変えるべきです。潮が動き始めるまで休憩するのも一つですし、北から南へエリアを大きく変えるのも手です。淡路島はエリアごとに若干水温やベイト状況が違うので、北がダメなら南へ、東がダメなら西へ、と極端に場所替えして好転することも珍しくありません。「釣れない時間帯こそ経験値を積むチャンス」と捉えて、色々と試しながら立ち回ると上達も早くなります。あきらめず工夫を重ねた末に手にした一杯は、きっと忘れられない釣行の思い出になるでしょう。
安全対策と快適なエギング装備
堤防や磯場でのエギングは、装備次第で快適さも安全性も大きく向上します。釣果も大事ですが、まず安全第一で釣りを楽しむことが肝心です。ここでは淡路島でエギングをする際に用意しておきたい基本装備と、その役割について確認しましょう。
ライフジャケット・スパイクシューズは必須
エギングに限らず海釣りで最も重要な安全装備はライフジャケット(救命胴衣)です。堤防だからと油断せず、必ず着用しましょう。万一足を滑らせて海に落ちた場合、ライジャケを着ていれば浮力で助かる可能性が飛躍的に上がります。磯場やテトラ上ではライフジャケット+**磯靴(スパイクシューズ)**が基本スタイルです。磯靴は靴底にスパイクピンやフェルトが付いていて、濡れた岩場や藻が生えた堤防上でも滑りにくくなっています。特に淡路島南部など岩礁帯が多い場所へ行くならスパイクシューズの着用は必須です。テトラポッドでの釣りも同様に滑落リスクがあるため、細心の注意とライジャケ+滑りにくい靴が必要となります。最近は自動膨張式ライフジャケット(コンパクトなベストタイプ)も普及していますので、動きの邪魔にならないものを選ぶと快適に釣りができます。加えて手袋(フィッシンググローブ)も怪我防止に有用です。イカのトゲやエギのカンナで手を傷つけないように、滑り止め付き手袋をはめると安心感が違います。安全装備は「万一の時のお守り」ですが、何もなければそれで良しなのです。淡路島でも岩場からの転落事故は起きていますから、自分は大丈夫と過信せず準備しておきましょう。釣りは安全に楽しんでこそ、良い思い出となります。
夜釣り用ヘッドライトと予備バッテリー
エギングでは日の出前や日没後の時間帯を狙うことも多く、ヘッドライトは非常に重要な装備です。両手を使って釣りができるよう、ライトはヘッドランプ型を用意しましょう。暗い足元を照らし安全を確保するだけでなく、ラインシステムの結束やエギ交換など細かな作業にもライトがないと困難です。ルアー釣り専用の赤色LEDモード付きヘッドライトもあります。赤色光は魚やイカが感じにくいため、足元でエギを交換する際に白色光を使うとイカを散らしてしまう懸念がありますが、赤色なら影響を抑えられます(必須ではありませんが、気になる方は活用してください)。それと忘れがちなのが予備の電池(バッテリー)です。夜明け前から釣りをしていると、明るくなってきた頃にヘッドライトの電池が切れる…なんてこともよくあります。特に長時間釣行や夜通し釣る場合はスペア電池、充電式ならモバイルバッテリーを携行しましょう。淡路島の堤防や磯は街灯が無く真っ暗な場所も多いので、ヘッドライトが命綱です。念のため予備の小型懐中電灯もザックに入れておくと完璧です。また夜釣り時は反射材付きウェアを着たり、ランタンを点けたりして、他の釣り人や船から見えやすくする配慮もあると安心です。視界と存在を確保して、安全に夜間のエギングを楽しんでください。
初心者でも安心な磯・堤防での立ち位置
釣り場での立ち位置にも気を配りましょう。初心者は特に足場の安定した場所を選ぶことが大切です。堤防であればできるだけ柵がある場所や、広くて平らな場所がおすすめです。堤防先端は釣れそうですが風が強かったり波を被ったりもしやすいので、最初は堤防中央付近の内側から始め、慣れてきたら先端に行くくらいでも遅くありません。テトラの上に立つ場合も、無理して沖側の高いテトラに乗るのではなく、比較的大きく安定したテトラに腰を下ろすくらいの姿勢で釣ると安全です。磯場では海に向かって張り出した先端部は釣果が期待できますが、波の影響を真っ先に受ける危険なポジションでもあります。初心者はできれば引き潮時など波が穏やかなタイミングに限定するか、経験者と同行して磯に入るようにしましょう。基本的に波が足元まで来て濡れている場所は危険信号です。立つ場所の高さを事前に確認し、波が来ても逃げられるルートを確保しておくことも重要です。また周囲に誰もいない深夜の釣行は避け、できるだけ他の釣り人がいる環境や明かりのある場所を選ぶようにすると安心感があります。淡路島の釣り場では地元の方が親切に声を掛けてくれることもありますので、分からないことがあれば聞いてみるのも良いでしょう。エギングは夢中になると足元への意識が疎かになりがちです。常に周囲の状況に気を配りながら立ち位置をキープすることで、初心者でも安心してシャクリに集中できます。安全が確保されてこそ、心から釣りを楽しめるというものです。
釣ったアオリイカを美味しく食べる方法
アオリイカは釣って楽しいだけでなく、食べても絶品です。せっかく自分で釣り上げた新鮮なイカですから、最高の状態で美味しくいただきたいもの。ここでは釣りたてアオリイカの締め方と保存法、定番の美味しいレシピ、そして持ち帰り時に鮮度を保つコツを紹介します。
釣った直後の締め方と保存法
アオリイカを釣り上げたら、できるだけ早く適切に処理することで味が格段に良くなります。まず取り込んだらすぐに締める(絞める)ことを心掛けましょう。イカを締める方法はいくつかありますが、手軽なのは急所をナイフやキリで刺す方法です。アオリイカの場合、目と目の間あたり(少し上寄り)に脳があり、ここを鋭利なものでひと突きすると即座に絶命します。締めると体色が真っ白になり、身が硬直して鮮度が保たれます。締めた後は、エラ(内臓)から墨袋が破れないよう注意して取り出し、海水で軽く洗い流します(現地で内臓まで処理するかは状況によりますが、持ち帰りを考えると抜いておくと楽です)。その後は素早くクーラーボックスで冷却しましょう。直接氷水に漬けると身が水っぽくなるので、ビニール袋に入れてから氷に当てるか、保冷剤を活用します。海水で冷やす際も、ジップ袋などに入れて浸けると良いです。ポイントは出来るだけ低温でキープすること。特に夏場や暖かい日は、釣ってから数時間で鮮度が落ちやすいため氷は多めに用意します。締めて冷やしたイカは、持ち帰ってから調理するまで冷蔵庫で保管してください。なお、イカは魚と違って外気に触れるとすぐ身が乾燥してしまいます。ラップや袋で密封しておくと表面の乾きや変色を防げます。釣った直後のひと手間で、食卓での美味しさが大きく変わりますので、ぜひ実践してみてください。
定番人気レシピ
釣り人の特権は、なんといっても新鮮なアオリイカを自分で料理して味わえることです。アオリイカは肉厚で甘みが強く、様々な料理で美味しくいただけます。まず外せないのが刺身です。透明感ある身は見るからに新鮮で、コリコリした歯ごたえと口に広がる甘みは格別。刺身にするには、胴体(身)を開いて薄皮を丁寧に剥ぎ、食べやすい大きさに包丁で引きます。細く切ればイカそうめん、そぎ切りにすれば刺身盛りに。わさび醤油はもちろん、生姜醤油やお塩だけでもイカ本来の甘みが際立ちます。次にバター焼き。バターで香ばしくソテーしたイカは、シンプルながら絶品のおかずになります。やり方は、食べやすく輪切りまたは短冊切りにしたイカをフライパンでバター炒めするだけ。仕上げに醤油を少し垂らせば、食欲をそそる香りが立ちます。レモンを絞っても美味しいです。柔らかいアオリイカは火を通しすぎないのがコツで、サッと炒めてプリプリ食感を楽しみましょう。そして天ぷらも人気レシピの一つ。衣をまとったイカはふっくらジューシーで、お子さんにも大好評です。一口大に切った身や足に薄く下味をつけ、衣を絡めてカラッと揚げれば完成。天つゆでも塩でも合いますが、個人的には抹茶塩やカレー塩など変わり塩で食べるのもおすすめです。その他にも塩焼き(網で焼いて醤油を塗る屋台風)、イカ墨パスタ(墨をソースに活用)、一夜干し(開いて塩干しに)などバリエーションは豊富。新鮮なアオリイカは何をしても美味しいので、釣れた際はいろいろな料理に挑戦してみてください。釣り人冥利に尽きる贅沢な時間が味わえるでしょう。
釣行後の持ち帰りと鮮度キープのコツ
釣ったアオリイカを家まで持ち帰る際には、いくつか鮮度キープのコツがあります。まず基本は低温を保つこと。クーラーボックスには氷を多めに入れ、イカができるだけ0℃に近い温度で維持されるようにします。ただし前述の通りイカを直接氷水に浸けないよう、袋に入れて氷に触れさせるか、氷とイカの間に新聞紙等を敷くと良いです。移動時間が長い場合や夏場は、氷が溶けてクーラー内が水浸しにならないよう氷は固形または保冷剤を使いましょう。溶けた水が出たら小まめに捨て、クーラー内をドライな冷気で満たすイメージです。次に直射日光を避けること。車に積む際は日陰に置き、釣り場でも車内に放置しないなど徹底します。せっかく冷やしても外気で温められては意味がありません。さらにイカ数杯をまとめて持ち帰る場合、一緒に入れると触れた部分から痛みやすいです。一杯ずつラップで包むか袋に分けておくと、互いの墨や体液で汚れず鮮度を保てます。家に着いたらすぐにクーラーから出し、必要に応じて再度〆て内臓を処理し、冷蔵庫へ入れましょう。アオリイカは釣ってから半日~1日寝かせると甘みが増すとも言われます(いわゆる“熟成”です)。すぐ食べるのもコリコリで美味しいですが、時間経過で身が柔らかく甘味が出るのもまた格別です。ただし傷みが早いので2日以内には食べきるのが無難です。どうしても食べきれない場合は、ラップで空気を抜いて冷凍すれば数週間は持ちます(ただし解凍時に食感は落ちます)。せっかく釣ったアオリイカ、美味しく味わうところまでがエギングの醍醐味です。鮮度管理に気を配って、自信作の料理を楽しんでください。
まとめ
この記事では、淡路島でアオリイカを狙うエギングの基本とコツを解説しました。
✅ 春・秋が淡路島エギングのベストシーズン – 春は大型の親イカ狙い、秋は新子の数釣りが楽しめます。特に秋は初心者にもおすすめの時期です。
✅ 初心者でも堤防から手軽にアオリイカが狙える – 岩屋港や洲本港など設備の整った釣り場が多く、安全装備とマナーを守れば初めてでもエギングを満喫できます。
✅ ポイントとシャクリを意識すれば釣果アップ! – 潮通しの良いポイント選びやマヅメ時の狙い撃ち、エギのカラーローテーションや丁寧なシャクリでヒット率が向上します。
次の週末は、ぜひ淡路島の海へ。朝日を浴びながらシャクリを楽しめば、あなたもきっと“初アオリ”の感動を味わえるはずです!エギングの奥深さとアオリイカの引きを存分に堪能し、釣って良し食べて良しの淡路島エギングライフを始めてみましょう。健闘を祈ります!


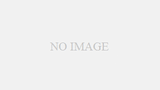
コメント