「淡路島でブリやハマチなどの大物青物を釣ってみたいけど、何から始めればいいの?」――そんなふうに悩んでいませんか?実は堤防や磯からメタルジグを投げて青物を狙うショアジギングこそ、まさに初心者にぴったりの釣り方です。淡路島は北の明石海峡と南の鳴門海峡に挟まれた潮通し抜群の地形でベイト(小魚)が豊富に集まるため、関西屈指の青物フィールドとして知られています 。筆者自身も淡路島の磯で初めてハマチを釣り上げたとき、その引きの強さと興奮は今でも忘れられません。この記事では、ショアジギングの基本タックル・ルアー選びから淡路島のおすすめ釣り場、季節ごとの狙い方や釣果アップのコツ、安全対策に至るまで徹底解説します。**この記事を読めば、あなたも淡路島で大物ヒットを狙えるようになり、釣った青物を美味しく味わう方法までバッチリわかりますよ!**結論を先に言えば、淡路島のショアジギングは初心者でも基本を押さえれば十分に大物青物が狙える最高のフィールドです。それでは具体的な攻略法を見ていきましょう。
ショアジギングとは?淡路島が人気の理由
まずは「ショアジギングってどんな釣り?」という基本から押さえましょう。岸から豪快にルアーを投げるこの釣りの魅力と、淡路島が初心者から上級者までショアジギングの聖地と呼ばれる理由、その環境的な強みを紹介します。
ショアジギングの基本
ショアジギングとは、岸(ショア)からメタルジグという鉄製のルアーを遠投し、大型魚を狙う豪快な釣りスタイルです 。重さ30~100g程度のメタルジグを思い切りキャストし、海中で泳がせて青物などを誘います。使うルアーは主にメタルジグですが、他にもバイブレーションやミノーなど金属製ルアー全般で底層から中層・表層まで幅広く探れるのが特徴です 。ショアジギングの最大の魅力は、陸から手軽に大物と出会えるチャンスがあること。メータークラス(1m超)のサワラやブリ、ヒラマサなど釣り人憧れの大型青物も、船に乗らなくても岸から狙えてしまいます 。初心者でも思わぬ大物がヒットする可能性があり、豪快なファイトを味わえるエキサイティングな釣りと言えるでしょう。
また、青物以外にもヒラメなどのフラットフィッシュ(平べったい魚)や根魚まで、様々な魚種がターゲットになるのもショアジギングの魅力です 。一度に広いレンジを探れるので、「何が釣れるかわからないワクワク感」も味わえます。タックル(道具)さえ揃えれば、防波堤でも磯場でも好きなポイントで始められる手軽さもあって、近年ますます人気が高まっている釣り方です。
淡路島がショアジギングの聖地と呼ばれる理由
そんなショアジギングですが、なかでも淡路島は全国的にも「ショアジギングの聖地」と呼ばれるほど人気のエリアです。その理由はズバリ、魚影の濃さと地理的条件の良さにあります。淡路島は北端に明石海峡、南端に鳴門海峡という二大急潮ポイントを抱え、島全体が**“天然のフィッシュロード”(魚の通り道)**の役割を果たしています 。強い潮流が栄養豊富な海水を島周辺に行き渡らせ、小魚(イワシやアジ、サヨリなど)の大群が集まりやすい環境です。それを狙ってブリやハマチ、サワラ(サゴシ)といった回遊魚から、ガシラやメバルなどの根魚まで多彩な魚種が寄ってくるため、一年を通して様々な魚に出会える豊かなフィールドになっています 。
特に青物に関して言えば、淡路島周辺ではツバス(ブリの幼魚)からハマチ・メジロ(中型)、そして大型のブリに至るまで幅広いサイズが狙えます 。秋には90cm級のブリが堤防から釣れる実績もあり、釣り人にとって夢のあるポイントです。「青物が1年中狙える」という声もあり 、季節ごとに異なるターゲットが回遊してくることで飽きることがありません。また足場の良い堤防から本格的な地磯、砂浜のサーフまでバラエティに富んだ釣り場が点在しているのも淡路島の魅力です。経験やその日の気分に応じてポイントを選べるため、初心者から上級者まで自分に合ったスタイルで挑戦できます。こうした好条件が揃う淡路島だからこそ、「ショアジギングをするなら淡路島」と言われるほど人気が高いのです。
初心者が挑戦しやすい時期と環境
淡路島は通年で青物を狙うチャンスがありますが、中でも初心者に挑戦しやすい時期というものも存在します。一般的に釣りのベストシーズンと呼ばれるのは春から秋にかけて。中でも秋(10~11月頃)は気候が穏やかで魚の活性も高く、「初心者にも優しい季節」と言われます 。水温が十分にある初秋~晩秋は回遊魚がエサを追って荒食いする時期で、**「秋は何でも釣れる」**とも言われるほど各魚種の釣果が上がりやすいのです 。このタイミングなら、初めてのショアジギングでもヒットに恵まれる可能性が高いでしょう。
一方、真冬の1~2月はベイト(小魚)が減って青物の回遊も少なくなるため、初心者には少し渋い季節です 。寒さも厳しく釣り自体が辛く感じることもあるので、まずは春先~秋にかけてチャレンジするのがおすすめです。**春(3~5月)**はサゴシ(サワラの若魚)やツバス(小ブリ)が釣れ始めるシーズンで、初夏に向けて青物シーズン開幕といった雰囲気があります。夏(6~8月)は日中暑いですが、朝夕のマズメ時や夜釣りでタチウオ(太刀魚)を狙えたり、運が良ければ南の海から回遊してくるシイラ(マヒマヒ)に出会えることもあります 。このように淡路島は季節ごとにターゲットが移り変わり、その都度違った釣り味を楽しめます。初心者の方はまず秋など釣りやすい時期に経験を積み、自信がついたら一年を通してチャレンジしてみると良いでしょう。
ショアジギングに必要なタックルとルアー選び
「どんな道具を使えばいいの?」「どんなジグを選べば釣れるの?」といった初心者の疑問に答えるセクションです。淡路島の地形や強い潮流に合わせたタックル構成やルアー選びの基本を押さえておきましょう。道具選びを間違えなければ、大物相手でも落ち着いてファイトできます。
ロッドとリールの選び方
ショアジギング用のロッド(竿)とリールは、大物とのやり取りに耐えられる強度と遠投性能が必要です。まずロッドですが、長さは9~10フィート前後(約2.7~3.3m)が一般的な範囲。長いロッドほど遠くへルアーを飛ばしやすく、高い足場(堤防や磯)からでも扱いやすいメリットがあります。一方で長すぎると取り回しが難しくなるため、初心者には10フィート未満~10フィート前後のバランスの良い長さが扱いやすいでしょう 。
ロッドの硬さ(パワー)は、扱うジグの重さによって選びます。基本的にショアジギングではMedium-Heavy(MH)以上の硬さが求められます 。水深の浅い堤防などで40g程度までのジグを使うならMHで十分ですが、淡路島の地磯や沖堤防のように水深が深く潮の速いポイントでは、60~80g以上の重いジグが必要になるためHeavy(H)以上のロッドがあった方が安心です 。淡路島の人気ポイント「翼港(つばさ港)」では潮流が速く、60g未満のジグはまったく底が取れず釣りにならないほどで、基本80gから、それでも流される時は100gでも着底しないことがあります 。そうした激流ポイントも攻略したいなら、H~XHクラスの強靭なロッドを選びましょう。最初の一本としてはルアーウェイトがだいたい~60g前後に対応したMH~Hクラスのロッドが汎用性が高くおすすめです。
次にリールですが、青物相手でもドラグ(糸を引き出す力)が強くスムーズに出るスピニングリールが一般的です。サイズはメーカーによって表示が異なりますが、シマノなら5000番前後、ダイワなら4000~4500番がスタンダードなサイズ感。これくらいのリールであればPEラインの3号前後を200~300m巻ける糸巻き量が確保でき、10kg級の魚にも太刀打ちできる強度があります。巻き取り速度も重要なので、初心者にはハイギア(HG)やエクストラハイギア(XG)モデルが手返し良く使いやすいでしょう。リールは重量が軽いほど操作性が上がりますが、その分価格も高くなりがちです。最初の一台は無理に高級機種を買わずとも、信頼できるメーカーの中級クラス(1万円台後半~2万円台程度)で十分実用に耐えます。例えばシマノの「アルテグラ」5000番やダイワの「フリームス」4000番などはコストパフォーマンスが高く、ショアジギング入門用に人気のモデルです。
PEラインとリーダーの基本設定
大物狙いのショアジギングでは道糸に**PEライン(編み糸)を使うのが一般的です。PEラインは細くて強度が高く、伸びがほとんど無いのでアタリを敏感に伝えてくれます。遠投もしやすいのでショアジギングには欠かせません。号数(太さ)は狙う魚と使うジグ重量に合わせますが、淡路島の青物狙いならPE1.5号~3号程度が目安です。初心者には扱いやすさと強度のバランスからPE2号(約8~10kg強度)**がおすすめ。これなら60g程度のジグも安心してフルキャストできますし、不意の大物が掛かっても余裕が生まれます。
PEラインは非常に滑らかで摩擦に弱いため、先端にリーダー(ショックリーダー)と呼ばれる太いナイロン/フロロカーボンラインを結束します。リーダーの役割は魚の歯や岩によるスレからPEラインを保護し、ファイト中のショックを吸収することです。太さはPEラインとの結束強度を保てる範囲でできるだけ太めを選びます。目安としてPE2号にはリーダー8号(約30lb相当)前後を合わせると良いでしょう。サワラやサゴシのように歯の鋭い魚が多いポイントではフロロカーボンの10号(40lb)程度にアップしても安心です。リーダーの長さは1.5ヒロ(約2.5~3m)ほど取っておけば充分です。長すぎるとキャスト時にガイドに巻き込んでトラブルの元になるので注意しましょう。結束にはFGノットなど強度の出るノットを習得してください。一見難しそうですが、最近は結び方動画や簡易ツールも充実しているので練習あるのみです。PEラインとリーダーの組み合わせをしっかりセットしておけば、大物とのやり取りでもラインブレイク(糸切れ)のリスクを大きく減らせます。
メタルジグの重さ・形状・カラーの選び方
ショアジギングの主役であるメタルジグは、種類が豊富でどれを選ぶか迷ってしまいますよね。まず重さ(ウェイト)ですが、これは釣り場の水深や潮の速さで使い分けます。淡路島ではポイントによって水深5m程度の浅場から30m超えの深場まで様々です。基本的な目安として、水深の約2倍の重さを一つの基準にすると言われます。例えば水深10mなら20g前後、水深20mなら40g前後という具合です。ただし潮の流れが速い場合はさらに重くしないと着底しません。淡路島の激流ポイントでは80g以上がメインなんてこともあります 。初心者の方はまず30g、40g、60gあたりのジグを揃えておき、中層狙いや浅場用に20g台も持っておくと安心です。風が強い日や遠投が必要な場面でも重めのジグがあると対応できます。
次に形状です。メタルジグは細長いロングタイプと扁平なショートタイプに大別できます。ロングジグは水押しが弱く沈下スピードが速いため、潮流の速いエリアや深場攻略に向いています。一方ショートジグはヒラヒラとゆっくり沈むので、浅場や食い渋り時にじっくり見せて食わせるのに効果的です。淡路島では基本的に飛距離と沈みの良さを重視してロング気味のジグが多用されますが、ベイト(小魚)のサイズが小さい時期や魚の活性が低いときにはショートタイプが有効な場合もあります。まずは扱いやすいセンターバランス(中央に重心)のジグから始め、慣れてきたらフロント重心・リア重心など動きの異なるジグも試してみると良いでしょう。
カラー選びも釣果に影響することがあります。定番は**シルバー系(イワシカラー)**やブルーピンクなど、ベイトフィッシュに似せたナチュラルカラーです。晴天時や日中のクリアな海ではナチュラル系、朝夕のマヅメや曇天・濁り時にはアピール系カラーが効果的と言われます。ゼブラグロー(夜光発光カラー)は夜明け前や夕マヅメの薄暗い時間帯、深場攻略の切り札としてぜひ持っておきたいカラーです (100円ジグには無いので別途用意を、との先人アドバイスもあります )。他にもチャート(黄緑)やピンクゴールドなど、水の色や太陽光によって見え方が変わる色もローテーションに組み込むと良いでしょう。「この色でなければ釣れない」ということはありませんが、信頼できるカラーが手元にあると心強いものです。最初は評判の良い定番色を揃え、釣行を重ねながら自分の実績カラーを見つけていきましょう。
初心者におすすめのコスパ最強タックルセット
最後に、これから淡路島でショアジギングを始める方向けにコストパフォーマンスに優れた入門タックルの一例を紹介します。全て購入しても予算3万円前後に収まるような組み合わせです。
- ロッド:ダイワ「ショアジギングX 100MH」 – 全長10フィート・ルアーMax60g・MHパワー。1万円台前半で買える本格ショアジギロッドです。初めての一本に最適。
- リール:シマノ「21ナスキー 5000XG」 – 2万円弱で入手可能な中堅スピニングリール。5000番のハイギアで手返しも良く、ドラグ力も充分。堅牢性があり長く使えます。
- PEライン:よつあみ「パワーハンターPE 2号-300m」 – 300m巻きで数千円程度。強度と扱いやすさのバランスが良い4編みPE。色付きなら残量も把握しやすいです。
- リーダー:シーガー「フロロショックリーダー 8号(30lb)」 – 50mで1,000円程度。青物狙いの定番フロロリーダー。太さ8号ならハマチクラスまで安心です。
- メタルジグ:ダイソーのメタルジグ(40g・ブルー/ピンクなど) – まずは100円ジグを複数用意しましょう。根掛かりしても惜しくない価格なので練習に最適。ただし夜光ゼブラカラーはないため、別途市販品で40g前後のゼブラグローを1本用意しておくと万全です。
上記は一例ですが、例えばロッドをメジャークラフトの「ソルパラ」シリーズに変えたり、リールをダイワ「レブロス」4000番にするなど、各価格帯でさまざまな代替品があります。重要なのはロッド・リール・ラインがバランスよく強度面でマッチしていること 。**「ロッドはMHクラス」「リールは4000~5000番」「PE2号前後」**という基準を押さえてタックルを組めば、大きな失敗はないでしょう。最初のタックルで無理に高価なものを揃える必要はありません。釣りに慣れてきて「もっと軽いセットが欲しい」「さらに大物に対応したい」と感じたタイミングで、徐々にステップアップしていけばOKです。
淡路島ショアジギングのおすすめ釣り場
淡路島には**堤防・磯・サーフ(砂浜)**と実に多彩な釣り場があります。それぞれロケーションによって特徴が異なり、狙える魚種や釣り方も変わってきます。このセクションではジャンル別に淡路島の代表的なポイントを紹介しましょう。釣行プランを立てる際の参考にしてください。ただし、釣り禁止区域や立入制限にも注意が必要ですので、マナーを守って楽しみましょう。
堤防でのショアジギングおすすめポイント
淡路島の**堤防(防波堤)**は初心者でも挑戦しやすいポイントが多くあります。足場が平坦で比較的安全に釣りができ、駐車場やトイレが整備された場所もあるため、まずは堤防から始めるのがおすすめです。
- 洲本港周辺(洲本市) – 淡路島の中部に位置する大規模港湾で、釣り場としても有名です 。港内は水深が深い場所もあり(10m以上)、秋には太刀魚や青物の実績が高いポイントです 。周囲に釣具店やコンビニもあり利便性抜群。ただし洲本港の沖に伸びる赤灯台の波止は2020年以降立入禁止となっているので注意してください 。マナー違反者が続出したためフェンス封鎖されてしまい、水深15mほどある絶好の青物ポイントでしたが現在は釣りができません 。釣りをする際は開放されているエリア(港内の岸壁や別の波止)を利用しましょう。近隣には有料で渡船してもらう**洲本一文字(沖波止)**もあります。予算と時間に余裕があれば渡船利用で沖の一文字に渡ると混雑も避けられ、ブリクラスの釣果も期待できます 。
- 江井漁港(淡路市) – 淡路島西岸の中部に位置する漁港です。湾内は波穏やかで、ファミリーフィッシング向きののんびりした雰囲気ですが、防波堤の先端から外海向きにキャストすると潮通しが良く大物も狙えます 。テトラ帯があるので足元に注意が必要ですが、テトラの切れ目周辺はベイトが溜まりやすく青物ヒットの可能性十分です 。実際に江井漁港ではハマチクラスの回遊やアオリイカ、スズキなども釣れています 。車は隣接の海水浴場駐車場に停められますが、夏場は海水浴シーズンで有料になるのでご注意ください。
- 炬口漁港(洲本市) – 「こたき(またはたき)港」と読む洲本市中心部近くの漁港です。ここは無料駐車場・トイレが整備され、かつテトラポッドのない平坦なケーソン(コンクリ護岸)から釣りができるため淡路島でも屈指の人気釣り場となっています 。足場が良く家族連れでも安心なうえ、シーズンを通して多彩な魚種が狙えます 。青物の回遊もあり、秋にはブリやメジロ狙いのルアーマンも多く訪れます。夜は常夜灯下でアジング(小アジ狙い)やメバリングも楽しめ、初心者からベテランまで賑わうポイントです。ただし人気ゆえ混雑もしやすいので、譲り合って釣り座を確保しましょう。また過去にトイレが破壊される心ない事件も起きているため 、利用者一人ひとりがマナーを守る意識を持ちたいところです。
この他にも、北淡エリアの岩屋港周辺や南淡エリアの福良港など、堤防から狙える釣り場は多数あります 。共通して言えるのは、堤防釣りでは安全最優先で足場の状況を把握することと、地元の規則やマナーを遵守することです。立入禁止区域の看板があれば必ず従い、ゴミは持ち帰るようにしてください。堤防は気軽に釣りを楽しめる反面、マナー違反があるとすぐ釣り禁止になってしまうデリケートな場所でもあります。ルールを守って長く釣り場を維持していきましょう。
磯場での実践ポイント
より本格的な釣りを味わいたいなら、淡路島の**磯場(岩礁帯)**もおすすめです。磯は自然の地形そのままの釣り場で、足場が悪い反面、魚との距離が近くダイナミックな釣りが楽しめます。淡路島には島沿岸の至る所に大小の磯場がありますが、その中から比較的アクセスしやすく青物実績のあるエリアを紹介します。
- 阿万磯(南あわじ市 阿万地域) – 淡路島南部、阿万地区の海岸線にはゴロタ石混じりの磯場や岩場が点在しています。阿万海岸は河口が絡む地形で、延びる波止と隣接するプチ磯&サーフになっており、四季折々いろいろな魚種が狙えるポイントです 。夏は海水浴客も訪れるため昼間の釣りは控えめに、朝夕の時間帯に狙いましょう。秋から初冬にかけては25cm級の大型アジ(マアジ)が回遊してくることがあり 、それを追って青物がヒットすることも期待できます。磯といっても入りやすい地形なので、磯釣り入門にも良いでしょう。
- 伊毘漁港周辺の磯(南あわじ市 伊毘) – 南あわじ市の西側、大鳴門橋に程近い伊毘エリアも穴場的な磯ポイントがあります。伊毘漁港自体が青物やアオリイカ、シーバスなど実績豊富な釣り場で 、その周辺にある岩場からもショアジギングで青物が狙えます 。見晴らしも良く大鳴門橋を眺めながら釣りができるロケーションも魅力です 。足場は磯なのでライフジャケットと滑りにくい靴は必須ですが、地形的には比較的平らな岩も多くエントリーしやすい磯と言えます。ここではハマチやメジロクラスの釣果が報告されており、秋には青物の他に新子のアオリイカエギングを楽しむ人も多いポイントです。
- 都志磯(都志港周辺 西海岸) – 淡路島西浦の都志港周辺には、一部磯場が広がるエリアがあります。都志自体は大きな風車が目印の広い漁港で足場が良く、サビキ釣りからルアーまで人気のスポットですが 、その港の外側には岩場混じりの海岸線が続いています。テトラ帯もありますが、所々磯が顔を出しており、満潮時にポイントまで渡れる小磯も点在しています。都志周辺は秋に青物の回遊が多いエリアとして知られ、メジロクラスがヒットした実績もあります(港の沖向きでは珍しくタチウオの釣果も報告されています )。磯から狙う場合は潮位に注意し、干潮時に立てた場所が満潮で水没しないか気を配りましょう。比較的緩やかな磯ですが、波が高い日は無理せず引き返す勇気も必要です。
磯場で釣りをする際は、安全装備の徹底と単独行動の回避が鉄則です。磯は気象海象の影響を受けやすく、一瞬の高波で危険な状況に陥ることもあります。必ずライフジャケットと滑り止めブーツを着用し、できれば複数人でお互い見守りながら釣行してください。また磯では足元の根掛かりも頻発します。根掛かりでルアーが外れず焦ると危険な姿勢をとりがちなので、無理に外そうとせずラインを手巻きで切るなど冷静に対処しましょう。磯釣りはリスクも伴いますが、そのぶん大物と出会えるチャンスも多いロマン溢れる舞台です。装備と心構えを万全に挑んでください。
サーフエリアでの釣り方
淡路島には美しい砂浜(サーフ)も数多くあり、砂浜からのルアーフィッシングも楽しめます。サーフでのショアジギングは、波打ち際から遠浅の海に向かってキャストし、主にヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュを狙うスタイルが有名ですが、タイミングが合えば青物が接岸することもあります。淡路島でサーフゲームを楽しめる代表的なビーチを紹介します。
- 慶野松原(けいのまつばら)海岸 – 淡路島西岸南部に広がる白砂青松の美しい海岸です。遠浅で波も穏やかなため夏は海水浴客で賑わいますが、シーズンオフの秋冬は絶好のサーフフィッシング場になります。ここではヒラメやマゴチ狙いでメタルジグやワームをキャストするアングラーが多いです。特に11~12月は産卵前のヒラメシーズンで、実績も上がっています。また秋にはカタクチイワシなどベイトが接岸すると、小型青物(ツバスやサゴシ)が岸近くまで追い込んでナブラを起こすこともあり、運が良ければサーフで青物を釣り上げるチャンスもあります。広大な砂浜なので釣り座の自由度が高く、障害物も少ないため初心者でも気軽にルアーを投げられるでしょう。ただし夏場は遊泳者優先のため、海水浴シーズン中の釣りは控えるか時間帯を工夫してください。
- 浦県民サンビーチ(岩屋北岸) – 淡路島北端、岩屋地区にある県立の海水浴ビーチです。明石海峡大橋のたもとに位置し、対岸の明石方面を望みながら釣りができます。ここも遠浅の地形ですが、北側は岩屋港に近く水深が若干あります。海底は砂地主体で所々にシモリ(沈み岩)もあります。ターゲットは秋~初冬のヒラメ・マゴチがメインですが、明石海峡に接しているため青物が回ってくる可能性も秘めています。特に朝夕にイワシの群れが寄っている時は要注目です。ルアーはメタルジグだけでなく、シンキングペンシルやミノーなども有効で、表層近くを泳ぐベイトに青物が付いている場合はミノーのただ巻きでヒットすることもあります。浦県民サンビーチは駐車場やトイレも整備されており、ファミリーレジャーついでに釣りを楽しむにも良い環境です。朝マズメの時間帯は地元アングラーも来ますので、場所取りは譲り合いましょう。
サーフで釣りをする際は、足元の波と流れに注意してください。見た目以上に波の力は強く、知らず知らずのうちに立ち位置が移動してしまうこともあります。シューズは砂が入りにくいハイカットのものを選び、できればフェルトスパイク底だと砂浜と水際の両方で滑りにくく安心です。また周囲に他の投げ釣り客やサーファーがいないか確認し、トラブルのないよう心掛けましょう。砂浜は開放感がありますが、油断せず後方確認と安全第一でキャストしてください。
釣り禁止・立入制限エリアの注意点
淡路島内の釣り場は年々状況が変化しており、釣り禁止区域や立入制限が設けられる場所も増えています。せっかく遠征しても現地で「立入禁止」の看板を見てショック…ということがないよう、事前に情報収集しておきましょう。
- 前述したように洲本港の赤灯波止は完全立入禁止となっています 。フェンスが設置され厳重に封鎖されているので近寄らないようにしましょう。地元釣具店や釣りブログでもアナウンスされていますが、2020年の閉鎖以降現在も解禁の予定はありません。代替としては有料の洲本一文字や、近隣の炬口漁港などで釣果が出ていますので、ポイントをスライドする形で対応すると良いでしょう。
- オノコロ裏(塩田新島) – 淡路市今井の海岸、淡路ワールドパークONOKORO裏手の人工島は一級の太刀魚ポイントとして有名でしたが、2024年に立入禁止となりました 。進入路が封鎖され、路上駐車の取り締まりも強化されています 。無理に侵入するとトラブルになりますので諦めましょう。同様に、近隣の志筑新島でも一部で車両の乗入れ禁止措置(ポール設置)がされているエリアがあります 。
- 佐野漁港の一部 – 淡路島西岸の佐野港では、漁協関係者以外立入禁止のエリアがあります 。過去に漁業用施設の水道を無断使用したり、深夜に騒いだ釣り人がいたため閉鎖措置となりました 。ローカルルールが存在する港もありますので、初めての場所では入口付近に注意書き看板がないか確認しましょう。
- 翼港(津名港 翼先端) – 淡路市の交流の翼港は有料釣り場で営業時間と定員があります。休日は早朝から入場待ちの行列ができる人気スポットで、「朝3時には並ばないと狙いの釣り座に入れない」なんて声もあります 。また釣り場が狭く子供連れファミリーも多いため、キャスト時は後方の壁や人に細心の注意が必要です 。有料施設のルール(受付手続き、釣座の順番、定員制限など)も事前に調べておきましょう。
以上のように、釣り禁止エリアは年ごとに変わる可能性があります。最新情報の入手には釣具店のスタッフや地元釣りブロガーの発信、SNSなどが役立ちます。また「駐車禁止」「夜間立入禁止」「○時以降閉門」など細かなルールも各所で定められています。違反すると即閉鎖されてしまうケースも珍しくないため、「ここで釣りをさせてもらっている」という意識を持って行動しましょう。淡路島の豊かな釣り場を次世代にも残せるよう、マナー遵守と美化にご協力をお願いします。
季節ごとに狙える青物と釣果アップのタイミング
ショアジギングでは季節によって狙える魚種や効果的な釣り方が変化します。ここでは淡路島における季節ごとの主なターゲットと、釣果を伸ばすためのタイミングのコツを解説します。季節の移り変わりを感じながら、その時期ならではの青物攻略法を身につけましょう。
春はサゴシ・ハマチの回遊が始まる時期
**春(3月~5月頃)は水温の上昇とともに青物シーズンが幕を開ける時期です。冬の間おとなしかった海に、徐々にベイトフィッシュが戻ってきます。淡路島では3月頃からサゴシ(サワラの幼魚)**が釣れ始め、港内でも跳ねたりナブラが発生する光景が見られるようになります。サゴシは50~60cm程度で数釣りが楽しめる青物で、ショアジギング初心者には格好のターゲットです。表層近くでヒットすることも多いので、メタルジグの早巻きやジグサビキ(ジグ+疑似餌フック)で手軽に狙えます。
4月以降になると**ハマチ(ブリの若魚 約40~60cm級)**やメジロ(60~80cm級)の回遊もポツポツと始まります。特にゴールデンウィーク明け頃からはイワシやコノシロなどベイトが接岸し、それに付いて青物が湾内に差してくるパターンが増えます。春先はまだ群れの規模が小さいこともあるため、**時合い(魚の活性が上がる短時間)**を逃さないことが重要です。朝マズメや夕マズメに短期決戦で回遊がある場合が多いので、潮見表で日の出・日没時間をチェックし、その前後に集中してキャストしましょう。
春の青物狙いでは、細めのタックルで食い渋りに対応するのも一つの手です。水温が低めの春は活性が完全には上がりきらず、動きの速いジグに反応しない魚もいます。そんなときはジグの動きを少しスローにしたり、小型のジグ(20~30g)に変えてみるとヒットに繋がるケースがあります。またサワラ類は**フォール中(ジグを落としている途中)**にアタックしてくる習性が強いので、ジグを投げたら着底まで油断せずラインを注視しましょう。ラインがフッと緩んだり止まったら、それは食っている証拠です。一呼吸おいてから合わせを入れてみてください。
夏は小型青物・タチウオ・シイラが狙える
夏(6月~8月頃)の淡路島は海水浴シーズンで釣り人もやや減りますが、実は釣れる魚は多彩です。梅雨明け頃から初夏にかけて、春に生まれた小型の青物(ツバスと呼ばれる20~30cm級のブリ幼魚)が各地の漁港で見られるようになります。これらは群れで行動しており、岸壁際でサビキにかかった小アジを横取りしたり、コマセ(撒き餌)に突っ込んでくる姿が観察されます。サイズは小さいですが引きは強く、ライトショアジギングで狙うと面白いターゲットです。18~28g程度の軽めのジグを早巻き主体で誘うとよく反応します 。ツバスは回遊次第なので、釣れだしたという情報があればすぐ現場に向かうフットワークの軽さも大事です。
夏本番の7~8月になると、夜釣りで**タチウオ(太刀魚)**を狙う人が増えてきます。淡路島では西浦(西岸)の漁港や一文字堤防でタチウオの実績が高く、夕方から夜にかけてワインド釣法やテンヤ釣りが盛んです 。ショアジギングスタイルでも、メタルジグのただ巻きやフォールでタチウオは釣れます。タチウオは群れで回遊するので、当たりが出だすと入れ食いになることもあります 。逆にまったくいないときは何をしても釣れませんので、釣果情報をチェックしてポイント選びをしましょう。夜間の釣りになるためライフジャケットと灯具は必須、安全第一でお願いします。
さらに夏の淡路島では、稀に**シイラ(マヒマヒ)**やカツオ類など南方系の回遊魚が回ってくることがあります 。特に南部の土生港沖や由良沖では毎年ではないもののシイラの目撃情報があり、実際にルアーで釣れた例もあります 。これらはボイル(魚が水面をバシャバシャ追い回す)すれば狙えますが、偶発的要素が強いので「釣れたらラッキー」くらいに思っておきましょう。夏場は全体的に日中は厳しいことが多いです。炎天下では魚も人もバテますので、朝夕の涼しい時間帯を中心に釣行計画を立てるのがおすすめです。また熱中症対策(水分・塩分補給、帽子着用、適宜休憩)も万全に行ってください。
秋はブリ・メジロの最盛期!
**秋(9月~11月頃)**は淡路島ショアジギングのハイシーズンです。「秋は釣り天国」と言われるほど魚影が濃くなり、初心者でも釣果を期待できる季節となります 。特に青物に関しては、ブリ・メジロ級が狙える最盛期です。夏の間に成長した個体が荒食いを始め、各地で大物の釣果が報告されます。10月~11月には、洲本や岩屋の一文字堤防で90cmオーバーのブリが上がった例もあります。夢のメータークラスも現実味を帯びるのがこの秋シーズンなのです。
秋に釣果を伸ばす鍵は、ベイトの動向を読むことと時合いを逃さないことです。イワシやアジなどのベイトフィッシュが接岸するとき、海面にナブラ(魚の群れが逃げ惑って水面が騒ぐ)が発生します。鳥山(海鳥が群れて飛び回る)も立ちやすく、これらはまさに絶好のヒットチャンスです。ナブラを見つけたら、少々距離があっても重めのジグで思い切り遠投し、ナブラの少し先に着水させて高速リトリーブするとガツンと来ることがあります。「ナブラ打ち」と呼ばれる釣法で、ショアから青物を仕留める醍醐味の一つです。もっとも、青物は意外と警戒心が強いので、ナブラ直撃より周辺を通す方が食いやすいとも言われます。興奮を抑えて冷静に狙いましょう。
また、秋は魚たちが冬に備えて活発に餌を追い回す荒食いの季節です 。朝夕のマズメだけでなく日中でも潮が動けばチャンスがあります 。淡路島翼港の例では、「潮が緩んだタイミング(潮止まり前後)がチャンスタイム」「マズメだけでなく1日中投げ続ければいつか回遊に当たる」といったデータが出ています 。つまり秋は長時間粘っても報われる可能性が高いということです。体力と相談になりますが、大物を狙うなら休憩をはさみつつ可能な限り竿を出しておきたいところですね。
ルアーについては、秋はベイトサイズが大きくなっている場合が多いのでやや大きめのジグやミノーが有効です。普段40gを使っているなら60g、60gを使っているなら80gとワンサイズ上げてみるのも手です。活性が高い魚はアピールに対して貪欲なので、派手なカラーや大きなシルエットにも果敢にアタックしてきます。ただしプレッシャーが高い人気ポイントでは、逆に小型ジグで喰わせる戦法もハマることがあります。他の人と違うルアーを投げてみるのも、混雑時には一つの作戦です。
冬は回遊が減るが根魚・ヒラメが狙える
**冬(12月~2月頃)**は青物の回遊が減少し、ショアジギング的にはオフシーズンに近づきます。ただ「まったく釣れない」わけではなく、狙い目と対象魚を変えれば釣果を出すことは可能です。青物の大群は南下して姿を消しますが、中には瀬付き(その場に居着く)化したハマチや、小規模な群れが残る場合もあります。実際、厳寒期の2月でも淡路島沖磯でブリが釣れた例があり 、絶対ではありません。ただ、初心者がわざわざ寒い思いをして青物を追うのは効率的ではないでしょう。
冬場にショアジギングスタイルで楽しめるターゲットとしては、根魚(ロックフィッシュ)が挙げられます。淡路島南部の沼島周辺や鳴門海峡側ではカサゴ(ガシラ)やソイ、アイナメなどが盛んなエリアがあり 、これらは冬でも活発にエサを捕食します。重めのジグヘッドにワームを付けて探るジギング的なアプローチで根魚を狙うのも一興です。足元の消波ブロック周りや岩陰をリフト&フォールで探れば、意外と良型のガシラがヒットするかもしれません。日中よりも夕まずめ~夜の方が実績が高いので、防寒対策を万全にして挑みましょう。
また、冬から初春にかけてはヒラメが狙い目です。特に1~2月の産卵期前後は岸寄りする個体もいて、大きいものは70cmクラスの座布団ヒラメも夢ではありません。砂地のサーフや港内の砂泥底を、底付近を意識してメタルジグをゆっくりめに引いてみてください。ヒラメは着底直後やリトリーブ開始直後に食ってくることが多いので、「着底→すぐシャクリ上げ」の繰り返しではなく、着底後に間をおいてゆっくり動かすようなイメージが有効です。食い渋るときはメタルジグをやめてバイブレーションやワームに切り替えるのも手です。
冬場は気温・水温ともに低く、人間の方がくじけやすいですが、そのぶん釣り人が少なくポイントを独占できるメリットもあります。「寒いけど誰もいない朝マズメ」に一発大物が…なんてロマンも秘めています。釣れないと決めつけず、安全第一で無理のない範囲で冬の海にも足を運んでみてください。澄んだ空気の中、静かな海で竿を振るだけでも心洗われるものがあります。
釣果を伸ばす!ジグアクションと回遊予測のコツ
ショアジギングで釣果を伸ばすためには、**ジグのアクション(操作方法)**を工夫することと、魚の回遊タイミングを読むことが重要です。ただ闇雲に投げて巻くだけではなく、ベテランが実践するテクニックを取り入れることでヒット率が格段にアップします。この章では初心者でも取り組みやすいジグアクションの基本と、経験者が意識している回遊予測のポイントを紹介します。
基本のワンピッチジャークをマスターしよう
ショアジギングの基本テクニックとしてぜひ覚えていただきたいのが、ワンピッチ・ジャークと呼ばれるジグアクションです。これはロッド操作とリール巻取りを連動させて、ジグを小魚が逃げ惑うように泳がせる方法です。やり方はシンプルで、**リールをハンドル1回転させる間にロッドを1回しゃくる(ジャークする)**動作を繰り返すだけです。具体的には、ロッドを下げた状態から素早く30~50cmほど煽り上げ(このときジグがヒュッと跳ね上がります)、すぐにロッドを元の位置に戻しながらリールを1回転巻き取ります。これでジグが「跳ね上がって小魚が逃げる動き→一瞬間を置いて再び動き出す動き」を繰り返すことになり、魚にスイッチが入りやすいアクションになります。
ワンピッチジャークは一見難しそうですが、一定のリズムで繰り返すことで比較的簡単に身につきます。最初はゆっくりめのテンポから始め、慣れてきたらだんだんスピードアップすると良いでしょう。大事なのはジグにしっかりとメリハリのある動きを与えることです。ロッドをしゃくったときにジグがしっかり跳ね上がり、ロッドを戻すときにジグがヒラヒラと落ちる。この一連の動きが1ピッチ毎にきちんとできていれば、魚にアピールできています。初心者の方はまずこのワンピッチジャークをマスターすることが釣果アップへの近道です。青物狙いの基本動作となりますので、ぜひ練習してみてください。
なお、実釣では延々とワンピッチだけを続ける必要はありません。いくつかジャークしたら止めてみる、速度を速めたり遅めたりする、といった変化をつけることも有効です。特に青物は追尾してきて最後の一押しで食わせるケースが多いので、**「3回ジャークして1秒フォール」**のようにパターンを作って誘うのもおすすめです。フォール中に食ってくることもよくあるので、ラインの動きには常に目を配りましょう。
フォール(落とし込み)で食わせるテクニック
ジグアクションの中で見逃せないのが、ジグを沈める動作=フォールを活用したテクニックです。多くの魚は、逃げる小魚が力尽きてフラフラと沈んでいく瞬間に捕食する習性があります。ショアジギングでも、この**「フォールで食わせる」**場面が非常に多いのです。
具体的なテクニックとしては、先述のワンピッチジャークと組み合わせて行うものが一般的です。例えば**「ワンピッチを5回入れたら、一旦ロッドを止めてジグを沈める」という動作を繰り返す方法があります。5回シュッシュッと跳ね上げられて警戒心より捕食本能が勝った青物は、「次にヒラヒラ落ちたら食ってやろう」とタイミングを伺っています。そしてフォールに入った瞬間にガツン!とバイトしてくる、というイメージです。実際、メジロやサワラなどはフォール中のヒットが全体の半分以上**ということも珍しくありません。
フォールで食わせるためには、ジグをしっかりフォールさせる「間」を作ることが大切です。常に動かし続けていると魚もタイミングを掴めません。意図的にカウント2~3秒ほどのフォールを入れることで、魚に口を使わせる隙を与えます。フォール中はラインテンションを保ちつつ、指に伝わるラインの動きや目で見える糸ふけを注意深くチェックしましょう。ひったくるようなアタリだけでなく、ラインがフッと止まったり、斜め前方に走ったりと違和感があれば全てアワせるつもりで臨みます。空アワセでも問題ありません。ヒットしていればグッと重みが乗るはずです。
また、フォールの方法にも二通りあります。ラインを張り気味にしてゆっくり落とす「テンションフォール」と、ラインをフリーにして一気に落とす「フリーフォール」です。テンションフォールはジグが安定してヒラヒラ落ち、魚に違和感を与えにくい利点があります。一方フリーフォールはジグが不規則に暴れるためアピール力が高いですが、絡みやすかったりアタリを取りにくい面もあります。状況によって使い分けましょう。基本はテンションフォールで丁寧に見せ、反応がないときや活性が高そうなときはフリーフォールを混ぜてスイッチを入れる、といった具合です。
潮・風・ベイトの動きから回遊を予測するコツ
ショアジギングで継続的に釣果を上げるには、魚の回遊タイミングをある程度予測する目を養うことが重要です。とはいえ相手は自然ですから絶対はありませんが、いくつかの要素に注目することで「そろそろ来るぞ」と準備を整えることができます。経験者がよく見ているポイントを紹介しましょう。
- 潮の流れ・潮目:淡路島のような海峡エリアでは、潮の流れが魚の活性に直結します。一般に上げ潮・下げ潮で水が動いている時間帯は魚も動くと言われます。特に潮目(異なる潮流がぶつかってできる水面の筋状の模様)にはベイトが集まりやすく、それを狙ってフィッシュイーター(捕食魚)が回ってきます。釣り場に着いたら海面を観察し、沖にできる潮目や流れのヨレを探しましょう。潮目が射程圏内にあるときは狙い目です。また満潮・干潮前後の緩むタイミングは、大型青物がエサを追い込むチャンスとも言われます 。潮汐表を見て潮位変化のピーク前後は特に集中してみてください。
- 風向き・海況:風はキャストのしやすさだけでなく、釣果にも影響します。追い風(後ろからの風)なら飛距離が伸びる利点もありますが、それ以上に風がベイトを寄せる役割に注目しましょう。例えば陸風(陸から海への風)が吹くと表層の水が沖に押し出され、代わりに深層の栄養豊富な水が岸に寄ります。これを嫌ってベイトが散ってしまうこともあります。一方、海風(海から陸への風)は表層のベイトを岸近くに運ぶため、青物が接岸しやすい状況になることが多いです。強風すぎると釣り辛いですが、適度な海からの風は釣果を呼ぶと覚えておきましょう。また海の濁り具合も影響します。雨後で濁りが入ったときは派手めカラーや音のでるルアーを試す、逆に澄み切ったときはよりナチュラルに攻めるなど工夫すると良いです。
- ベイトフィッシュの存在:結局のところ、ベイト(エサ魚)の有無が最も重要です。釣り場に着いたら海面や足元を覗き込み、小魚の群れやナブラがないかを確認しましょう。朝夕にはイワシやアジの小魚が群れてキラキラしているのが見えることがあります。そのようなときは絶好のチャンスで、ベイトのサイズ・色に合わせたジグを選べば高確率でヒットに持ち込めます。逆にベイトの気配が全くないときは、早めに見切って場所替えする判断も大切です。また、釣り場に到着する前に海鳥の動きにも注目しましょう。カモメやウミネコが海面すれすれを旋回していたり、一斉に水面にダイブしている光景があれば、そこには高確率でナブラが立っています。鳥は離れた場所からでも目立つので、車で移動中も空をチェックしてみてください。
こうした自然のサインを総合して、「潮が緩む○時頃にあの潮目が寄ってきそうだ」「風向き的に湾奥にベイトが溜まってそうだ」など仮説を立てながら釣ると、釣果アップのみならず釣り自体がより楽しくなります。たとえ外れても考えたことは無駄になりません。むしろデータを蓄積して次回に活かせます。釣れない時間も海を眺め、状況分析する癖をつければ、あなたも徐々に**「回遊予測が当たる」**アングラーになれるでしょう。
安全に楽しむための装備と注意点
ショアジギングは釣果も大事ですが、何より安全が大切です。特に磯場や足場の高い堤防では、思わぬ事故のリスクがあります。この章では釣行前に揃えておきたい必須装備や、現地での立ち居振る舞いの注意点、そして天候や海況のチェック項目について解説します。万全の安全対策で、安心して淡路島釣行を楽しみましょう。
必須装備
ショアジギングを含む海釣りにおいて、**ライフジャケット(救命胴衣)**は絶対に着用すべき命綱です。特に磯や防波堤から釣る場合、足を滑らせて海に転落する可能性はゼロではありません。万一落水してもライフジャケットが浮力を確保してくれれば、生存率は飛躍的に高まります。近年は国土交通省型式承認の膨張式ライジャケなど軽量コンパクトな製品も普及していますので、必ず身につけてください。堤防によってはライフジャケット着用が利用条件になっている所もあります。
次に滑り止め効果のあるシューズ。磯場ではフェルトスパイク底のブーツ、堤防上でもコケや濡れた藻で滑ることがあるので、ラジアル底よりはフェルトorスパイク底のシューズが安心です。特に磯用のピン付きスパイクブーツは抜群のグリップ力を発揮します。逆に普通のスニーカーや長靴で磯に降りるのは大変危険ですので避けましょう。
**フィッシンググローブ(手袋)**もできれば着用をおすすめします。キャスティング時にPEラインが指に食い込むのを防いだり、大物を素手で掴んだ際のケガ防止になります。青物は暴れるので、取り込む際にフックが外れて手に刺さる事故も起こりえます。厚手のグローブがワンクッションあるだけで怪我のリスクはかなり減ります。さらに装備を挙げるなら、偏光サングラス(海面のギラつきを抑えて足元や魚影が見やすくなる&目を保護)、帽子(転倒時に頭を守る)、小型プライヤー(フック外し用)、ナイフ(ロープやラインを切る緊急用)なども携行しましょう。磯では荷物を最小限にしたいところですが、安全装備は削らないようにしてください。
磯場での立ち位置とキャスト時の注意
磯や防波堤では、釣りに熱中するあまり足元や周囲への注意がおろそかになることがあります。以下のポイントに気を配り、安全に釣りをしましょう。
- 立ち位置の選定:磯ではなるべく平坦で滑りにくい場所を選びましょう。波をかぶった形跡がある岩(海藻が付着しテカテカしている場所など)は潮位が上がると危険です。磯に立つ前に波の様子を数分観察し、大波が来ないか確認してください。足場が低すぎる場所(一発の高波でさらわれるような位置)には決して立たないこと。防波堤でも先端は波をかぶりやすいので、無理せず少し手前で釣る勇気も必要です。
- キャストの前後確認:ルアーを投げる際は、必ず後方と周囲の確認を徹底してください。特に堤防では後ろに人や自転車、釣り人の子供などがいる場合があります。磯でも背後に岩壁や木の枝が迫っているかもしれません。後方確認を怠ってルアーを引っ掛けたり、人に当ててしまうと大惨事です 。周囲に声を掛け合い、「投げまーす!」など合図するのも良いでしょう。狭い釣り座では順番にキャストするなど譲り合ってください。
- ランディング時の注意:魚が掛かった後も気は抜けません。特に磯では足元まで寄せても最後に抜き上げる際にバラしたり、無理に手を伸ばして姿勢を崩すことがあります。大物が掛かったらできればタモ(玉網)を使いましょう。タモ入れに夢中で足元疎か…にならないよう踏ん張りを意識してください。堤防では周囲の釣り人に声をかけてタモを借りたり、助けてもらえる場合もあります。無理せず協力を仰ぎましょう。
- 複数人での位置取り:人気ポイントでは釣り人が肩を並べてキャストすることもあります。こうした場合、斜め前への斜めキャストは厳禁です。他人のラインとお祭り(絡まる)してしまう原因になります。基本は真正面に遠投しますが、潮でラインが流れることもあるので、お互い声を掛け合いながら釣り座を調整しましょう。また自分がファイト中は左右の人は一旦仕掛けの回収を。逆に隣の人にヒットしたら自分は仕掛けを上げてファイトの邪魔にならないようにするのがマナーです。
釣行前に確認すべき天候・潮位情報
釣りに出かける際は、当日の天気と海の状況を必ずチェックしましょう。自然相手のレジャーでは、予測と準備が身を守ります。
- 天気予報:雨の有無はもちろんですが、特に風予報と波浪予報は重要です。風速5m/sを超えるようだとラインが煽られて釣り辛く、10m/sを超えると危険領域です。風向きも先述の通り釣果に影響するので把握しておきます。また波浪では波高1.5m以上の予報なら高波に警戒が必要です。2mを超える予報なら無理せず中止する判断も大切です。磯釣りの場合、前日までのうねりが残っているケースもあるので現地の海況も一目見て異常な波が来ていないか確認してください。
- 潮汐・潮位:潮見表で釣行時間帯の潮位変化をチェックしましょう。特に磯では、干潮時には行けた場所が満潮で帰れなくなる事態もあり得ます。潮位差が大きい日(大潮)は要注意です。事前に満潮時の写真や情報をネットで調べ、その磯が冠水しないか把握しておくと安心です。また潮回りによって釣りやすさも変わります。例えば激流ポイントの翼港では小潮の日を狙うと比較的釣りやすいなどの傾向があります 。淡路島釣行に慣れてきたら、潮回りも釣果情報と照らし合わせて記録しておくと良いでしょう。
- 日出・日没時刻:これも見逃せません。ショアジギングでは日の出前後1時間程度がゴールデンタイムになることが多く、早朝から釣り場に入る釣り人が多いです。暗いうちから行動する際はヘッドライトを用意し、足元に十分注意してください。日没後に撤収する場合も、辺りが暗くなる前に片付けを始めるのが安全です。初めて行く場所では特に、明るい時間帯のうちに帰路の確認を済ませるよう意識しましょう。
安全確認と聞くと堅苦しく感じるかもしれませんが、**「備えあれば憂いなし」**です。安心して釣りに集中するためにも、天候・海況のチェックとそれに応じた準備を習慣化してください。淡路島の自然は豊かで時に厳しいですが、しっかり備えていれば私たちに最高の釣り体験を与えてくれるでしょう。
釣った青物を美味しく食べる!下処理と保存法
ショアジギングの醍醐味は、自分で釣った新鮮な魚を味わうことにもあります。特に青物は釣りたてなら刺身は絶品ですし、料理のレパートリーも豊富です。ただし美味しく食べるためには現場での下処理と鮮度管理がとても重要になります。最後に、釣れた青物を最高の状態で持ち帰り、美味しくいただくためのコツを紹介しましょう。
青物の正しい締め方と血抜き方法
釣った魚はできるだけ早く〆めて鮮度を保つのが鉄則です。青物は特に血が多い魚なので、しっかり血抜きするか否かで味に大きな差が出ます。基本的な締め(しめ)手順は次のとおりです 。
- 魚を気絶・瞬殺させる(脳締め) – 魚が生きているうちに、まず脳に傷を入れて即死させます 。ブリやサワラクラスなら、目の後方にある急所めがけてナイフやフィッシュピックを刺し、脳を破壊します 。暴れる場合はタオルで目を覆うと落ち着きます 。
- 血管を切る(エラ切り&尾切り) – 次に魚の大きな血管を切断し血抜きを行います。エラ蓋を開けてエラの付け根(中骨の下あたり)に刃先を入れ、太い動脈を切ります 。左右のエラ両方切るとより確実です。続いて尾の付け根にも切れ目を入れ、尾側の血管も断ち切ります 。
- 血抜き – 血管を切ったら、魚をバッカン(桶)や海水の入ったクーラーに浸けて血を抜きます 。魚の頭と尾を持って曲げたり伸ばしたりすると、ポンプのように血がどんどん出ていきます 。血がある程度抜けきったら、海水でしっかり魚体を洗い流してください 。ここまでやれば筋肉内の血もかなり排出され、生臭さや腐敗のリスクがぐっと減ります 。
以上がいわゆる「活け締め+血抜き」の方法です。難しそうに思えますが、慣れれば数分でできますし、何より持ち帰った魚の美味しさが段違いになります。特にブリやカンパチなど大型青物は血抜きをしないと血合いが黒ずんで鮮度落ちが早いので必須と言えます 。「釣ったらすぐ締めて血を抜く」はぜひ実践してみてください 。なお、もし神経締め(ワイヤーを通して神経も破壊する高等テク)が可能なら挑戦してみても良いですが、難易度が高いのでまずは基本の脳締め+血抜きで十分です。
クーラー管理と氷の使い方
血抜きまで済んだ魚は、できるだけ早く冷やして鮮度をキープします。ただし闇雲に冷やせば良いというものでもなく、ポイントがあります。
- 冷やしすぎない:魚は冷やしすぎると身が固くなりやすく、せっかく遅らせた死後硬直が早まってしまいます 。血抜き直後に氷水にガンガン浸けっぱなしにするのは実は逆効果です 。理想を言えば、最初は海水+氷の「塩氷」で急速冷却し、その後は氷水から魚体を出して適度に冷やす、というのがプロのやり方です 。
- 魚を直接氷水に触れさせない:クーラーボックスで持ち帰る際、魚が溶けた水に浸かりっぱなしだと、水っぽくなったり旨味が流出する恐れがあります 。おすすめは、魚を大きめのビニール袋に入れて密閉し、さらに新聞紙などで包んでから氷と一緒に入れる方法です 。こうすれば魚は濡れず空気にも触れず、それでいてしっかり冷やせます 。簡易的には、こまめにクーラー内の海水を捨てて氷だけで冷やすだけでも違います 。
- 十分な量の氷を用意:夏場は特にですが、大きな魚ほど冷やすのに氷がたくさん必要です。クーラーには余裕を持った氷を入れて持参しましょう。万一氷が融けて足りなくなりそうなら、途中でコンビニ等に寄って追加購入することも検討してください 。氷なしで持ち帰るのは論外です 。
クーラーボックスは断熱性の高いものほど氷が長持ちします。釣り専用のものが望ましいですが、無ければホームセンターで売っている発泡スチロールの箱に氷詰めでも代用できます。とにかく魚を適温(0~5℃くらい)に保つことを心がけてください。家に着くまでが遠足、ではなく釣りでは家に着くまでが釣りと言われる所以です。
おすすめレシピ(刺身・漬け丼・塩焼き)
さて、こうして持ち帰った新鮮な青物。ぜひ美味しく料理していただきたいものです。最後に初心者でも挑戦しやすいおすすめレシピを3つ紹介します。
- 刺身:何と言っても釣りたての青物は刺身が最高です。ブリやハマチなら身がプリプリで甘みがあり、サゴシ(サワラ)なら淡白ながら上品な味わいです。釣ってすぐ締めた魚は身が硬直している場合があるので、一晩寝かせるとさらに旨味が増しますが、待ちきれなければ当日でもOK。ポイントはしっかり血合いを取り除くことと、身を冷やし気味で切ることです。血合いの部分は臭みの原因になるので包丁でそぎ落とし、身はキンキンに冷やしたまな板で切るときれいにお刺身になります。ハマチの刺身にはワサビ醤油に少しおろしショウガを混ぜても美味しいです。
- 漬け丼:刺身用に切った青物の切り身を、特製ダレに漬け込んでご飯に乗せる漬け丼も絶品です。醤油・みりん・酒を1:1:1程度に合わせ、お好みでショウガやゴマを少々加えた漬けダレを用意。そこに刺身を10~15分ほど漬け込みます。あとはアツアツのご飯に乗せるだけ。ブリやハマチの漬けは照り焼きとは一味違うコクが出て、ご飯が何杯でも進みます。卵黄を乗せたり、刻み海苔や大葉を散らすと見た目も風味もアップ。釣行で疲れた体にもするする入るので、釣り人飯としておすすめです。
- 塩焼き:青物というと刺身のイメージが強いですが、シンプルな塩焼きもぜひ試してみてください。特にサゴシ(サワラの若魚)は西京漬けなどにもされるように焼き物に向いています。三枚おろしにして食べやすい大きさに切った切り身に塩を振り、グリルやフライパンで香ばしく焼き上げます。皮目からじっくり焼くとパリッと仕上がります。余分な脂が落ちて身はふっくら、レモンを絞ればさっぱりいただけます。ブリもカマ(エラの後ろ部分)は塩焼きすると絶品です。濃厚な脂に塩味が染みて、日本酒のお供にも最高ですよ。
この他にも、ブリならブリ大根や照り焼き、サワラなら味噌や粕に漬けて焼く幽庵焼き、ハマチならフライや南蛮漬けなど、枚挙にいとまがありません。釣って楽しく、食べて美味しいのが釣りの醍醐味です。ぜひ色々なレシピに挑戦して、淡路島の海の幸を堪能してください。
まとめ
この記事では、淡路島ショアジギングの基本と実践方法について解説しました。最後に重要なポイントを振り返っておきましょう。
✅ 初心者でも堤防から大物青物を狙える – 淡路島は潮通しが良くベイトが豊富なおかげで、ツバスからブリ級まで青物の魚影が濃いフィールドです 。適切なタックルを揃え基本アクションをマスターすれば、初心者でも岸から大物ヒットのチャンスがあります。
✅ 季節に合わせたルアー選びと戦略が釣果を左右する – 春はサゴシやハマチ、夏はタチウオや小型青物、秋はブリ・メジロ、冬は根魚やヒラメと、ターゲットが移り変わります。それぞれの季節で有効なジグの重さ・カラーやアクション、狙う時間帯を押さえておくことでヒット率が格段にアップします 。
✅ 安全対策とマナーの徹底で誰でもショアジギングを楽しめる – ライフジャケットや滑り止めシューズの装備、キャスト時の後方確認や釣り場のルール遵守など、安全とマナーを守ることが何より大切です 。準備を万全にすれば、磯でも堤防でも安心してショアジギングに挑戦できます。
この記事を参考にすれば、あなたも淡路島の海でショアジギングを安心して実践できるはずです。釣れた青物はしっかり締めて持ち帰り、刺身や漬け丼で味わえば格別の美味しさですよ。次の週末はぜひ淡路島へ足を運んで、一度その朝マヅメの興奮と大物ヒットの手応えを体感してみてください!きっとあなたのアウトドアライフがもっと豊かで刺激的なものになります。最後までお読みいただきありがとうございました。釣行の際は安全第一で、淡路島ショアジギングを存分に楽しんできてくださいね。釣果アップとご安全をお祈りしています!


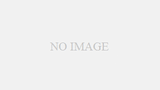
コメント