「釣り堀で青物を狙ったけど、途中でバラしてしまった…」「他の人は釣れているのに、自分だけ釣れない…」そんな経験はありませんか?青物(カンパチ・ブリ・ハマチ)は引きが強く、釣り堀でも大人気のターゲットですが、その引きの強さゆえにバラしやすく、初心者には難易度が高い魚でもあります。実際、青物を確実に釣るにはコツが必要で、何も知らずに挑むと悔しい思いをすることも多いでしょう。
釣り堀で青物をゲットした瞬間。強烈な引きは初心者には驚きですが、その分釣り上げた時の喜びも格別です。
とはいえ、ポイントさえ押さえれば初心者でも青物を釣る確率をグッと上げることができます。本記事では「初心者でも青物を確実に釣るための方法」を徹底解説!仕掛け選びからエサの使い方、誘い方やアワセのコツまで、実践的なテクニックをまとめました。青物釣りの基本を学んで、釣り堀で憧れの大物を手にしましょう。
青物の特徴と釣り堀での動き方
青物の生態と習性
まず青物の生態と習性を理解しましょう。青物(ブリやカンパチ類)は回遊性が高く、群れで水槽内(生簀)をグルグルと移動します。一箇所に留まらず活発に泳ぎ回るため、タイなど他の魚に比べて活性(食欲や反応)のムラが大きいのが特徴です。機嫌が良い時は猛烈にエサに食いつきますが、機嫌が悪い時はエサを目の前に落としても無視されることもあります。
釣り堀内での動き方
釣り堀内での青物の動き方にもパターンがあります。魚が放流された直後は、お腹を空かせていることが多く活発にエサを追い回します 。生簀に放たれる前にエサ抜き(絶食)されている場合もあり、放流後は一気に活性が上がるのです 。このタイミングでは表層付近まで青物が上がってきてエサを追う姿も見られます。しかし時間が経つにつれて次第に活性が落ち着き、青物たちは深場や生簀の隅のほうへ移動しがちです。特に何度かエサを食べて満腹になると、表層近くを規則正しく回遊するだけでエサに見向きもしなくなることがあります。このように円を描くようにのんびり表層を泳いでいるときは食い気が低い証拠で、狙ってもなかなか釣れません 。
また、青物の活性は潮の流れ・水温・時間帯によっても変化します。海上釣り堀の場合、潮が動くと水中に酸素や匂いが行き渡り魚の活性が上がりやすいです。逆に潮止まりで水が淀んでいるときは動きが鈍くなりがちです。水温も重要で、適水温の春秋は活発ですが、真夏の高水温時や冬の低水温時は動きが鈍くなります。釣り堀ではこうした要因で青物の活性が刻々と変わるため、「今魚がどんな様子で泳いでいるか」をよく観察し、その動きに合わせて釣り方を工夫することが大切です。
釣れる時間帯やシーズン
釣れる時間帯の狙い目
狙い目の時間帯は大きく三つあります。まず朝イチ(釣り堀開始直後)。前日からプレッシャーがリセットされ、一晩空腹になった魚が口を使いやすい時間帯です。朝一番はマダイ狙いが定番とも言われますが、実は青物も朝から十分チャンスがあります 。遠慮せず開始早々に青物を狙ってみる価値はあるでしょう。ただし、乗合(他のお客さんと同じ生簀)では、自分だけ朝から青物を掛けると周囲に仕掛け回収をお願いすることになるため、状況を見て判断してください 。
次に放流直後です。多くの海上釣り堀では決まった時間に青物の追加放流がありますが、その直後はまさに絶好のチャンス!放流された青物は空腹で活性が高く、餌を探して生簀内を縦横無尽に駆け回ります 。このタイミングを逃さずエサを投入すれば、ヒット率が格段に上がります。実際に「朝から全く青物の気配がなかったが、放流後に活性が上がり連続ヒットになった」という報告もあります 。放流直後は生簀全体の青物の活性が上がり、1匹釣れると次々とヒットする場合もあるのです 。興奮した青物が仲間のヒットした魚を追って連鎖的に食いつくことも珍しくありません。そのため放流直後は一気に勝負をかけ、手返し良く狙うようにしましょう。
放流直後の生簀では青物が一斉に動き出します。釣り堀スタッフが魚を放つと、空腹の青物たちが水面近くまで浮いてエサを探し始めます 。このチャンスにエサを投入すれば高確率でヒットにつながるでしょう。
そして夕方(終了間際)も狙い目です。一日の終わり頃になると、朝方ほどではないにせよ魚の活性が上向く傾向があります。特に日が傾き始める頃は、青物が再び表層付近に現れやすくなる時間帯です。これは夕まずめのフィーディング(捕食行動)とも言え、自然界で夕暮れに餌を食べる習性が影響しているとも考えられます。釣り堀でも夕方に青物をヒットさせた例は多く、諦めずに粘った末にようやくヒットすることもあります。
季節ごとの傾向
シーズン別の傾向も押さえておきましょう。一般的に春と秋は水温が適温で青物の活性が高く、釣果が上がりやすい時期です。春先は冬場餌をあまり食べなかった魚が活発に動き始め、秋は産卵を控えてエサを盛んに食べるため活性が上がります。反対に夏と冬は活性が落ち込みやすいです。夏の真昼間は水温上昇と酸欠気味で魚もバテ気味になり、表層に青物が見えていても口を使わないことが増えます。冬は水温低下で魚の代謝自体が落ち、エサへの反応が極端に鈍くなります。
活性が低い渋い状況では釣り方を工夫しましょう。基本は「じっくり待つ」か「攻めの釣り」の二択です。魚の活性が低いときは動くエサよりも、むしろじっと目の前に留まるエサに食いつくことがあります。例えば真冬や真夏の青物は、活きたアジを泳がせていても追わない代わりに、ゆっくり沈むイワシの切り身を底近くに放置しておいたら食った…というケースもあります。一方で、活性が低い時でもリアクションバイト(反射的な食いつき)を狙って攻めの誘いを入れる手もあります。エサを小さく刻んでこまめに動かし、嫌でも魚にアピールし続けてスイッチを入れる作戦です。状況に応じて待ちと攻めを切り替え、辛抱強く探ってみましょう。渋い時間帯でも一瞬活性が上がるタイミングがあるので、そのチャンスを逃さないことが重要です。
仕掛けの選び方(ウキ釣り・ミャク釣り)
青物狙いでは主にウキ釣り(浮き釣り)とミャク釣りの二通りの仕掛けが使われます。それぞれ特徴があり、状況に応じて使い分けることで釣果アップにつながります。
ウキ釣りの特徴と使い方
ウキ(浮き)仕掛けは、決めたタナ(深さ)にエサを留めておけるので、青物が泳いでいるレンジに的確にエサを届けられるのが強みです。ウキ下(ウキからハリまでの長さ)を調整して魚のいるタナに合わせることが重要で、これを怠ると青物にエサを届けられません。またウキがあることでアタリ(魚がエサを食った動き)が目で見てわかるので、タイミングを取りやすい利点もあります。青物狙いの場合、ウキ釣りではやや重めのオモリを付けてエサが狙った深さまで素早く沈むようにすることが多いです。他の人とのオマツリ(オマツリ=仕掛けの絡み)を防ぐためにも、活きエサ使用時は6~10号程度の重りで確実に沈めるなど工夫します 。ウキ釣りではエサを漂わせつつ時折ウキごと動かして誘いをかけたり、逆に風や潮に任せて自然に流したりと、エサの動かし方もテクニックになります。
ミャク釣り(ノーシンカー・ズボ釣り)の特徴
ミャク釣りとはウキを使わない釣り方で、海上釣り堀ではハリス(ハリの付いた糸)とオモリだけのシンプルな仕掛けを指すことが多いです。特にオモリを付けずエサの重さだけで自然沈下させる「ノーシンカー」や、オモリを付けてもウキなしで真下に沈める「ズボ釣り」といった方法があります。ミャク釣りの最大の利点はエサを自然に漂わせられることです。ウキがない分エサの動きが自由で不自然さが少なく、スレた青物にも口を使わせやすい場合があります。例えば活きアジの泳がせ釣りでは、ウキを外してアジの泳ぐままに任せると警戒心の強い青物がヒットすることもあります。ただしウキがない分アタリは手元に伝わる「ミャク」で感じ取る必要があり、明確に穂先に出るまで分かりづらい欠点もあります。またタナを固定できないので、青物の泳層が合っていないとエサはどんどん沈んでいってしまいます。そのため、ミャク釣りをする際も一度タナ取りオモリなどで底までの深さを測っておき、狙うレンジを決めておくと良いでしょう 。
仕掛けの使い分け
仕掛けの使い分けとしては、表層~中層で青物が餌を追っているときはウキ釣りが適しています。ウキで広範囲を探りつつ誘いも入れやすく、活性が高い青物には効果的です。一方、魚が沈み気味で底付近にいるときや、ウキに見慣れてスレてしまったような状況ではミャク釣り(ノーシンカー)でナチュラルにエサを落とし込む方が有利なことがあります。状況によってはウキ仕掛けとミャク仕掛けの二本竿を用意し(釣り堀のルールで許される場合)、様子を見ながら使い分ける上級者もいます。初心者の方も両方のメリットを知ったうえで、その日の状況に合った仕掛けを選択してみてください。
おすすめのエサとその使い方
青物が好むエサの種類
青物が釣り堀で好んで食いつくエサには定番があります。大きく分けて**活きエサ(生きた餌)と死にエサ(冷凍・生餌)**です 。青物狙いの代表的な活きエサはアジやウグイ(銀平)、イワシなどの小魚です。そのほか稚アユ(小さいアユ)やニジマス、金魚が使われることもあります。一方、死にエサ(冷凍エサ)ではカツオの切り身、サンマ(秋刀魚)の切り身、イワシの丸ごとや切り身、サヨリ、キビナゴ、さらには小イカ(ヒイカ)など多彩です 。釣り堀によってはエビや貝のむき身、練り餌(団子状の餌)も販売されており、青物がそれらに反応するケースもあります。
青物用エサのローテーションも重要です。まず活性が高いときは動きのある活きエサが最も効果的なことが多いです。放流直後や朝イチで魚の活性が明らかに高い場合、まずは活きアジなどを投入して反応を見るとよいでしょう 。活きエサが水中を泳ぎ回る刺激に青物がスイッチONになり、豪快に食ってくることがあります。反対に、活きエサを入れてもまったく追わない場合は魚の活性が低い証拠です。そのときは冷凍エサへ切り替えて様子を見るのが鉄則です。「今日はアジには見向きもしないけど、イワシの切り身に替えた途端に当たりが出た」ということは日常茶飯事なので、活きエサと死にエサの両方を準備しておき、反応の良い方を探っていきます 。実際「活きエサに反応がない日はカツオやサンマばかり当たる」というように日によって嗜好が偏ることもあります。また青物は基本的に動くエサに反応する習性があります。たとえ死にエサを使う場合でも、ただじっと置いておくより竿先を小さくしゃくってエサを動かしたり、ゆっくり誘い上げてヒラヒラと落とし直したりと、こまめな誘いを入れた方がヒット率は上がります 。
エサの付け方のポイント
エサの付け方も見落とせないポイントです。青物は餌を丸呑みするイメージがありますが、エサの付け方が悪いと違和感を与えて途中で吐き出されたり、肝心のハリが魚の口に掛からなかったりします。活きエサの場合はできるだけ長く弱らず泳ぐように付けるのが鉄則です。一般的には鼻掛け(上顎と鼻の間にハリを刺す)や唇掛け(上顎または下顎にハリを通す)が推奨されます。こうすることでエサの魚は泳ぎやすく、青物に追われたときも自然に逃げる動きを演出できます。背中にハリを刺す「背掛け」は泳ぎは派手になりますが弱りやすいため、釣り堀ではあまり使われません 。一方、イワシやサンマの切り身など死にエサの場合は、身が千切れないようにしっかりハリに刺す必要があります。基本はエサの先端付近にハリを通し、エサがずれにくくしておきます。例えばサンマの切り身なら皮側からハリを刺して皮一枚を残して抜くと、身がホールドされ外れにくくなります。ただしハリを深く埋め込みすぎると肝心のハリ先まで身で隠れてしまい、フッキングが決まりにくいので注意しましょう。「針先は少し出す」が基本です。
釣り堀で販売されている練り餌(ペースト状の配合餌)で青物を釣る方法もあります。練り餌は本来マダイやシマアジ狙いに使うものですが、青物がスレて何も食わないとき、不意に練り餌に食いつくことがあります。特に養殖場育ちの青物は配合飼料に慣れているため、練り餌のニオイや味に反応する個体もいるのです。練り餌を使う場合は大きめの団子にしてハリを中に埋め込み、ゆっくり沈めて待ちます。食わせるコツはあまり動かさずじっと我慢することです。青物釣りの引き出しの一つとして、覚えておくと良いでしょう。
誘い方とアワセのコツ
誘い方の基本
青物の食いつきを良くする誘い方にはいくつかパターンがあります。基本は「エサを動かして魚に気づかせる」ことです。活性が高い時なら放っておいてもエサを見つけてくれますが、渋い時ほどこちらから存在をアピールする必要があります。具体的には、竿先を上下に小さく動かしてエサを泳がせる/踊らせるのが効果的です。ウキ釣りであればウキをポンポンと引いてエサを上下させたり、ゆっくり引きずって横方向に動かしたりしてみましょう。ミャク釣り(ノーシンカー)であれば、いったんエサを回収して再度ゆらゆらと落とし直す「誘い落とし」や、底まで沈めてから少し巻き上げてまたフリーフォールさせる動きなどが有効です。青物は目ざとく動くものを見つけ追尾する習性がありますので、この本能を刺激するイメージです。
誘いを入れる際の動かし方の強弱も状況次第で変えましょう。魚の反応パターンは大きく二通りあります。ひとつはエサがピタッと止まった瞬間に食わせるパターン。もうひとつはエサがフワッと落ちていく動きに反応して食わせるパターンです 。例えばウキ下1mで止めたエサをじっと見つめている青物には、小さく誘いを入れてエサを動かした後、再び止めてみます。動いた途端に本能的に口を使うケースがあるからです。一方で、水面近くまで追ってきたのに食わない魚には、エサを一度沈め直してゆっくり落としてやるとフッと食いつくことがあります 。このように、その時の青物の反応を見ながら「動かして止める」「落としてみせる」を織り交ぜ、最適な誘いを探ってください。もちろん誘いを入れすぎてエサが外れてしまっては逆効果なので、エサの様子を見つつ加減することも大事です。
アワセのタイミング
一番難しく感じるかもしれないアワセ(合わせ)のタイミングです。青物釣りでは「早アワセ厳禁、遅アワセ気味」が基本と言われます。青物はエサを咥えてから一気に走る習性があり、最初の走りでハリ掛かりさせるイメージだからです。ウキ釣りの場合、ウキが「スッ!」と消し込まれても、すぐには合わせず一呼吸置きます。糸がギューンと走る、あるいは竿先がグッと入るのを見てから、満を持して大きく竿を立ててアワセを入れましょう。ミャク釣りの場合も、魚が食った瞬間にビクッと反射的に合わせるのではなく、ラインがスーッと走り出すのを指で感じ取ってから思い切り竿を煽ります。この遅めの大アワセで青物の硬い口元にもハリがしっかり貫通し、バラシが減ります。実際、「ハリが魚の口にしっかり入ったのを確認してから大きくアワせる」のがコツだと解説する釣り人もいます 。早く合わせすぎるとハリが口に掛からずエサだけ取られてしまうので注意しましょう。
ファイトに入ったら、青物の強烈な引きに慌てず対処します。まずドラグの調整が重要です。最初の突っ込みで糸が一気に引き出されますが、このときドラグ(リールの糸の出る強さ)が適切に緩んでいないと、ラインブレイク(糸切れ)や針伸びの原因になります。青物が走るときは無理に止めず、ドラグを滑らせて走らせてあげましょう。ドラグ音を「ジーーーッ」と鳴らしつつ、ロッドはしっかりと曲げて耐えます。魚が止まったらこちらのターン。ロッドを立てたままリールを巻き、魚を手前に寄せていきます。再び突っ込んだらまた耐える、という**「出されては巻き取る」**攻防を繰り返して少しずつ距離を詰めます。青物は何度か強い突っ込みを見せますが、ドラグ調整さえ良ければ切られることはありません。逆に興奮してドラグを締めすぎたり、ロッドを下げてしまったりすると急激な負荷でラインが切れるので気を付けてください。
ファイト中は周囲への配慮も大切です。青物がヒットしたら大きな声で「青物来ました!」などと周りに知らせましょう 。他の人は仕掛けを上げて待つルールですので、お互い気持ちよく釣りをするためにも声掛けはマナーとして行います。また、自分の魚が他人のラインに近づきそうなら「すみません、下通ります!」など伝えて、ラインをまたがせてもらうなど協力してもらいましょう。無事に魚が弱って浮いてきたら、最後はタモ(網)入れです。大物なので自分でタモ入れせず、スタッフや近くの人にお願いした方が確実です。魚の頭を水面に出さないようにリードし、タモに誘導してもらいましょう。ネットに収まったら勝利です!ここまでくればもうバラす心配はありません。思い切り喜んでOKです。
釣れない時の対処法
どれだけ腕が良くても、青物が全然釣れない「地合い」が存在します。そんなとき焦って同じことを繰り返すより、いくつか手を打つべき対処法があります。
タナの微調整
青物は群れで行動し、その群れごとに泳ぐレンジ(深さ)が刻々と変わります。さっきまで表層近くでバシャバシャしていたのに急に静かになった…という時は、群れが沈んだ可能性があります。そんなときはウキ下を1m深くしてみる、あるいは逆に浅くしてみる、とこまめにタナを調整しましょう。実際「青物を釣るにはタナを見極めることが重要」です 。魚の泳層がズレていたらどんな名人でも釣れないので、まずは正しいタナにエサを届けることが第一です。また、生簀内で青物が泳いでいる姿が見えない場合は迷わず底~中層付近を狙ってください 。逆に青物が表層付近に見えているときは、思い切って浅いタナにしてみる価値があります。ただし先述の通り、表層を規則正しく回遊しているだけの場合は食わないことも多いです 。その場合は無理に浅場を狙うより、割り切って底近くでマダイでも狙いながら機を待つのも手です。青物釣りでは「見えている魚は釣れない」こともある、と心得ましょう。
エサのローテーション
釣れない時はエサを疑え、というくらいエサの変更は効果があります。たとえば周りが活きアジで釣れているのに自分だけ釣れないとしたら、自分のアジのサイズが大きすぎたり弱っていたりしないか確認します。青物が小さめのエサにしか反応しない日もありますし、逆にアピールの弱いエサには見向きもしない日もあります。エサのアピール強弱を変えてみるのも大事です。イワシのように匂いと油分が強いものから、キビナゴのように小さく淡白なものまでローテーションし、ヒットパターンを探ります。例えば、それまでカツオの切り身を使っていたなら、思い切ってニジマスなどの活きエサに変えてみる、といった感じです。また、エサの付け方も再チェックしましょう。せっかく良いエサを使っても、ハリに違和感がある付け方だと魚は吐き出してしまいます。柔らかいエサなら刺し方を変えてみる、活きエサなら弱っていないか確認するなど、細部も見直してください。
ルアーOKならルアーも試す
釣れない状況を打破するには、普段と違うアプローチを試すのも有効です。たとえばルアーを試すのも一つの手段です。海上釣り堀によってはルアー使用OKの所もあります。メタルジグやトップウォータープラグを投げてみると、死んだエサに見向きもしなかった青物が突然スイッチが入って食ってくることがあります。ただし周囲とのお祭りには十分注意しましょう。また練り餌で狙うのも裏技です。特に人が多くプレッシャーの高い日は、意外なエサに反応することがあります。「まさか青物がこんな練り餌で?」というケースもあるので、ダメ元で試してみる価値はあります。
周囲の状況を観察する
釣り堀では自分以外の動向にも目を配りましょう。他のお客さんが青物をヒットさせたときはチャンスです。その場では自分も一旦仕掛けを回収し、魚がネットに収まるまで待機しますが 、直後にすぐ仕掛けを投入できる準備をしておきます。ヒットした魚を追ってもう一匹の青物が興奮していることがあり、ネットイン後に仕掛けを入れると高確率でそいつが食ってきます 。事実、「自分の仕掛けに反応がなくても、生簀内の誰かが青物を掛けているときは諦めず様子を見るべき」との助言もあります 。他人のヒットも自分のチャンスに変える、この発想を持っておくと釣果に差が出ます。
以上のように、「釣れない…」と感じたらタナ・エサ・釣り方の三点を柔軟に変えてみてください。青物は一瞬の判断で状況が好転することが多々あります。様々な引き出しを用意して臨機応変に対応しましょう。
.釣った青物の持ち帰り・食べ方
苦労の末に釣り上げた青物、どうせなら最高の状態で持ち帰って美味しく味わいたいですよね。最後に、釣った青物の締め方と美味しい食べ方について触れておきます。
締め方の基本
まず鮮度を保つための締め方です。青物は大きく力も強い魚なので、釣り上げた後そのままクーラーに入れるだけでは身が暴れて傷んでしまいます。オススメは釣れたらすぐ活き締め(活締め)すること。具体的には、魚の脳天にキリやナイフを刺して即死させ(または延髄を断つ)、次にエラぶたを開いてエラや尾の付け根を切り血抜きをします。血を抜いたら海水を張ったバケツなどで魚を洗い、その後たっぷりの氷で氷締めします。氷水に浸けて急速に冷やすと身の鮮度が長持ちします。海上釣り堀によってはスタッフが締め作業を代行してくれたり、氷を用意してくれているところもありますので、サービスがあれば利用すると良いでしょう。自分で行う場合も難しい作業ではありませんが、周囲の安全に配慮しつつ手早く行ってください。
おすすめの食べ方
持ち帰った青物は是非美味しくいただきましょう。新鮮な青物は刺身が絶品です。ただし釣りたて当日よりも、冷蔵庫で熟成させて1~2日置いた方が身に旨味が増すと言われます(特にブリ系は寝かせた方が美味しいです)。もちろん、釣りたてのコリコリ食感が好きな方は当日でもOKです。刺身にする際は血合いや骨を丁寧に取り除き、薄造りよりはやや厚めに切ると青物の味がしっかり楽しめます。
冬の寒ブリ(ブリの成熟個体)の刺身はまさに絶品。釣り堀で釣った青物も、適切に締めて持ち帰れば新鮮そのものの刺身を味わえます。脂が乗った身は照りがあり、美しいオレンジ色をしています。
刺身以外にも塩焼きや漬け丼などもオススメです。カンパチやブリのカマ(エラ下の部分)は塩焼きにすると脂がのって最高です。身の部分は醤油ダレに漬け込んで「漬け」にすれば、翌日以降でも美味しくいただけます。漬けにした切り身をご飯に乗せれば即席の漬け丼に。薬味にゴマやシソ、刻み海苔を散らすとお店顔負けの逸品です。また、青物は煮付けや照り焼き、フライにしても美味しく、まさに捨てるところなしの高級魚と言えます。せっかく釣った青物ですから、家に帰ってからも存分に堪能してください。
まとめ
釣り堀での青物釣りは難易度が高い分、攻略しがいがあり、釣れたときの喜びはひとしおです。「回遊ルートとタナを見極めることが重要!」という言葉の通り 、まずは青物の泳いでいる層を的確に捉えることが釣果への近道です。その上でエサや誘い方を工夫し、魚の活性に合わせた対応を心掛ければ、初心者でも青物の引きを味わえるチャンスが必ず巡ってきます。
最後に、念願の青物を釣り上げた際はしっかりと締めて鮮度を保ち、美味しくいただきましょう。釣った魚を自分で調理して食べるのも釣りの醍醐味です。存分に釣り堀の青物釣りを楽しみ、そして最高の一皿を味わってください!お疲れ様でした。釣果アップを祈っています。


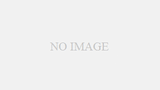
コメント