海上釣り堀でマダイを狙ってみたものの「全然釣れない…」と悩んでいませんか?実は釣り堀とはいえ、何も考えず普通の釣りと同じようにエサを放り込んでいるだけでは、なかなか釣果が上がらないものです 。釣り堀には釣り堀ならではのコツや釣り方があり、それを知らないとせっかく放流された魚も思うように釣れません 。この記事では初心者でもマダイを釣れるようになるためのポイントを解説します。釣り堀特有のテクニックを学べば、今まで釣れなかった人でもきっとマダイが釣れるようになります!
真鯛の特徴と釣り堀での動き方
マダイ(真鯛)は警戒心が強い魚として知られます。特に大きな個体になるほど用心深くなり、小型のうちは群れで行動しますが、大型になると単独行動が増える傾向があります 。釣り堀にいるマダイも周囲の状況をよく観察しており、不自然な動きや激しいアクションには警戒して口を使わなくなることがあります 。
釣り堀内でのマダイの動きにもパターンがあります。放流直後は環境に慣れていないこともあり活発にエサを追い回し、イケス(生け簀)の中を泳ぎ回ります 。特に朝一番の放流直後などはマダイの活性が非常に高く、チャンスタイムになります 。しかし時間が経つにつれマダイは次第に底付近に定位(待機)することが多くなります。日中は水温が安定した底層に留まる魚が多く、マダイも底近くでじっとしているケースが増えます 。このため、釣り堀では時間帯によってマダイの泳層が変化しやすい点を押さえておきましょう。
釣れる時間帯やシーズン
時間帯では、朝イチ(釣り堀開場直後)と放流直後がもっとも狙い目です。マダイは朝方に活発にエサを追う習性があり、釣り堀でも開場直後のいわゆる「モーニングタイム」は絶好のチャンスとなります 。同様に、魚を追加放流した直後も魚の活性が一気に上がり、エサへの反応が良くなるため見逃せません 。夕方の閉場前後も日中より水温が下がり始めて魚の動きが良くなる傾向があるため、朝と夕方の涼しい時間帯を狙うのが賢明です 。逆に日中の真夏の直射日光下では魚の動きが鈍くなることが多いので、暑い時間帯は休憩しつつ朝夕に集中すると良いでしょう。
シーズン(季節)によっても釣れやすさは変わります。一般的に春と秋はマダイの活性が高くエサをよく食べるシーズンです。春先は水温の上昇につれて魚たちが冬眠状態から目覚め、マダイも産卵前でエサへの反応が良くなります 。秋も冬に備えてマダイを含む魚が積極的にエサを摂る時期で、マダイは脂がのって味も良く、釣りやすい季節です 。一方、夏と冬は環境が過酷で魚の活性が下がりがちです。真夏は水温が高すぎる日中に魚がバテ気味になったり、逆にエサが豊富で満腹になりやすかったりして食い渋る傾向があります。冬は水温低下で魚全体の動きが鈍くなり、活発にエサを追いにくくなります 。冬場のマダイは寒さに強いとはいえ 、やはり反応は春秋に比べると渋めです。夏は朝夕の涼しい時間、冬は日中の暖かい時間帯を選ぶなど、季節に合わせた釣行計画を立てることが大切です。
仕掛けの選び方(ウキ釣り・ミャク釣り)
釣り堀でマダイを釣るには、大きく分けてウキ釣り(浮き釣り)とミャク釣りという仕掛け・釣法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、初心者の方は特徴を理解して自分に合った方法を選びましょう。
ウキ釣り(浮き釣り)
ウキ(浮き)がエサの動きとアタリ(魚信)を視覚的に教えてくれる釣り方です。ウキが沈めばアタリだと一目で分かるため、初心者にはアタリの判断がしやすいのが利点です 。一定の棚(タナ=水深)にエサを留めやすく、狙った層を集中して探れるのもメリットです 。初心者や子供でも扱いやすいため、初めて釣り堀に行くなら基本的にはウキ釣りがおすすめと言われます 。一方でウキ釣りのデメリットは、設定したタナが魚のいる層と合っていないと全くアタリが出ないことです 。ウキ下の長さ(棚)をこまめに調整し、マダイの泳いでいる深さを探る必要があります 。手間はかかりますが、ハマれば連続ヒットも可能です。
ミャク釣り(脈釣り)
ウキを使わず、竿先や手元に伝わるわずかな魚信をとらえてアワセる釣り方です。仕掛けに余計な浮力がない分、魚に違和感を与えにくく、マダイがエサを咥えたときに警戒されにくいメリットがあります 。また、ウキ釣りのようにタナが固定されないため、幅広い層を探れるのも利点です 。特に活性が低く底付近に沈んでいる魚を狙う際や、逆に表層近くまで浮いてきた魚を狙う際にはミャク釣りが効果を発揮します。ただし、魚がエサを咥えたかどうかを自分の手の感覚だけで判断する必要があるため、アタリを取るのに慣れが必要です 。ウキという目印がない分だけ難易度は上がるので、ミャク釣りは釣り経験を積んでからチャレンジする方が無難でしょう 。
ワンポイント
初心者にはまずウキ釣りがおすすめですが、釣り堀ではタックルも重要です。竿は硬さ3号程度のしっかりしたもの長さは釣り堀に合わせて規定内で選びましょう。、リールも4000番クラスでパワーのあるものを用意しましょう 。大型魚が掛かる可能性もあるので、道糸はナイロン6号前後と太めでトラブルの少ないものが安心です 。
おすすめのエサとその使い方
釣り堀でマダイを釣る際のエサ選びも非常に重要なポイントです。マダイは意外とエサの好みがうるさい魚で、その日の状況や個体のクセによって好んで食べるエサが変わることがあります 。そこで、いくつかの定番エサを準備し、状況に応じて使い分けられるようにしましょう。
団子エサ(練りエサ)
釣り堀のマダイ狙いで定番中の定番といえば団子状の練りエサです。市販のマダイ用配合エサ(例:「マダイイエロー」など)を水で練って丸めた団子エサは、マダイが非常に好む餌として知られています 。マダイはこの練りエサに対して反応が良いのでまず試す価値があります。練りエサは色によって釣果が左右される場合があるため、黄色だけでなくオレンジや茶色など数種類のカラーを持って行き、反応を見ながらローテーションすると効果的です 。
オキアミ(エビ類のエサ)
オキアミは海上釣り堀でもよく使われる万能エサです。小さなエビの一種で、付けエサとしてマダイだけでなく他の魚にもアピールします。特に水温が低めで魚の動きがゆっくりな時期でも、オキアミのように柔らかく食べやすいエサはマダイが口を使いやすい傾向があります 。春先など魚の食欲が回復してくるタイミングではオキアミは効果的で、他にもアサリのむき身や魚の切り身と並んで実績のあるエサです 。付け方のコツは、針先をしっかりオキアミの身に隠すように刺して、マダイに違和感を与えないようにすることです。
エビ(シラサエビなど)
生きたエビやシラサエビ(シラウオエビ)は活きエサとしてマダイ狙いに人気のエサです。釣り堀によっては活きエビをその場で購入できるところもあります。エビはマダイにとって大好物であり、生きたまま動くエビはマダイの捕食本能を刺激してくれます。特に食い渋りの時でもエビなら反応するというケースも多いので、練りエサで反応がないときの切り札にもなります 。使い方は尾の付け根付近に針を刺して生かし、できるだけ自然に泳がせるようにすると効果的です。
そのほかにも、イワシやサバの切り身、青イソメ(ゴカイ類)、ササミ(鶏肉)など、釣り堀で試されるエサは多種多様です 。中にはマダイがトマトやバナナといったフルーツを食べるというユニークな例も報告されています 。基本的にはマダイ用配合エサ+エビ類を中心に用意しつつ、「今日は何が当たりエサか?」を探っていく姿勢が大切です。一種類のエサに固執するのではなく、複数のエサをローテーションして試すことで釣果アップにつながります 。状況に応じたエサの使い分けができれば、活性が高いときはより効率よく釣れ、食い渋っているときでもポツポツ拾えるようになるでしょう。
誘い方とアワセのコツ
マダイを釣るためには、エサをただ沈めて待つだけでなく魚にエサを発見・捕食させる工夫(誘い)も重要です。また、せっかくアタリがあっても上手にハリ掛かりさせなければ釣れないので、アワセ(フッキング)のタイミングも心得ておきましょう。
誘い方のコツ
釣り堀のマダイは放流直後こそ活発ですが、時間が経つと動きが鈍くなり底でじっとしていることがあります。そのような状況でエサを動かさずに待っていても、魚に気付かれないことも多いです。そこで有効なのが「誘い」をかけること。具体的には、竿先を上下に軽くしゃくってエサをふわっと浮かせ、再び沈める動作を何度か入れてみます。エサが少し動くことでマダイに「エサが逃げる」と意識させ、捕食スイッチを入れるイメージです。ポイントは小さく優しく動かすこと。大きく激しく動かしすぎるとエサだけが踊って逆にマダイに警戒されてしまいます 。あくまで「ちょっとエサが動いたかな?」程度のアクションで様子を見て、エサへの反応を引き出しましょう。
アワセのタイミング
ウキ釣りの場合、ウキに明確な反応が出てからアワセることが肝心です。マダイはエサを咥えてもすぐには走らず、違和感がないか確かめるように一瞬静止したり、小さくウキを揺らしたりすることがあります。ウキが軽くチョンチョンと動く程度の「前アタリ」ではまだ早合わせ禁止です。ウキがスッと完全に沈み込むのを待ってから、大きく竿を立ててアワセを入れましょう 。早すぎるアワセは針掛かりせずエサだけ取られる原因になりますし、逆にじっくり待つことでマダイがしっかりエサを飲み込んでくれるためフッキングが確実になります 。特に釣り堀では周囲に他の人もいて魚がスレやすい状況です。焦らずタイミングを見極めてアワセることで、バラシ(針外れ)を減らせるでしょう。
ミャク釣りの場合はウキがないため目視ではなく手感でアタリを取ります。僅かな重みを感じたり竿先がモゾっと動いたら、糸フケを素早く巻き取ってから鋭くアワセます。最初は難しいですが、何匹か釣るうちにコツが掴めてくるはずです。
釣れない時の対処法
釣り堀でなかなかマダイが釣れないときは、闇雲に続けるのではなく何かを変えてみることが重要です。以下のようなポイントを順番に見直してみましょう。
タナの調整
アタリがないときはまず棚(タナ=エサの深さ)を疑ってみます。マダイがいる層と仕掛けの深さがずれているとエサを見つけてもらえません。ウキ釣りならウキ止めの位置を変えて、浅すぎる場合は深く、深すぎる場合は浅く調整してみましょう 。基本は底付近から探り、徐々にレンジを上げていくのがおすすめです 。実際、釣り堀では「マダイはまず底を釣れ」と言われるほど底近くにいることが多いですが 、日によっては中層や上層に浮いていることもあります。こまめなタナ調整でマダイのいる深さを探り当てることが釣果アップにつながります。
エサのローテーション(種類・サイズの変更)
同じエサばかり使って反応がないときは、思い切ってエサの種類を変えてみましょう。例えば練りエサで反応しないなら生エビに替える、オキアミを試す、魚の切り身にする等です。マダイはその時々で好物が変わるため、「今日はこのエサしか食わない」というパターンもしばしばあります 。実際に釣り堀でも、周りを見るとある人だけが特定のエサで入れ食い状態、他の人は沈黙…なんてことがあります。そんな時は真似して同じエサを使ってみるのも手です。また、エサの大きさも重要な要素です。活性が低い時には大きなエサだと食い込みが悪くなるため、一回り小さく付けてみると途端に食うこともあります 。逆に活性が高い時は存在感のある大きめのエサや動きのある活きエサでアピールした方が効果的です 。このようにエサをこまめに交換・調整して、「今日の当たりエサ」を探り当てることが釣果アップの鍵です 。
周囲の状況観察
釣れていないと焦りがちですが、こんな時こそ周囲の様子をよく観察してみましょう。他の釣り人がどんな仕掛け・エサで釣っているのか、どのあたりのタナでヒットしているのかを盗み見るのも上達のコツです。特に常連らしき人がポツポツ釣れているなら、その人のマネをしてみる価値大いにありです。釣り堀のスタッフが近くにいれば、現在の狙い目のタナやエサを教えてもらうのも良いでしょう 。状況を的確に把握して対応を変えれば、「今日は渋いな…」という日でも一矢報いることができるかもしれません。
以上のように、釣れないときはタナ・エサ・誘い方を中心に柔軟に対処してみてください。何かしら手を打てば状況が好転する可能性は十分あります。
釣った真鯛の持ち帰り・食べ方のポイント
苦労して釣り上げたマダイは、新鮮で美味しく食べたいものです。釣った後の処理を適切に行えば、持ち帰ってから最高の状態で調理することができます。ここではマダイの鮮度を保つための締め方と、美味しく食べるための下処理(血抜き・熟成)のポイントを紹介します。
魚の締め方と血抜き
マダイを釣り上げたら、まず手早く締めて血抜きをしましょう。魚は釣られた後も暴れて体力を消耗したり、ストレスで筋肉に乳酸が溜まったりすると鮮度が落ちてしまいます。釣れたマダイはできるだけ早く〆める(瞬間的に殺す)ことが肝心です 。締める方法はいくつかありますが、一般的にはエラの付け根や脳天をナイフや専用ピックで刺して即死させます。その後すぐにエラ切りか尾切りを行い、海水を入れたバッカン(桶)で徹底的に血抜きをします 。血抜きは水を何度か入れ替えながら10~15分ほどかけてじっくり行うと良いでしょう 。血が抜けたら、今度は氷締めです。海水にたっぷり氷を入れた冷水(潮氷)に魚を15分程度浸け、魚の体を芯から冷やします 。こうすることで死後硬直がゆっくり進み、鮮度が長持ちします。持ち帰り用のクーラーには氷と魚を直接触れさせないようビニール等で仕切り、冷えた海水ごと持ち帰るとベストです 。ここまで丁寧に処理できれば、家に着く頃でもマダイはピチピチの新鮮さを保てます。
美味しく食べるための下処理(熟成)
血抜きまでしっかりできたマダイは、そのまま刺身や塩焼きにしてももちろん美味しいですが、さらに美味しく食べるには寝かせ(熟成)を取り入れるのがおすすめです。釣りたての魚は身が硬直していますが、冷蔵庫で一定期間寝かせることで身が柔らかくなり、酵素の働きで旨味成分(アミノ酸)が増していきます 。マダイの場合、内臓とウロコを処理して三枚におろした後、キッチンペーパーで水気を拭いてラップやジップロックで密封します。そしてチルド室(0〜5℃程度)で1日~数日程度寝かせると、刺身にしたとき身に甘みが出て格別の味わいになります。実際、海上釣り堀の達人は釣ったマダイを血抜き後に真空パックし、チルドで丸一週間寝かせて刺身にすることもあるほどで、驚くほど美味しくなるといいます 。家庭ではさすがに1週間は難しいかもしれませんが、1~2日置くだけでも違いが出ます。注意点は、長めに寝かせる場合はきちんと血と内臓を除去し、空気に触れないよう密封すること(雑菌繁殖を防ぐため)です。熟成させたマダイは刺身はもちろん昆布締めや寿司ネタにしても抜群です。ぜひ試してみてください。
まとめ
釣り堀でのマダイ釣りは、仕掛け選び・エサ選び・誘い方といったポイントを押さえるだけで釣果が大きく変わります。本記事で解説したように、ウキ釣りでタナを的確に合わせ、状況に応じてエサを工夫し、適切なタイミングでアワセを入れれば、初心者でもマダイを手にするチャンスは十分にあります。 釣り堀のマダイはコツさえ掴めば非常に釣りやすいターゲットですので、怖がらずにいろいろ試してみましょう。
そして、釣った後の処理も含めてが釣りの醍醐味です。せっかく釣り上げた真鯛は、ここで学んだ方法で丁寧に締めて持ち帰り、美味しくいただいてください。釣って楽しく、食べて美味しい真鯛釣りを存分に堪能しましょう!


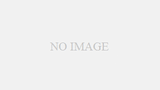
コメント