「タコ釣りに興味あるけど、難しそう…」そんな初心者の不安を解消します! 実は堤防からのタコ釣りなら、特別なエサもいらず道具も少なくて手軽に始められるんです。この記事では、タックル選び・釣り方・おすすめの時間帯やコツまで、初心者がタコ釣りデビューするために必要な情報を完全網羅しました。読み終えれば、今週末にでも堤防タコ釣りがスタートできますよ!
そもそもタコ釣りってどんな釣り?初心者に人気の理由
「タコって釣れるの?」そう思う方も多いかもしれませんが、実は最近じわじわ人気が高まっているのが“タコ釣り”。特に堤防から狙える手軽さと、高級食材が釣れる楽しさで、釣り初心者にも大人気です!まずはその魅力から見ていきましょう。
意外と手軽!タコ釣りの魅力とは?
タコ釣りは一見ハードルが高そうですが、実は意外と手軽な釣りです。魚を釣る場合とは異なり、タコがエサ(ルアー)に抱き付いたときの「ずっしりとした重み」は独特で、一度味わうと病みつきになります 。引きが強烈というより、根掛かり(ルアーが底に引っかかった)と間違えるような「ヌンッ」という重い違和感が伝わってくるのがタコ特有のアタリです 。この独特の感触と、タコを引き剥がすスリルが面白さのポイントです。
さらに、自分で釣ったタコは格別のごちそうになります。タコはマダコなど国産のものは漁獲量が少なく市場価値が高い高級食材です 。特に関西では明石ダコなどブランド化されるほど美味しいタコが知られていますが、そんな高級タコを自分で釣って味わえるのがタコ釣りの醍醐味です。獲れたてを調理すれば、歯ごたえや甘みが段違いですよ。
初心者でも釣れる?どこでできる?
結論から言えば、**タコ釣りは初心者でも十分釣れます。**タコは堤防や漁港など身近な岸から狙えるので、足場の良い防波堤であれば安全に楽しめます。実際、関西の大阪湾では毎年初夏になると波止場でマダコ釣りが盛期を迎え、100~300g程度の「新子」(生まれて間もない小ダコ)が数釣れるため、初心者の入門に最適とされています 。ちょっと慣れれば一日で20杯・30杯と釣り上げる人もおり、手軽で人気のターゲットなのです 。
堤防からのタコ釣りは、足場の良い防波堤や岸壁で行えます。特にテトラポッド周りや岸壁の継ぎ目といった身近なポイントにもタコは潜んでいるため、わざわざ船を出さなくても大丈夫です 。関西エリアでは、渡船で渡る沖堤防も含め、武庫川一文字や神戸第七防波堤(通称・七防)、大阪・堺港の新波止など有名なタコ釣りスポットがいくつもあります 。夏から秋にかけてはこうした堤防で安定した釣果が望め、特に6~8月頃は小型の数釣りシーズンなので初心者にもおすすめの時期です 。タコ釣りのベストシーズンである夏場(6月~9月頃)は水温が上がりタコの活性が高くなりますし、秋口まで比較的狙いやすいでしょう 。
タコ釣りに必要な基本タックルを紹介!
「道具って何を揃えたらいいの?」そんなあなたも大丈夫!タコ釣りに必要なタックル(竿・リール・ラインなど)は、実はそんなに多くありません。この章では、初心者にぴったりなアイテムを実例付きでわかりやすく紹介していきます。
ロッド(竿)はこれを選べばOK!
タコ釣り専用ロッドがなくても大丈夫。エギングロッド(アオリイカ釣り用の竿)や硬めのシーバスロッドで代用可能です 。目安として長さ7フィート(2.1m)前後、先調子でバット(根元)にパワーがある竿が理想的です 。堤防からのタコ釣りでは、タコが吸盤で岩に張り付いたのを引き剥がす強いパワーが必要になるため、ロッドの**硬さ(パワー)**はしっかりしたものを選びましょう 。エギングロッドやシーバスロッドの中でもHクラス(ヘビー)程度の硬さがあるものが向いています。手持ちのロッドでは心配…という方も、市販の比較的安価な専用ロッド(例:メジャークラフト「岸タコ」モデル等)もあるので検討しても良いですね。いずれにせよ「柔らかすぎず張りのあるロッド」を選べばOKです。
また長さについては、堤防での取り回しを考えると7~8ft程度が扱いやすいでしょう。あまり短いと遠投がしにくく、長すぎると操作が大変です。エギングロッドならだいたいその範囲に収まります。初心者はまず手持ちのエギングロッドや硬めシーバスロッドで試し、慣れてきて本格的にやりたくなったら専用ロッド購入を検討すると良いでしょう。
リール・ラインの選び方
リールはスピニングリールでもベイトリールでも構いませんが、初心者には扱いやすい小型スピニングリールがおすすめです 。サイズはだいたい2500番~3000番クラス(メーカーによっては3000~4000番相当)を目安に選びましょう 。このクラスなら太めのラインも十分巻けて、ドラグ(糸の出る力加減)もそれなりに強いので安心です。実際、タコ釣り用にはPEライン(編み糸)1.0号前後を100m程度巻いておくと良いと言われています 。PE1号はポンド換算で20~25lb(約9~11kg)の強度があり、直径も細いので飛距離と強度のバランスがとれます 。リーダー(ハリス)も忘れずにつけましょう。**フロロカーボンの20lb程度(5号前後)**を1mほど先糸として結べば、根ズレ(岩との摩擦)による高切れ防止になります 。この組み合わせ(PE1号+20lbリーダー)は岸タコ狙いの定番で、初心者には扱いやすい太さです 。
ラインはできるだけ強めを使うことがタコ釣りでは肝心です。タコ釣りは障害物の多いエリアを攻めるので根掛かりも頻発します。あまりに細いラインだと仕掛けを回収できずに高価なタコエギを何個もロスト(紛失)してしまいがちです 。PE1号程度あればある程度の根掛かりにも耐えますし、小型タコなら引き抜ける強度もあります。それでも万一根掛かりしてしまった場合は、無理に引っ張らず糸を一度緩めてからロッドを煽ったり、逆方向に引いてみると外れることがあります 。
ドラグ設定はタコ釣りではやや強め(出ない程度)に締めておく人も多いです。理由は、タコが掛かった際に一気に引きはしませんが、ドラグが緩すぎるとアワセ時に滑ってフッキングが決まらない可能性があるためです 。ただし根掛かりのときはドラグを緩めて対処するなど、状況に応じて調整しましょう。
タコエギってなに?おすすめエギ3選
「タコエギ」とは、タコ専用のルアー(疑似餌)の一種で、見た目はエビ型のエギに大きなカンナ(針)が付いたものです。アオリイカ用のエギとは異なり、着底重視で沈みが早く、針もタコを引っ掛けやすい形状になっています 。タコ釣りではエサを使う「テンヤ釣り」という方法もありますが、最近はエサ不要で手軽なタコエギ釣法が主流で人気です 。タコエギは投げて底をズル引きする釣り方に適しており、小型から大型まで幅広いサイズのタコが狙えます 。アオリイカ用エギでは沈下速度が遅く針も小さいためタコには不向きなので、必ず専用のタコエギを用意しましょう 。
針の形状とカラー選びもタコエギでは重要です。タコエギの針(カンナ)はイカ用より大きく頑丈で、タコが抱きついた際にしっかりフッキングできる形になっています。カラーは派手めで目立つ色が効果的です。タコ釣りの基本色とされるのは、「黄色系」「グリーン系」「オレンジ/ピンク系」、そして「白系(夜光やパールホワイト)」などです 。特に蛍光イエローは現在の定番カラーで、水中でも目立ちタコへのアピール力が高いと言われます 。白系(夜光カラー)も海底で視認性が高くタコが見つけやすい色です 。まずはこうした基本カラーを数種類用意して、状況によってローテーションすると良いでしょう。
初心者におすすめの実績タコエギを3つ紹介します。
タコやん(デュエル)
初めて迷ったらコレ! ボディ内部に浮力材が入っており、海底で立ち気味に浮く設計なので根掛かりしにくく初心者でも使いやすいエギです 。3号~3.5号サイズが扱いやすく、関西の波止タコ釣りでも定番の一つです。黄色やピンクなど明るいカラーが人気。
デビルエイト(ワンナック)
タコエギブームを牽引した有名ルアー。タコ釣りの達人「デビル渡辺」氏監修のシリーズで、8本の足のようなラバーが付いた独特の形状が特徴。大ダコにも耐える頑丈なフレームとフックを備え、初心者からベテランまで愛用者が多いです 。30g前後と適度な重さで遠投も可能。
オクトパスタップ(マルシン漁具)
2008年発売のタコエギ初号機とも言われるロングセラー商品 。斜めに浮くバランス設計で根掛かりを減らし、ダブルの大針で抱きついたタコをしっかりキャッチします 。3.5号(約32g)などサイズ展開もあり、実績十分のエギです。
他にも100円ショップの安価なタコエギから、有名メーカーの凝ったものまで色々あります。それぞれ特徴がありますが、まずは実績のある定番エギから使ってみるのが成功への近道です。釣れないときはカラーやタイプを変えてみることで、思わぬヒットにつながることも多いですよ。
釣り方の基本!堤防から始めるタコ釣りステップ
「道具はそろえたけど、釣り方がわからない…」そんな初心者の方に向けて、堤防でのタコ釣りステップをていねいに解説!キャストの仕方からアタリの取り方、釣れたときの取り込み方まで、一連の流れがしっかり身につきます。
キャスト・ズル引き・アタリの取り方
堤防タコ釣りの基本的な動作はシンプルです。まず狙いたいポイントへ向けてタコエギをキャスト(遠投)し、しっかりとエギを底まで沈めます。着底したら、あとはリールをゆっくり巻き取りながらエギを底面に引きずるようにズルズルと引いてくるだけです。「ズル引き」と呼ばれるこの操作で、エギを底にいるタコにアピールします。ときどき竿先を小さくシャクって(チョンチョンと動かして)エギを揺らし、数秒止める…という動作を繰り返すと効果的です 。タコは匂いや動きに反応してエギに近寄り、抱きついてきます。
肝心なのはタコのアタリ( bite )を感じ取ることです。タコの場合、魚のように明確な「ググッ」という引きではなく、まるで海藻かゴミを引っ掛けたかのように急に重くなる違和感で伝わってきます 。具体的にはエギを引いていて「ヌンッ」と竿先に重みが乗る感じや、一瞬引っかかったような抵抗を覚えたら、それがタコが抱きついたサインです 。慣れないうちは根掛かりと区別が難しいですが、違和感を感じたら**即座に糸フケを巻き取り、大きくアワセ(フッキング)**を入れましょう 。竿でグイっと持ち上げるように力強く合わせるイメージです 。タコが乗っていれば、エギに抱きついたタコの足が針に引っ掛かり釣り上がります。空振りでも気にせず、どんどん合わせていくことが大事です。タコは瞬間的に逃げたりしないので、多少待ってしっかり抱かせてから合わせるのも一つの方法ですが 、初心者のうちは判断が難しいため違和感があればすぐアワセでOKです。
ヒットがなければ、数メートル引いてまた投げ直すか、少し横に移動して別のコースを探ってください。同じ場所ばかり探っていても効率が悪いので、堤防際を歩きながら広範囲に探ることが釣果アップにつながります 。
タコがエギに抱きつく瞬間はこの写真のように突然訪れます。一度抱きついたタコはエギにしがみついて離れないため、違和感を感じたら迷わず合わせましょう。タコの足には吸盤があり、岩やエギに強力に吸着します。強めのフッキングで剥がしにかかることで針がしっかり掛かり、逃げられにくくなります 。
ヒットしたらこうする!取り込みのコツ
タコがヒットしたら、焦らず対処しましょう。まず、一定のテンション(糸の張り)を保ったままリールをゆっくり巻き上げます。タコは掛かっても暴れ回る魚とは違い、自分の吸盤で岩や壁に張り付こうと踏ん張ります。そのため、こちらが強引に引っぱるとタコの足が切れたり、エギから外れてしまう恐れがあります。竿を立てすぎず、適度にタコの重みを感じながらゆっくり巻いてください。もし途中で急に動かなくなった場合、タコが岩に張り付いている可能性があります。そのときは一旦テンションを緩めてみましょう。糸の緩みでタコが安心して動き出した瞬間に再度巻き上げると、ふっと剥がれることがあります。
足元までタコが浮いてきたら、タモ網(ランディングネット)で掬い取るのが確実です。特に1kgを超えるような大きなタコは重く、抜き上げようとするとラインブレイクのリスクがあります。網ですくうのが難しい場合や網が無い場合、**ギャフ(タコギャフ)**と呼ばれる先端に針が付いた棒で引っ掛けて持ち上げる方法もあります。ただ初心者には扱いが難しいので、できればコンパクトな玉網を用意しましょう。岸壁にずり上げる際は、タコが最後に足で踏ん張って抵抗することもあるので、油断せず竿を起こしてタコの重みが常に針に掛かる状態をキープしてください。無理に抜き上げようとしてタコがポチャン…と海に落ちてしまうのは初心者によくある失敗です。
取り込んだタコは噛みつく恐れがあります。タコの口には硬いクチバシのような器官があり、噛まれると結構痛いので指を近づけないよう注意しましょう 。暴れて逃げないようにしっかり掴んでください。タコは意外と腕力(?)が強いので、バケツに入れても吸盤で這い出して脱走することがある点にも気を付けてください 。
釣りやすい時間帯や潮回りは?
タコは基本的に夜行性の生き物です。そのため、夜間は活発に捕食行動をとり特によく釣れる傾向があります 。しかし、防波堤での夜釣りは足元が暗く初心者には危険も伴います。そこで**朝まずめや夕まずめ(日の出前後や日没前後)**の時間帯が狙い目です 。薄暗い時間帯でタコも活動的になりますし、人間にとっても周囲が見えて安全に釣りができます。経験上、朝夕のまだ薄暗い時間にヒットが集中することが多く、真っ昼間より効率が良いです。「夜>朝・夕>日中」の順で期待度が高いと覚えておきましょう 。
潮回りでは、満潮前後の潮が動き出すタイミングが狙い目です。特に満潮から下げに転じて流れが出始める頃によく釣れる傾向があります 。反対に潮止まり(上げ止まり・下げ止まり)で水の動きが鈍い時間帯はタコの反応も鈍りがちです 。潮位が大きく動いているときや、逆に速すぎて底が取りづらい潮流のときも釣果は安定しません 。要は「適度に潮が動いている時間」がチャンスタイムといえます。
他にチェックしたいのが水の濁りや天候です。タコは雨などで川から大量の真水が流れ込んで水質が変化するのを嫌う習性があります 。大雨の直後などは浅場から深場へ動いてしまい、途端に釣れなくなることもあります 。特に河口近くのポイントでは雨の影響が大きいので、雨の日やその翌日は避けた方が無難でしょう。また、風が強い日はエギが思うように底を取れなかったり、ラインが風で煽られてアタリが取りづらくなります。できれば風速5m以下くらいの穏やかな日を選ぶと釣りやすいです。真夏は炎天下での釣りになるため、熱中症対策(帽子やドリンク携行)もお忘れなく 。
初心者がやりがちな失敗&釣果アップのコツ
せっかく釣りに行ったのに「全然釣れなかった…」なんて経験、避けたいですよね。この章では、初心者がついやってしまいがちな失敗と、それを防ぐコツを伝授!ちょっとした工夫で釣果が大きく変わります。
よくあるミス3選(仕掛け・誘い方・場所選び)
タコ釣り初心者が陥りがちな失敗を3つ挙げます。当てはまらないよう注意しましょう。
1.仕掛けトラブル(ライン切れ・根掛かり連発)
ラインや仕掛けの選択ミスで、タコエギを次々失くしてしまうケースです。例えばラインが細すぎたりリーダーを付けていなかったりすると、少し根ズレしただけでプツンと切れてエギをロストしてしまいます 。タコ釣りは根掛かりとの戦いでもあるため、最初から太めで強いライン・リーダーを使うことが大切です 。また、根掛かりした際に無理に引っ張りすぎるのもNG。切れる前に場所を変えたり、竿を煽る方向を変えるなど工夫しましょう。
2.誘いが速すぎる/雑すぎる
タコエギの動かし方が速すぎると、タコにエギを抱かせる隙を与えず逆効果です。タコは俊敏に泳ぐ魚ではないので、エギはゆっくり見せてじっくり誘うのがコツ。せっかくタコが興味を示して近寄っても、エギを急に跳ね上げたり早巻きしてしまっては抱きつく暇がありません。基本は「ゆっくりズル引き、たまに小さくシェイク」くらいが丁度良いです 。逆に全く動かさないのも発見してもらえないので、適度にアピールしましょう。またアタリに気付かず引き続けてしまうミスもあります。違和感を見逃さないためにも、竿先やラインに集中して手元に伝わる感触を研ぎ澄ませてください。
3.ポイント選びのミス
「根掛かりが怖いから…」と砂地の何もない場所ばかり狙っていませんか? 実はそれが釣れない原因かもしれません。タコは基本的に隠れ家となる障害物や岩場のある所に潜んでいます 。何も障害物のないツルツルの海底にもいないわけではありませんが、明らかに数は減ります。初心者は根掛かりを嫌って安全な場所を狙いがちですが、それではタコにも出会いにくいのです。多少根掛かりリスクがあっても、テトラ帯や岩の多いエリアを攻める勇気も必要です。堤防の継ぎ目や沈み根周りなど「いかにもタコが居そうな所」を狙いましょう 。逆に、干潮時に干上がるような浅すぎる場所や、淡水が流れ込む真水交じりの場所(大雨後の河口など)は避けた方が無難です 。
釣れる場所と釣れない場所の違いは?
タコが釣れる場所にはいくつかの共通点があります。それは**「エサとなる生物が多いこと」と「タコが隠れる構造物があること」**です 。例えば防波堤の壁際は定番ポイント。壁に付着したカニや貝類が多く、タコにとって格好のエサ場になっています 。特に堤防の継ぎ目やひび割れ部分、スリット(排水溝)などはタコが身を潜める最高の住処なので、こうした場所は重点的に探りましょう 。実際、堤防沿いにタコエギを落として歩いていくと、継ぎ目ごとに「ここにもタコ、あそこにもタコ」という具合に次々ヒットすることがあります。
また、テトラポッド周辺や消波ブロック帯も一級ポイントです。テトラの隙間には小魚やカニが住み着き、それを狙ってタコも集まります。足場が悪く難易度は上がりますが、テトラ帯で釣れるタコのサイズは比較的大きい傾向があります。一方、コンクリートで整備された何も起伏のない護岸などはタコのエサも少なく、ポイントとしては今ひとつです。沖にも沈み根や捨て石など見えない障害物がある場合がありますが、そういう場所では「エギを引いていて頻繁に引っ掛かりを感じる所」は高確率でタコの住処です 。逆に全く引っ掛かりすらないようなツルツルの海底はタコも少ないでしょう。
要するに「根(障害物)がある場所=タコがいる場所」です 。多少の根掛かりと上手に付き合いながら、障害物周りを丁寧に探ることがタコ釣りでは欠かせません。「釣れる場所」と「釣れない場所」の違いは、水中の地形や構造物の有無に加え、潮通しやエサの量なども関係します。複数の釣り場で試してみて、「ここはよく釣れる」「ここは渋い」という体感を蓄積していくと、自分なりの実績スポットがわかってくるでしょう。
なお、釣り場によってはタコに漁業権が設定されていることがあります 。勝手に採捕すると密漁となり罰せられる場合もありますので、地元の情報を事前に確認してルールを守りましょう。また極端に小さいタコ(例えば手のひらサイズ以下)は資源保護のためリリースするのがマナーです 。
釣果アップのためのワンポイントアドバイス
最後に、さらに釣果を伸ばすためのコツをいくつか紹介します。
エギのローテーションを活用
タコの反応が悪いと感じたら、遠慮なくタコエギの種類やカラーを変更してみましょう。同じ場所でも、色や動きの違うエギに変えた途端に抱きついてくることがあります。例えば朝マズメは実績のピンク系で攻め、日が高くなって渋くなったら黄色や白系のアピールカラーに替える、といった工夫です。「当たりエギ」は日によって変わるので、何種類かローテーションしてタコの好みに当てていきます。
誘い方にメリハリを
基本はスローなズル引きですが、ときには変化をつけることも有効です。例えばエギを**ボトムでしばらくステイ(停止)**させて、タコに考える時間を与えるのも手です。逆に反応がないときは、小刻いシェイクを数回入れてホコリを立てるように砂煙を起こし、注目させてからピタッと止める、という「誘って止める」のメリハリで抱かせる作戦もあります。タコの気分に合わせて、動かしすぎずサボりすぎず、緩急をつけてみましょう。
広範囲を探る/ランガン
タコ釣りはラン&ガン(移動を繰り返す釣法)との相性が抜群です。一箇所で粘りすぎず、ある程度探って釣れなければどんどん移動しましょう 。特に堤防沿いの釣りは、同じ場所に何匹ものタコがいることは少ないです。1匹釣れたら少し場所を変えて次を狙う方が効率的です。「足で稼ぐ」イメージで、こまめに立ち位置を変えながら探り歩けば、その日のチャンスを最大限生かせます。
タコの習性を利用
タコは一度餌と認識したものにはしつこく抱き付く性質があります。仮に一度乗せそこねても、すぐに諦めず同じ地点にエギを落としてみてください。タコがまだ近くにいれば再び抱き付いてくることがあります。また、タコは視力があまり良くない代わりに嗅覚が鋭いとも言われます。そこで、エギにイワシや鶏肉など小さなエサの切り身を縛り付けて匂いを足す“欲張り仕掛け”を試す人もいます。多少手間は増えますが、どうしても釣れないときの奥の手として覚えておくと良いでしょう。
タックルメンテナンス
地味ですが釣果アップに効いてきます。タコ釣りはどうしても根掛かりとの戦いでラインが傷つきやすい釣りです。定期的にラインの先端をチェックし、毛羽立っていたらカットして結び直す、リーダーを交換する、といったケアを怠らないようにしましょう。強度万全で挑むことが、ここ一番の大物を逃さないポイントです。
以上のコツを踏まえて釣りをすれば、きっと今まで以上にタコの顔を見る機会が増えるはずです。小さな工夫と心掛けが釣果に直結するのも釣りの面白さですね。
釣れたタコの締め方・持ち帰り・下処理のやり方
「タコってどうやって持って帰るの?」そんな疑問を解決!釣ったタコを美味しく食べるための締め方・保存方法・料理のコツまで、初めてでもできる方法を紹介します。釣りの楽しさは、食べるところまで含めて完結です!
タコの締め方と保存のコツ
いよいよ念願のタコをゲットしたら、最後まで美味しくいただくために正しい締め方と保存方法を実践しましょう。タコは釣ってから放置するとストレスで味が落ちたり、逃げ出したりする恐れがあります。釣れたらできるだけ**すぐに締めて(絞めて)**しまうのが基本です 。
**締め方(活け締めの方法)**はとても簡単です。タコの急所は「目と目の間の少し下あたり」にあります 。そこにナイフの切っ先かキリ(もしくはキリの代わりになるハサミの先端)を突き刺し、神経を断つようにします 。具体的にはタコの頭(胴体)を裏返し、目と目の間の位置をハサミでチョキンと切断すると確実です 。そうするとタコの体色がスッと白っぽく変わり、筋肉の緊張が解けてぐったりと動かなくなります 。これが締まったサインです。なお、タコは締める前だと腕(足)が絡みついて暴れたり、口で噛みついてくることがあります。締める作業中も決してタコの口元(足の付け根中央にあるクチバシ)に指を近付けないように注意しましょう 。
締めたタコは持ち帰りの際に鮮度を保つ工夫をします。まずクーラーボックスに入れるのですが、その際タコを直接氷水に触れさせないのがポイントです 。ビニール袋にタコを1杯ずつ入れて密封し、氷の入ったクーラーに入れましょう 。複数のタコを一緒の袋に入れると、互いの吸盤で身が傷つくことがあるのでできれば分けます 。氷で急冷することで鮮度が保たれますが、真水(氷が溶けた水)にタコが触れると風味が落ちるので直接触れないよう袋詰めするわけです 。また袋に入れる際はタコが重ならないように平たく広げて入れると、余計な重みがかからず身崩れ防止になります 。
もし「できれば生かして持ち帰りたい」という場合は、洗濯ネットや専用のタコ用ネットにタコを入れて脱走を防ぎ、海水を張ったバケツやクーラーに入れて酸素ポンプでエアレーションしながら持ち帰る方法もあります 。ただしこの方法は手間もかかるうえ、真夏だと水温上昇でタコが弱ったりするリスクもあるため、初心者は素直に締めて冷やして持ち帰るほうが無難でしょう。
自宅での下処理と保存方法
タコを持ち帰ったら、食べる前に**下処理(下ごしらえ)をします。まず行うべきはヌメリ取り(ぬめり取り)**です。タコの体表は粘液で非常にヌルヌルしています。このままだと食感も悪く、調理もしづらいのでしっかり落としましょう。
家庭で簡単にできるヌメリ取りの方法は**「塩もみ」**です。バケツやボウルにタコを入れ、食塩を一掴み(タコ1匹に対し大さじ1~2程度)まぶしてよく揉み込みます 。さらに、もし目の粗い金属製ザルがあればその上でタコを揉むと効果的です 。ザルの網目がタコのヌメリと汚れをこそげ落としてくれます 。力を入れすぎるとタコの身が傷むので、ほどほどの強さで全体を擦り洗いしましょう。しばらく揉むと茶色い泡が出てきますので、水で洗い流します。これを2~3回繰り返すと、表面がキュッキュと締まった感じになり滑りがなくなります 。特に足の付け根あたりはヌメリが残りやすいので、根元から先に向かってしごくように洗うと綺麗に取れます 。
ヌメリが取れたら、内臓の処理もしておきます。タコの胴体をひっくり返して中の内臓を取り出し、墨袋をつぶさないよう注意しながら取り除きます 。ついでに目玉と口(クチバシ)も切り落としておくと良いでしょう。ここまでやれば下処理完了です。すぐ料理に使わない場合は、この段階で保存します。
保存方法は冷蔵でも冷凍でも可能ですが、**鮮度維持という点では冷凍保存がおすすめ】です。実はタコは冷凍しても味が落ちにくい上、冷凍後に解凍するとヌメリも簡単に取れるという利点があります 。釣れたタコを一度冷凍すると粘液も凍結し、半解凍状態で流水にさらせばヌメリがスルッと取れるのです 。処理も楽になりますし、美味しさも保てるので、すぐ食べないなら一旦冷凍してしまうのが筆者のおすすめです 。
冷凍保存する際は、できるだけ早く低温で凍らせるのがコツです。下処理をしたタコをキッチンペーパーで水気をふき、1杯ずつラップやフリーザーバッグに密封して冷凍庫へ入れましょう。金属バットなどに乗せて急速冷凍すると臭みも少なくなります。なお冷凍前に無理にヌメリを完全に取ろうとしなくても、前述の通り解凍時に取れるので大丈夫です 。内臓・目・口だけ取ったらサッと拭いて即冷凍、でOKです。食べるときは冷蔵庫でゆっくり解凍するか、流水で半解凍にしてヌメリを洗い落としてから調理します。
冷蔵保存(チルド室などで数日内に食べる場合)なら、塩もみ後によく洗ったタコをキッチンペーパーで包み、更にラップや袋で密封して冷蔵庫へ入れます。こうすることで乾燥と臭い漏れを防げます。なるべくその日のうちか翌日には調理しましょう。
簡単タコレシピ3選(茹で・タコ飯・唐揚げ)
釣れたタコは新鮮そのもの!手間をかけなくても十分美味しいですが、ここでは初心者でもできる簡単レシピを3つ紹介します。
1. タコのやわらか茹で
一番シンプルで素材の味を楽しめる調理法が茹でダコです。下処理したタコをそのままお湯でボイルするだけですが、茹で方のコツがあります。沸騰したお湯にいきなり全部入れるのではなく、まずタコの頭(胴体)部分を手で持ち、足先からお湯にくぐらせていきます 。そうすると足がくるんと丸まります。足先が赤くなって丸まったら、一気に全身をお湯に沈めます 。タコの大きさにもよりますが、中火で3~5分ほど茹でればOKです 。茹ですぎると硬くなるので、小さめのタコなら3分、大きめでも5分程度で火を止めましょう。茹で上がったら氷水に取って急冷し、粗熱が取れたら薄切りに。プリプリ食感の茹でダコ刺しはもちろん、酢味噌和えやマリネ、カルパッチョにしても絶品です。塩を少し入れて茹でると下味が付いて◎。
2. タコ飯(タコの炊き込みご飯)
タコの旨味をお米に染み込ませた炊き込みご飯は、初心者でも失敗しにくい人気料理です。基本の材料は茹でタコ、ショウガ、醤油、みりんだけととてもシンプル 。作り方は、まずお米2合を研いで30分ほど浸水させておきます。その間に茹でダコ(生でも可)を食べやすい一口大に刻み、ショウガを千切りにします。炊飯器に米と醤油大さじ2・みりん大さじ2を入れ、2合の目盛りまで水を足して軽く混ぜます 。そこに刻んだショウガとタコを乗せて普通に炊飯するだけ。 炊き上がったらさっくり混ぜ、お好みで彩りに刻みネギやゆで枝豆を散らせば完成です。タコの出汁がご飯に染みて噛むほどに旨味が広がる一品で、「これならいつでも作れる!」とリピートする人も多いです 。シンプルなだけにタコの鮮度が味を左右するので、釣りたてタコでぜひ味わってみてください。
3. タコの唐揚げ
居酒屋の定番メニュー「タコの唐揚げ」も、実は簡単に作れます。下処理済みのタコ(生でも茹ででも可)を一口大に切り、醤油・酒・おろしショウガ・おろしニンニクなどで下味をつけて15分ほど漬け込みます 。その後、キッチンペーパーでタコの表面の汁気を軽く拭き取り、片栗粉をまぶします 。あとは170℃程度に熱した油でカラリと揚げれば出来上がり 。衣が剥がれないよう、タコ同士がくっつかないように1個ずつそっと油に入れましょう。揚げ時間はタコ自体には火が通っているので表面がキツネ色になる程度(だいたい2~3分)が目安です。二度揚げするとよりサクッと仕上がります。醤油とショウガの風味が効いたジュワッと美味しいタコ唐揚げはビールとの相性も抜群です。お好みでレモンを絞ったりマヨネーズをつけたりして召し上がれ。
この他にも、タコを使ったレシピはたくさんあります。刺身や酢の物はもちろん、たこ焼きやタコパスタ、ガーリック炒めなどアレンジは無限大。釣ってきたタコだからこそ味わえる新鮮さで、いろいろな料理にチャレンジしてみてください。「自分で釣ったタコを料理して食べる」という体験は、釣り人にとって最高の贅沢ですよ。
まとめ
- タコ釣りは初心者でもすぐ始められて釣果が出やすい手軽な釣りです。特別な高級タックルは不要で、堤防など身近な場所から狙える気軽さが人気の理由です。釣れたときの喜びと達成感は格別で、「自分で高級食材を手に入れた!」という満足感も味わえます。
- 必要な道具は最小限でOK。エギングロッドや硬めのシーバスロッドに小型スピニングリール、太めのPEラインと専用タコエギがあれば十分です。釣り方も底をゆっくり引くだけと簡単で、コツさえ掴めば誰でもタコを釣ることができます。朝夕の満潮前後といったタイミングを狙えば、堤防からしっかり釣果を伸ばせるでしょう。
- 安全とマナーを守って楽しく挑戦しましょう。この記事を参考に準備を整えれば、あなたも今週末には念願のタコ釣りデビューができるはず! 足元に気を付けて堤防へ出かけ、ぜひタコとの駆け引きを存分に楽しんでみてください。釣って良し・食べて良しのタコ釣りで、釣りの新たな魅力に出会えること間違いなしです!


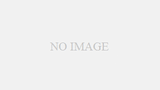
コメント